「まずは構造化して考えて」
「情報が構造化されてないから、整理し直して」
新人コンサルタントがほぼ間違いなく先輩コンサルタントやマネージャーに指摘される言葉。
それが “構造化” という言葉です。
そもそも「構造化」とは?
なぜ「構造化」が重要?
今回の書評記事は、昔の自分に送るように「いや、構造化って言葉だけ言われても、具体的に何をどう考えれば、あなたの言う “構造化” になるんですか」と悩む新人コンサルタントに向けた記事です。
『構造化思考トレーニング コンサルタントが必ず身につける定番スキル』のおすすめ読者
- 「構造化して考えろ」という指摘に悩む新人コンサルタント・コンサル未経験の転職者
- 生産性を高めて残業時間を減らしたいビジネスパーソン
- 新人コンサルタントの育成に悩む新米マネージャー
ここで質問です。
「出世をして年収を上げたい・キャリアアップをしたい!」
「副業/複業に挑戦したい!」
「投資をして不労所得を得たい!」
筆者「きつね」と同じく、あなたもそう考えたことはありませんか?
書籍から知識を得ることであなたの目的達成に近づきますが、本を購入すると費用も場所も負担になりますよね・・・。
そんなお悩みを持つあなたにオススメするのが『Amazon Kindle Unlimited』です。
200万冊以上の本が読み放題になるAmazon(アマゾン)の電子書籍読み放題サービスで、「あなたの年収を上げる・サイドFIRE実現を助ける・不労所得をゲットする」本が見つかります!
電子書籍よりも紙の本が好きという方もいるかもしれませんが、初めてご利用の方は30日間の無料体験が可能です。
使いにくければ30日経過する前に解約をしましょう。
無料期間終了後は月額980円で使えます。
「1か月だと読み切れないし、1年だと長すぎるかも・・・。」
もちろん、いつでも解約できるので3か月くらい集中して本を読み漁って解約するという使い方でも良いかもしれません。
>>Amazon Kindle Unlimitedを無料で試してみる\ 初回利用は30日間無料!200万冊以上の本が読み放題 /
『構造化思考トレーニング コンサルタントが必ず身につける定番スキル』概要
構造化思考がコンサルタントとして仕事をするうえでは基礎になります。
本書の前半では「構造化思考とは何か」を多くの図解を掲載しながら、解説してくれています。
「構造化をするうえでの観点」や「イシューツリーとロジックツリーの違い」など、ある程度経験を積んだコンサルタントでも振り返りとして学びになることも掲載されています。
後半は実践編となっており、5つのケーススタディを通じて、構造化思考を駆使した論点整理とアウトプット・タスク設計の過程を疑似体験できます。
シニアコンサルタント以下ではマネージャーが論点を設定してくれることも多く、各論点を検証するためにタスクをこなしていることも多いでしょう。
しかし、「上位職は何を考えて自分にタスクを振っているだろう?」と考えることは、自身のタスクに対する意味付けを大きく変えてくれます。
本書は「構造化思考の入門書」といった内容になっていますが、一定の経験があるコンサルタントが読んでも学びはあります。
マネージャー以上の職位についている方は、コンサルタントとしての修行を通じて身に付いている考え方かもしれませんが、こういった基礎トレーニングを継続して行うことはで新たな気付きを得ることもありますよね。
筆者「きつね」は「コンサルティングの提案を考えるときの論点整理をしっかりやらないと、デリバリーに入ったときに苦労する」という経験を(残念ながら)多くしています。
それは、構造化思考が弱く論点をブレイクダウンしきれていないし、アウトプットに繋がるタスクのアプローチ設計も曖昧に済ませているからなのだと本書を読んで痛感しました・・・。
このようにコンサルタントとして働いているビジネスパーソンであれば職位関係なく学びを得られると思います。
著者:中島 将貴(なかじま まさたか)
野村総合研究所で幅広いコンサルティングに従事され、2022年度より野村総合研究所のグループ会社であるブライアリー・アンド・パートナーズ・ジャパンに出向。
米国MBAと中小企業診断士の肩書も持たれていて、構造化思考力を駆使して活躍されてきたのでしょうね。
著者情報
- 中島 将貴(なかじま まさたか)
- 2008年、早稲田大学政治経済学部卒業後、野村総合研究所入社
- 2019年、米国エモリー大学ゴイズエタビジネススクールMBA修了
- 2022年度よりブライアリー・アンド・パートナーズ・ジャパン(野村総合研究所グループ会社)出向
- 中小企業診断士
『構造化思考トレーニング コンサルタントが必ず身につける定番スキル』目次・章構成
本書は3章に分かれています。
最初に「構造化思考の重要性」をキークエスチョンという言葉を軸にして解説してくれています。
次は「どのようにしたら構造化思考を実践できるのか」を3ステップで教えてくれるので、最後の3章で実践してみるという流れになっています。
構造化思考力に自信のある方は、力試し的に3章からトライしても良いと思います!!
- プロローグ 職場でよく見る「残念な現場」の実態
- 1章 キークエスチョンにたどりつかなければ、すべてはムダ
- 場当たり的アプローチの恐怖
- なぜコンサルタントは、最初に論点について学ぶのか
- キークエスチョンとは何か
- まずは構造化してみよう
- あらゆる場面で構造化思考は活用できる
- 2章 構造化思考のアプローチ 3つのステップ
- 構造化思考の“トライアングル”
- ステップ1:論点を分解する
- ステップ2:解き方を整理する
- ステップ3:解を整える
- 3章 やってみよう! 構造化思考 実践編
- 実践問題1:ある商材を海外展開する
- 実践問題2:類似商材を売るべきか?
- 実践問題3:その商品は「収益の柱」になるか?
- 実践問題4:レストランの夜間営業を継続すべきか?
- 実践問題5:プロモーション戦略を考える
- エピローグ 構造化は、プロにしかできない技ではない
『構造化思考トレーニング コンサルタントが必ず身につける定番スキル』要約詳細
1章と2章の内容を簡単に要約していきます。
3章の実践編については、ケーススタディになるのでケースのテーマだけを記載しようと思います。
実際にケーススタディを解いて、構造化思考を鍛えたい方はぜひ本書を手に取って挑戦してみてください!
1章 キークエスチョンにたどりつかなければ、すべてはムダ
構造化思考のアプローチや鍛え方を知る前に、なぜ構造化思考が重要なのか。
この点は、1章を読んでしっかりと押さえておきましょう。
本章で語られていることを要約すると以下のような説明になるでしょう。
構造化思考とは何か
- 仕事のゴール(誰が、どのような状態になっているのか)を定め、ゴールに対するキークエスチョン(解くべき問い)を設定する思考法
- キークエスチョンを検証するための論点をピラミッド状に分解して、論点を検証するためのアウトプットとタスクを設計する思考法
あえて2つの文章で書き表してみました。
1つ目は仕事の方向性を決めるうえで、大事な前提となる部分です。
「何を解きたいのか」や「何を明らかにしたいのか」を踏まえ、それらが達成された後にはどのような状態を目指すのか。
これがゴールです。
ゴールが明確になっていると、ほぼ裏返しでキークエスチョンが設定されます。
例えば「○○商材をA国に展開すべきか判断できている状態」をゴールと設定すれば、「○○商材をA国に展開すべきか判断するためには?」というキークエスチョンが設定できます。
このキークエスチョンを設定できたら、2つ目の文章で記載した内容を実践します。
キークエスチョンに答えるための論点をピラミッド状に分解していき、各論点に対する仮説と仮説を検証した結果としてのアウトプットイメージを定めます。
あとはアウトプットイメージを作り出すために、タスクの実施アプローチを設計するのです。
この一連の活動がコンサルタントが行う仕事のアプローチであり、構造化思考になります。
2章 構造化思考のアプローチ 3つのステップ
1章の内容は、仕事のアプローチに関する広い考え方を説明する章でした。
この一連のアプローチにおいて、特に「構造化思考」という表現が似合うのは「論点をピラミッド状に分解」する部分でしょう。
2章では、まさにこの点を実践するステップが示されています。
キークエスチョンを検証可能なレベルの論点を目指して、MECEに分解する
このとき「実施事項(○○分析、□□調査など)」として表現してはならない
仮説を立て、アウトプットとタスクを具体化する
このとき論理構造に抜け漏れがないかを検証する
仮説の検証結果を説明するために適した表やグラフを検討する
このとき資料全体のストーリー構成も同時に考えるが、「聞き手の頭の中」と「自分の頭の中」を揃えることを意識しながら、既出情報を起点にして新たな情報を伝えることで「情報の繋がり」を担保する
これが実践ステップの概要になります。
構造化思考においてはステップ1の「論点を分解する」ことが、肝になります。
本書では、論点を分解するときの手法が5つ紹介されており、これらの手法が「構造化思考を鍛えたい」と思うあなたにとって即効性のある学びとなるはずです!
論点を分解するときの代表手法
- 文章区切り:キークエスチョンを文章の区切りで分解して論点に設定
- フレームワーク:3Cや4Pなどのフレームワークを活用して論点に分解
- 前提条件:解を出すための条件で論点を設定
- 通念的概念:通念的にMECE考えられる概念(過去・現在・未来など)で論点を設定
- 類似論点の統合・整理(ボトムアップ方式):個別の論点をグルーピングして論点構造を整理
3章 やってみよう! 構造化思考 実践編
3章は実践編として、構造化思考を試す5つの問題が用意されています。
- 実践問題1:ある商材を海外展開する
- 実践問題2:類似商材を売るべきか?
- 実践問題3:その商品は「収益の柱」になるか?
- 実践問題4:レストランの夜間営業を継続すべきか?
- 実践問題5:プロモーション戦略を考える
5つの問題は全て繋がっています。
中堅商社の課長を主人公として、商材の海外展開するか否かの問いに答えを出して、出世をして部長となった後に経営企画の人間として、他事業のことも考える・・・といった話になっています。
事業について考えるレベルから、マーケティング施策としてどのような手を打つかを考えるレベルまで、視座や視点の異なる実践問題を通じて、構造化思考を鍛えることができるでしょう。
『構造化思考トレーニング』でコンサル基礎強化
「構造化」という言葉は業界では良く使われるのですが、明確な定義を説明できるコンサルタントは意外に少ないのです。
この記事を書いていながら、「構造化とは?」と聞かれると正直困っていました・・・。
「構造化できていない = 考えられていない」というのが業界として暗黙の了解になっている気がします。
レビューのタイミングで真っ先に見られるのが、「そもそも構造化されているか」だった経験はありませんか?
新人コンサルタントがレビューしてもらいたい内容ではなく、構造化されているか否かを詰められる。
よくあります。
コンサルタントという仕事が多くの事実や情報を体系的に整理して、示唆を出すことを生業の中心としているからです。
デスクトップリサーチやアンケート、インタビュー・ヒアリングなどを通して得られた事実や情報はコンサルティングを行う上でとても重要な材料となります。
しかし、その材料は非常に多く、様々な観点でバラバラな情報として集まってきます。
それらの情報をコンサルタント(特にアナリストやコンサルタントというジュニアな職位)は綺麗に整理して、情報を情報を俯瞰的に理解できるようにせねばなりません。
混沌とした情報の海に身を投げ出されては、どんなに優秀なコンサルタントであっても荒波を乗りこなすことはできずに溺れ死んでしまいます。
構造化することで忙しいクライアントにも情報を視覚的にも伝えることができるので、情報を短時間で理解してもらうこともできます。
だから、構造化思考は大事なのです。
あなたがコンサルタントとして、ビジネスパーソンとして、ムダな仕事やグダグダ会議を減らして効率的に働くために、『構造化思考トレーニング コンサルタントが必ず身につける定番スキル』で構造化思考を鍛えてみませんか?
以上、特に新人コンサル・若手コンサルにオススメの本『構造化思考トレーニング コンサルタントが必ず身につける定番スキル』のご紹介でした!
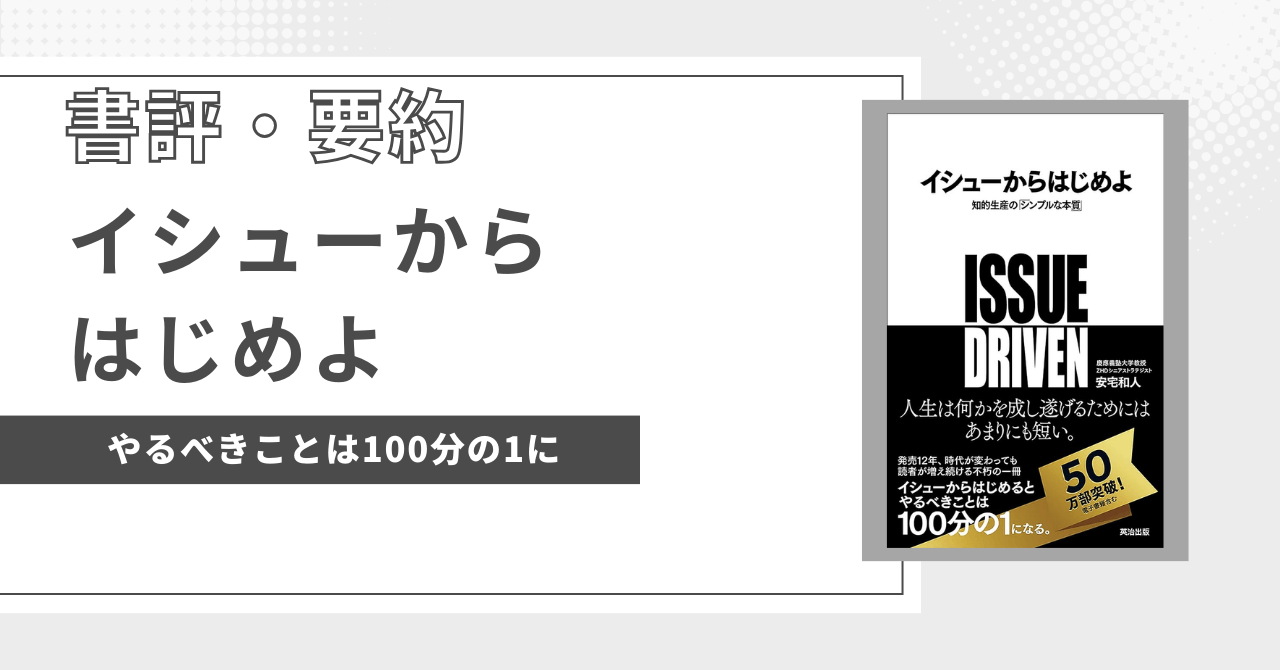
スキマ時間・休日の自己投資にオーディオブックサービスを活用
「休日を充実させる自己投資がしたい!」
「仕事で忙しいけど、スキマ時間に勉強をしたい!」
「たくさんビジネス書を読んで、活躍できるビジネスパーソンになりたい!」
あなたも同じ考えではありませんか?
そんな人にオススメできるのが、会員数250万人を突破したオーディオブック配信サービス【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】です。
【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】のおすすめポイント
- 年割プラン料金なら「月額833円」で15,000点以上のコンテンツを聴ける
- 14日間の「聴き放題お試し」が提供されている
- 厳選されたプロがナレーターとして本を朗読する
\ 14日間の「聴き放題お試し」あり /
本をたくさん買う人には、オーディオブックの方が安くなることもあります。
audiobook.jpの年割プラン料金なら「月額833円」で15,000点以上のコンテンツを聴くことができます。
14日間の「聴き放題お試し」が提供されているので、いちど気になる作品を聴いて継続利用するかお考えてみてください。
ちなみに、Amazonの子会社であるAudible Inc.が提供するオーディオブック・サービス【Audible】の料金は月額1,500円です。
外国語のコンテンツも多いので、英語学習をしたい方はAudibleをオススメしますが、多くの方には月額880円で「聴き放題月額プラン」が使えるaudiobook.jpをオススメします。
audiobook.jpには定額の「聴き放題プラン」以外にも「チケットプラン」があります。
「チケットプラン」は通常価格 ¥1,500で1枚のチケットを購入します。
購入したチケットと聴きたい作品を交換することができます。
チケット交換した作品は永久に何度も聴くことができるので、何度も聴き返したいオーディオブックコンテンツはチケット交換がオススメです。
ビジネス書は1冊2,000円以上することもあるので、「聴き放題プラン」「チケットプラン」のどちらでもコスパが良いですよね!
最近ではAIが音声を読み上げるオーディオブックサービスもありますが、厳選されたプロがナレーターとして本を朗読するaudiobook.jpが聴き心地は良いですね。
ぜひ、スキマ時間や休日の自己投資にオーディオブック配信サービス【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】を活用してみてください!
\ 14日間の「聴き放題お試し」あり /
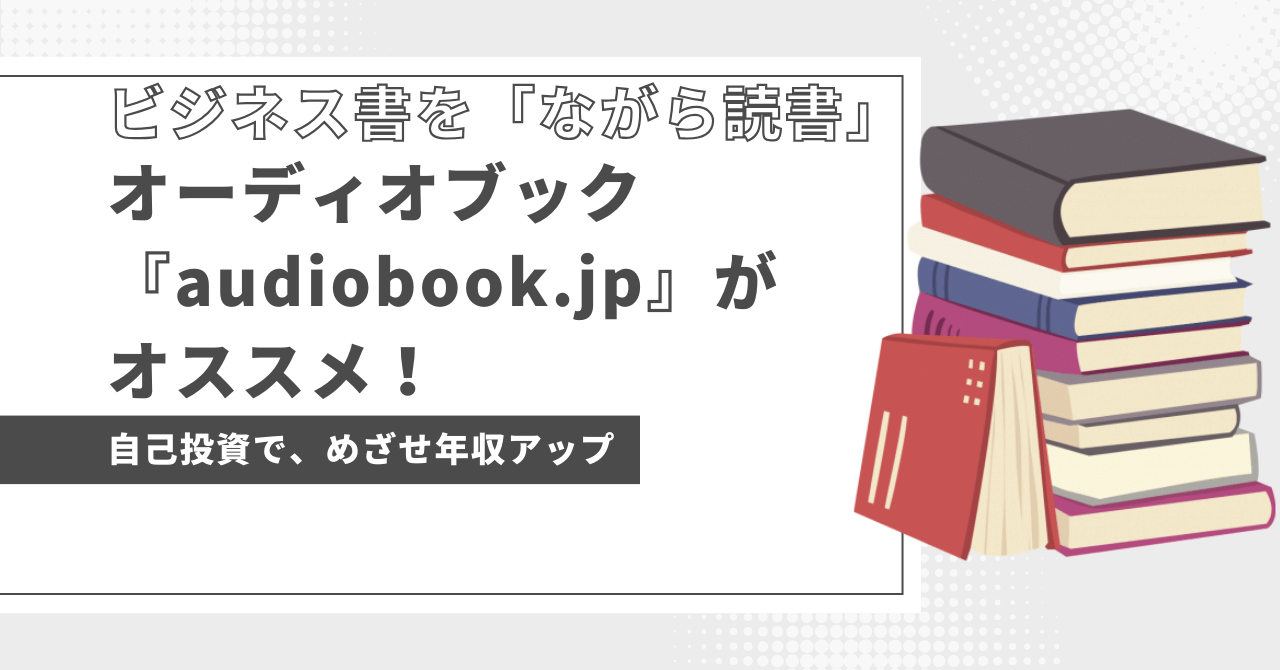
コンサルティング業界転職体験談まとめ
筆者「きつね」がコンサル転職を2回した体験談をまとめています!
30代で資産3,000万円を築いて、サイドFIREを実現したい。
そのためにコンサルティング業界で働いて年収を上げるため頑張っています。
転職をすることで年収を上げる、もしくは労働環境を改善させながら年収を維持することも可能です。
コンサル転職の成功は人それぞれですが、あなたのコンサル転職を成功させるため、ぜひ筆者「きつね」の体験談を参考にしてもらえたら嬉しいです!
コンサル転職体験談のオススメ記事
- 【オススメ】コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
- 【コンサル転職体験談】20代で年収1,000万!コンサルタントが年収を上げてきた思考法を伝授!
- 客先常駐=高級派遣?アクセンチュアやベイカレントなどの総合系コンサルが揶揄される理由
- 【コンサル転職体験談】転職候補はアクセンチュアソング、デロイト、PwC、インキュデータ
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職スケジュール公開!実際の転職ステップで要点を解説!
- 【3つの理由】「20代でコンサルタント就職・転職」が市場価値を高め、生涯年収を上げる!
- コンサル流「20代で市場価値を上げる休日の過ごし方」を紹介!暇な社会人こそ自己研鑽!
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職ならホワイト500の日系総合コンサルがオススメ!
- 【コンサル転職体験談】30代マネージャーが総合系コンサルファームを辞める理由は?
- 【コンサル転職体験談】面接でした逆質問を紹介!志望度を間接的に伝える重要要素
- 【コンサル転職体験談】コンサル就職・転職前に必読!ケース面接の対策本3選!
- 【コンサル転職体験談】職務経歴書|書き方のコツ!書類選考は全社通過!
- 【高年収】コンサルタントの種類?コンサルタントの職位・相場年収って?
- 【コンサル転職】転職活動おすすめの「企業の口コミサイト」を紹介!
- 【未経験30代のコンサル転職】コンサル転職に失敗する人の特徴3選
コンサル転職を成功させるため転職エージェントを複数利用
筆者「きつね」が内定までサポートしてもらった転職エージェントはアクシスコンサルティングでした。
>>コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
もちろんオススメですが、コンサルティング業界・ポストコンサル転職を目指すなら、転職エージェントは複数登録しておいた方が良いでしょう。
1つの転職エージェントから得られる求人情報は偏ってしまいますし、キャリア相談におけるセカンドオピニオンを得られることが複数の転職エージェントを活用するメリットです。
以下が筆者「きつね」も利用した転職エージェントです!
最近はコーチングにお金を払って転職をサポートするエージェントもいますよね。
ご紹介しているサービスはあくまで転職エージェントなので、無料で利用可能です!
転職活動の初期は複数の転職エージェントから求人情報をもらいつつ、担当さんとの相性も見極めましょう!
アクシスコンサルティング
アクシスコンサルティングは、コンサルティング業界の転職を目指すなら登録必須です。
コンサルティングファームの採用担当者と密に連携をしており、あなたの希望にあった非公開求人を紹介してくれます。
長年コンサル業界の転職を支援しているので、ケース面接対策もバッチリです。
\ コンサルティング業界に特化した転職面接サポート!! /
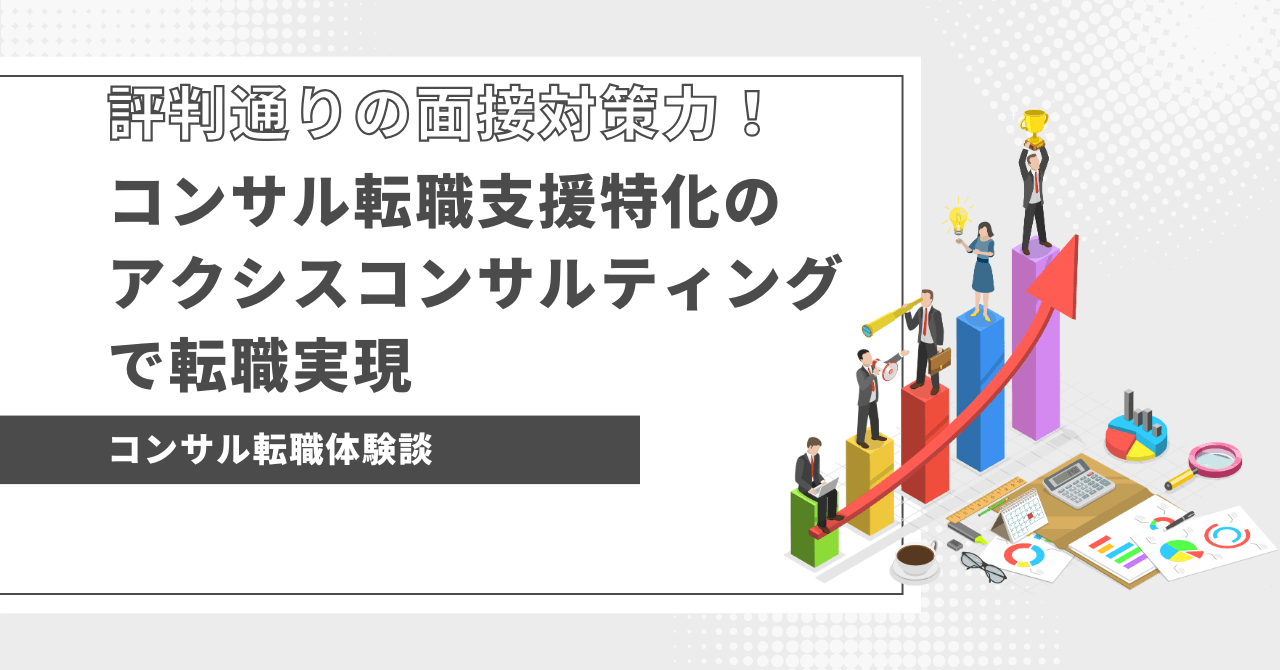
MyVision
コンサル業界出身者・人材会社出身者が立ち上げた新進気鋭のコンサル転職特化の転職支援サービスです。
200社・1,000ポジション以上の広範な紹介先ネットワークを有しているので、希望につながる転職先が見つかるはずです。
受賞歴も凄まじいですね!
コンサル転職を検討しているなら登録をオススメします。

\ コンサル転職ならMyVision /
コトラ
ハイクラス転職に強く、特に金融業界の転職に強いのが「コトラ」です。
コンサル業界の転職も支援をしてくれます。
CFOや金融業界を専門としたコンサルを目指すなら登録必須だと思います。
コンサルタントとして金融業界の支援経験がある方も登録をしておくと良いでしょう。
\ ハイクラス転職に強い! /
マスメディアン
広告業界やマーケティング職の転職を考えているなら「マスメディアン」の登録がオススメです。
「宣伝会議」という広告やマーケティングに関する出版社が運営する転職エージェントで、出版社としてのコネクションを活かした転職情報が魅力的です。
\ 広告・Web・マスコミの求人情報・転職なら! /
DODA
大手転職エージェントdodaは約12万件ある求人情報から、あなた専任のキャリアアドバイザーが希望に合致した求人情報をリストアップしてくれます。
ワークライフバランスを見直したり、業種・職種を広く検討したい場合はdodaがオススメです。
\ 安心のサポート力! /
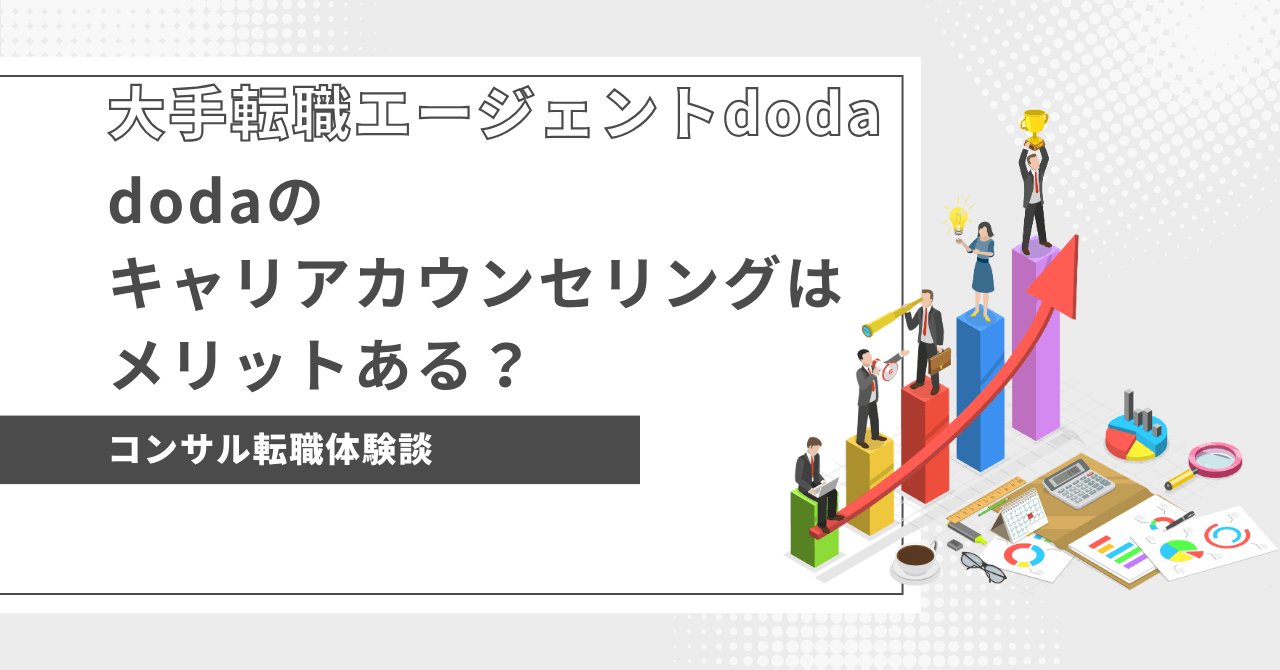
リクルートエージェント
\ 10万件以上の非公開求人! /


