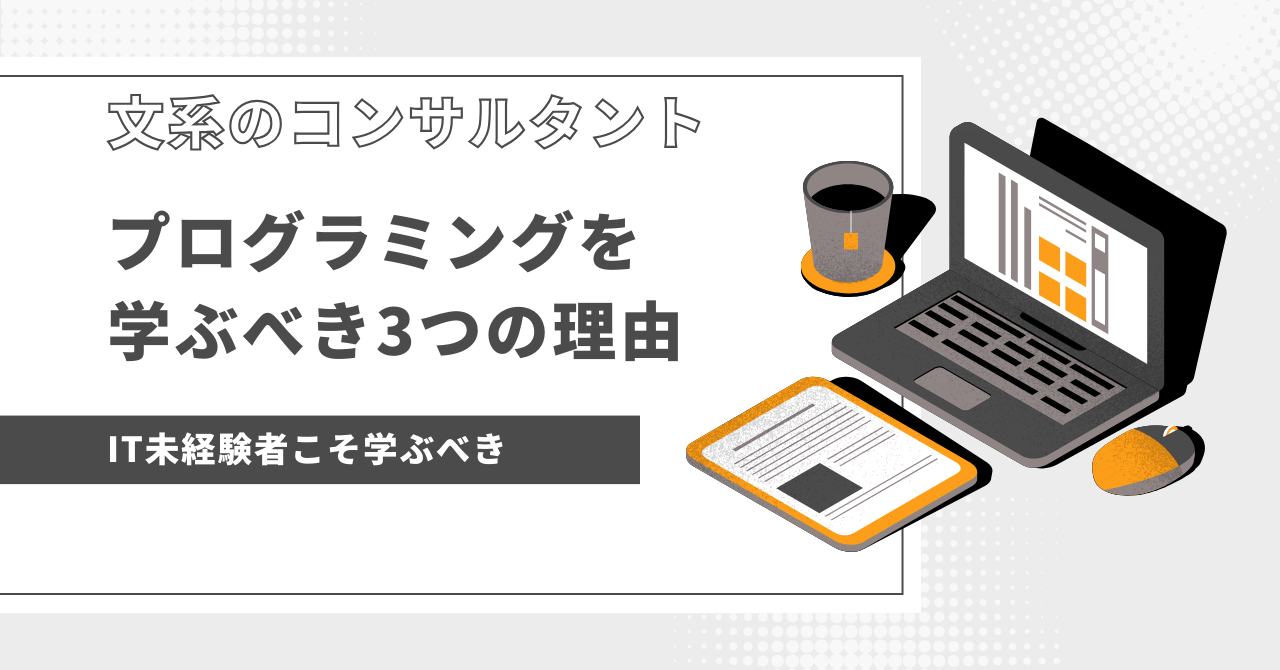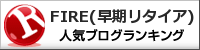約10年間、総合系コンサルティングファームで働いてきた経験からお話します。
ITコンサルやDXコンサルと呼ばれるコンサルタントとしてキャリアを磨くうえで、プログラミングができなくても問題はありません。
しかし、「プログラミングができる・プログラミング知識がある」とプロジェクト推進上で有利に働くことは多くあります。
筆者「きつね」は大学生時代は心理学を専攻する文系でした。
ITは未経験でコンサルタントとして働くことになった人間です。
新人コンサル時代はITに抵抗感と苦手意識がすごく、苦手意識を克服したい気持ちはありましたが、なかなか難しかったです。
そんな筆者「きつね」がIT領域を中心としたコンサルタントとして働くなかで、プログラミングを学び、磨かれたと感じる能力をお伝えしたいと思います。
文系プログラミング未経験でもITコンサル・DXコンサルとして活躍できる
ITコンサル・DXコンサルは言葉が違いますが、業務実態として近しい領域を支援することもあります。
言葉の定義は諸説ありますが、「ITコンサルが支援する上流工程≒DXコンサル」と捉えても問題ないと思います。
具体的にITコンサル・DXコンサルが行っていることは、クライアント企業の持続的な成長や足元の課題解決を実現するため「課題分析・解決施策の検討・実行」になります。
「解決すべき課題は何か」を考え、「テクノロジーの力を使って、どのように課題を解決するか」がコンサルの支援領域です。
課題設定力やリサーチ力、プレゼン力などは必要ですが、プログラミングスキルがなくとも最新テクノロジーやソリューションの特徴を把握して、課題解決に適用・活用できれば問題ありません。
テクノロジーを活用して新しい事業を考えたり、業務を改善することもありますが、プログラミングを実際にすることは少ないです。
総合系コンサルティングファームに新卒で入社すると、1年目のときにプログラミングをすることもあるようです。
また、ITコンサルとしてのプロジェクトで、開発プロジェクトの管理や現場へのシステム導入という
新人コンサル時代にプログラミングをするケースはITコンサルとして、将来的に役立つからです。
では、なぜプログラミングをすることがITコンサル・DXコンサルとして役立つのかを考えてみましょう。
ITとビジネスが切り離せない時代

デジタル戦略・デジタルトランスフォーメーション(DX)やAIなどの必要性は叫ばれるなかで、コンサルタントとして働く人間がITと向き合う機会がとても多い時代となりました。
財務会計に特化したり、人事評価制度策定に特化するなど、ITと比較的触れずとも成り立つコンサルタントとしての専門領域を定めて、そのスキル・知識・経験を尖らせていく場合は別かもしれません。
ただ、それはそれでリスクもあります。
財務会計領域については、会計士がAIに代替されるという話はあなたも耳にされたことがあるでしょう。
クライアントと接して改善策を提案・実行していく領域はAI単体では難しいでしょうが、財務分析についてAIが代替してくれることは想像に難くありません。
人事評価制度設計についても、ITを絡めずにゼロから評価制度を構築することよりも、そのようなパッケージ製品を組織に導入するための製品選定やカスタマイズ要件の有無をご支援する機会の方が多いと思われます。
クライアント企業とコンサルティングファームに情報格差があった時代とは違い、MBAホルダーやポスト・コンサルが事業会社に普通に在籍してノウハウや経験を事業展開に活かしています。
それに、ベンチャー界隈のスピード感のある業界動向については、コンサルタントといえども、大企業相手の仕事をしていれば正直、疎くなりがちです。
コンサルタントよりベンチャーキャピタルや起業家の方が精通していることでしょう。
知識だけでコンサルタントが戦える時代は過ぎ去りつつあります。
プログラミングで得られる「実行力・推進力」と「先見力・修正力」

そのような中でコンサルタントに求められているのは、 現場での「実行力・推進力」と、走りながらも目まぐるしく変化する状況に戦略や戦術を適応させていく「先見力・修正力」といった点に価値が移動していると考えています。
コンサルタントがプログラミングを学ぶことで、これらの力が大きく磨かれていくと考えています。
具体的に、私が得たプログラミングによる効用は以下の3点です。
- 論理思考強化(プログラミングによるロジカルシンキング習得)⇒「実行力・推進力」&「先見力・修正力」
- 提案力強化(IT自体への理解促進)⇒「先見力・修正力」
- 施策実現力強化(SE/プログラマとのコミュニケーション土台)⇒「実行力・推進力」
これらの力により、これからのコンサルタントに重要な「提案→実行→実行しながらの修正」のベースとなる力が磨かれました。
では、それぞれの効用について説明していきます。
論理思考強化(プログラミングによるロジカルシンキング習得)
まずは、ビジネスパーソンとしての基礎スキルと謳われて久しい論理思考力の強化です。
プログラミングの世界では以下の言葉が常識となっています。
プログラムは思った通りには動かない。書いたとおりに動くのだ。
Any code doesn’t run as you thought, run as it wrote.
この言葉の通り、
- システムで処理するデータはどのような形式なのか
- データをどのように受け取るのか
- どのように処理(データ加工)するのか
- どのように出力するのか
これらの全てが整合性を保てるように、システムの処理を考えて、「プログラムとして完成させるためには、どのようにプログラミングを行えば良いのか」を考える必要があります。
更に言うと、現代のITシステムは複雑化しておりシステム間の連携が当然となっています。
そこで考える必要があるのはシステム間でのコミュニケーションがちゃんとできるのか、ということも加わってきます。
相手は英語で話しかけられるのを待っているのに、日本語で話しかけても通じないように、システム間でのコミュニケーションが成り立つのかを確認する必要があるのです。
このようにシステムを開発するのは、とても神経の使う難しい仕事です。
その分「やりがい」があるのは確かですが、システム開発の実態を知らない人が「売上データをいい感じに分析して、適正発注数と在庫数を算定して」と思っていても、実現するには途方もない「論理の積み重ね」があるのです。
「論理の積み重ね」で実現されるシステム。
システムを開発するプログラミング。
プログラミングを通じて行うことで、論理思考力が否応もなく鍛えられるのです。
提案力強化(IT自体への理解促進)
プログラミングによってIT自体の理解が深まることで、コンサルタントとしてクライアントに提案できる幅が広がります。
戦略立案から業務設計まで、現代はITとビジネスが強く結びついています。
あなたも公私問わず日常的にITと接しているでしょう。
しかし、ITという文明の利器を使う人間と作る人間では、ITに対する大きな知識と情報の格差があります。
先の例で「適正発注数を算出して」という無茶ぶりを記載しましたが、この無茶ぶりは普通に起こりえます。
(そもそも「適正発注の定義って何?という点から会話しましょうよ」と思うのですが・・・。)
ここで「何となく簡単そうだし、できそうだな・・・。」と思って、易々と「できます!」 と言ってしまうと自分の首を絞めることにしかなりません。
現在のシステム構成はどうなっているのかという点やシステムを実現するプログラムがどのような作りになっているのかを正確に把握していないと、実現可否は判断できません。
現システムではできないとしたら、実現するためのシステム改修内容を考らることを求められるのですが、ITを理解していないと想像もできません。
システムの改修と聞くと壮大なイメージが浮かびますが、極論すればどんなシステムも小さなプログラムの積み重ねです。
プログラムはどのようにして動くのか、プログラムを動かすために必要な道具はなにか、といったことをプログラミング学習を通して理解することで、ITと関連した提案を行う力の基礎を鍛えることができます。
施策実現力強化(SE/プログラマとのコミュニケーション土台)
最後の3点目は、施策実現力としてSEやプログラマの方々とコミュニケーションをする土台ができあがります。
「ビジネスとITが密接につながっています⇒ITはプログラムの積み重ねです⇒プログラムは SEやプログラマという方々が作ります」ということで、システムを作ってくださる方と会話ができることで、オーダーを伝えやすくなったり、 IT関連課題の対応について議論できたりします。
また、有事の際には自社の役員クラスにITのことをわかりやすく報告する必要もあるでしょう。
このときに開発ベンダーのSEやプログラマが言っていることを理解して咀嚼・翻訳するカも非常に重要です。
システム障害などが発生した際、開発ベンダーの人間はあくまでIT目線での事象報告がメインです。
ですが、発注元の会社ではビジネス・事業という観点での報告が求められることがあるでしょう。
社外の開発ベンダーの報告と社内の役員への報告には、さながら異文化を繋ぐ力が必要です。
「IT文化の理解をするための土台・ビジネス文化への翻訳をするための土台」としての力が、プログラミングを学ぶことで培われます。
文系プログラミング未経験のコンサルに向け|Webアプリ開発のススメ
文系プログラミング未経験でITコンサル・DXコンサルとして働くことになった方に向けて、プログラムができなくても問題ないことをお伝えしました。
一方で、ITコンサル・DXコンサルとして活躍するうえで、「プログラミングができない」というより「プログラミングをしたことがある」というレベルの経験があるに越したことはありません。
システムエンジニア・プログラマーの方と一緒に仕事をして信頼を得るためにも、一度くらいはプログラミングに挑戦することをオススメします。
ITコンサル・DXコンサルとしてプロジェクトをマネジメントする立場となったときも、役立ちます。
プログラミング経験があれば、「これくらいの機能を開発するのに、もっと短い期間で開発できない?」とベンダーと交渉することもできますからね。
簡単なWebアプリケーションの開発を勉強してみると、現代で使われるIT技術要素の大枠に触れることができるので非常に有益です。
筆者「きつね」自身も新人時代にEclipseという開発用ツールを使い、JavaやJavaScriptというプログラミング言語でWebアプリケーションを開発する勉強をしました。
しかし、Javaというプログラミング言語を学びながら「オブジェクト指向」というプログラムを作るうえでの考え方を学ぶことができました。
Webアプリケーションを開発するなかで、URLやHTTPSという通信に関する知識、Oracleなどのデータベースについて学んだり、と自然に基礎的なIT知識を身に付けることもできました。
いきなり難しい専門書を読むと一気にアレルギー症状を発症させてしまうでしょう。
「少しプログラミングを学んでみようかな!でも、何を読めば・・・。」
そう思っているあなたに、私が実際にお世話になった「スッキリわかる」シリーズをオススメしたいと思います!
RPGを題材にしたような本の構成となっており、少しずつJavaというプログラミング言語やITについてを学ぶことができます。
プログラミング自体が未経験で、基礎からプログラミングを学びたい方は、以下の2冊をオススメします。
Webアプリケーションについて学習をしたいという方は以下の本を通じて、Webの仕組みを学べば、現場で耐えうる知識と経験を身に付けることができます。
この記事を読んでくださったあなたがITやプログラミングについて学んでくださり、今後の日本ビジネスを支えるデジタル人材として共に頑張っていければと思います!
文系コンサルがプログラミングを学ぶなら学習サービスの活用も
文系でプログラミングが未経験だと、ちょっとした開発準備もできないで苦しむこともあると思います。
プログラミングに特化したサービスではありませんが、動画学習サービスSchoo(スクー)などを活用して、プログラミングを学ぶ手段もオススメです。
月額980円の課金で録画授業を見放題です。
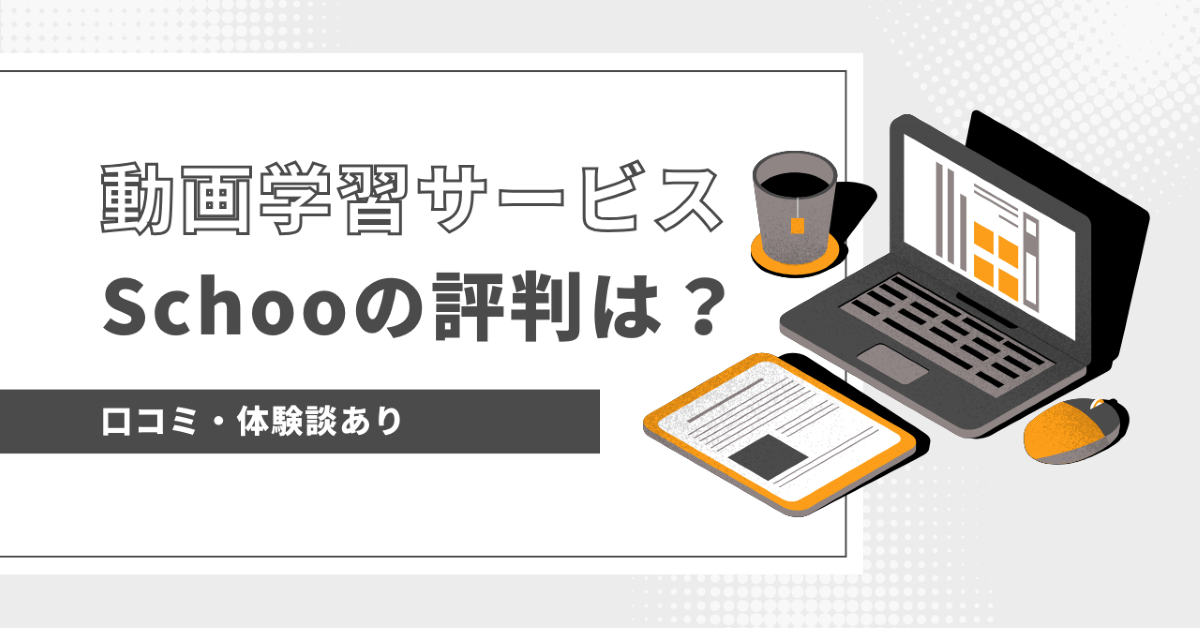
また、ストアカというスキルシェアサービスを活用すれば、数千円でプログラミングを学ぶことができます。
プログラミングができないからといって、コンサルとして活躍できないわけではありません。
だからこそ、他のコンサルタントとの差別化要素として、ぜひプログラミングを学んでみてください!
コンサル転職・自己研鑽に有効な資格は?
筆者「きつね」が実際に合格/勉強して、コンサルティング業務や自己研鑽に役立ったと思える資格を紹介します。
ぜひ、あなたのコンサル転職・自己研鑽の参考としてください!
コンサル転職前のオススメ資格/勉強記事
>>20代コンサルにおすすめ!年収を上げるIT資格【応用情報技術者試験】
>>【基本情報技術者試験】20代のコンサル転職で年収を上げるIT資格
>>【対策本あり】文系こそ取得すべき国家資格『ITパスポート』取得メリットを紹介
>>文系のIT未経験コンサルタントがプログラミングを学ぶべき3つの理由
>>【本も紹介】図解思考の技術・モデリング技術で概念を具体化【資格のUMTPもオススメ】
>>【合格体験談】マーケティング検定3級の体感難易度は簡単!勉強時間に参考書も紹介
>>【コンサル転職体験談】資格挑戦:マーケティング検定2級に挑戦|いきなり合格は無理?難易度は3級より確実に高い!
>>TOEIC400点台から800点台!コンサル実践の英語勉強法
>>【PMBOK】5つのプロセスと10の知識エリアはコンサル必修科目
>>新人コンサルにおすすめの資格「ビジネス会計検定3級」:簿記との違い・難易度・合格率をまとめた!
>>【オススメ】動画学習サービスSchoo(スクー)は評判がいい!
>>【無料あり】マーケティングが学べるオススメ動画学習サービス5選
コンサル転職に有利な資格合格に向けて
コンサル転職・転職後の自己研鑽として、資格取得を目指して勉強することはオススメです。
コンサルティング業界で働いていると、常に試験勉強をするように新しい知識をキャッチアップしないといけないので「勉強慣れ」をしておくとよいでしょう。
【STUDYing】中小企業診断士・応用情報技術者などをカバー
上記の資格をフルサポートしているわけではありませんが、スキマ時間で効率的に中小企業診断士などの資格合格を目指すなら、STUDYingも使うのもオススメです。
STUDYing中小企業診断士講座の2022年2次試験の最終合格実績が「業界No.1」
- 【合格実績 No.1!】
- ※12022年2次試験合格者数:167名
- 【合格者続々輩出中!】
- 2023年1次試験合格者数:510名
※1:同種の資格講座を提供している業者について、KIYOラーニング株式会社が2023年11月6日時点でHP上に記載されている合格者実績を調査した範囲での比較となります。
【診断士ゼミナール】格安で中小企業診断士を目指す!
高難易度ですが、コンサル転職に有利な資格として有名な「中小企業診断士」を目指すなら、低価格&高品質な中小企業診断士試験合格講座である【診断士ゼミナール】も検討してみてください!
>>42,000円からの中小企業企業診断士講座【診断士ゼミナール】【アガルート】MBA取得・中小企業診断士合格を目指す!
「中小企業診断士」の合格や「MBA取得」を検討している方は【アガルート】で対策をするのもオススメです!
講義はオンライン・フルカラーのテキストが届くので、印刷の手間なく勉強を始められますよ。