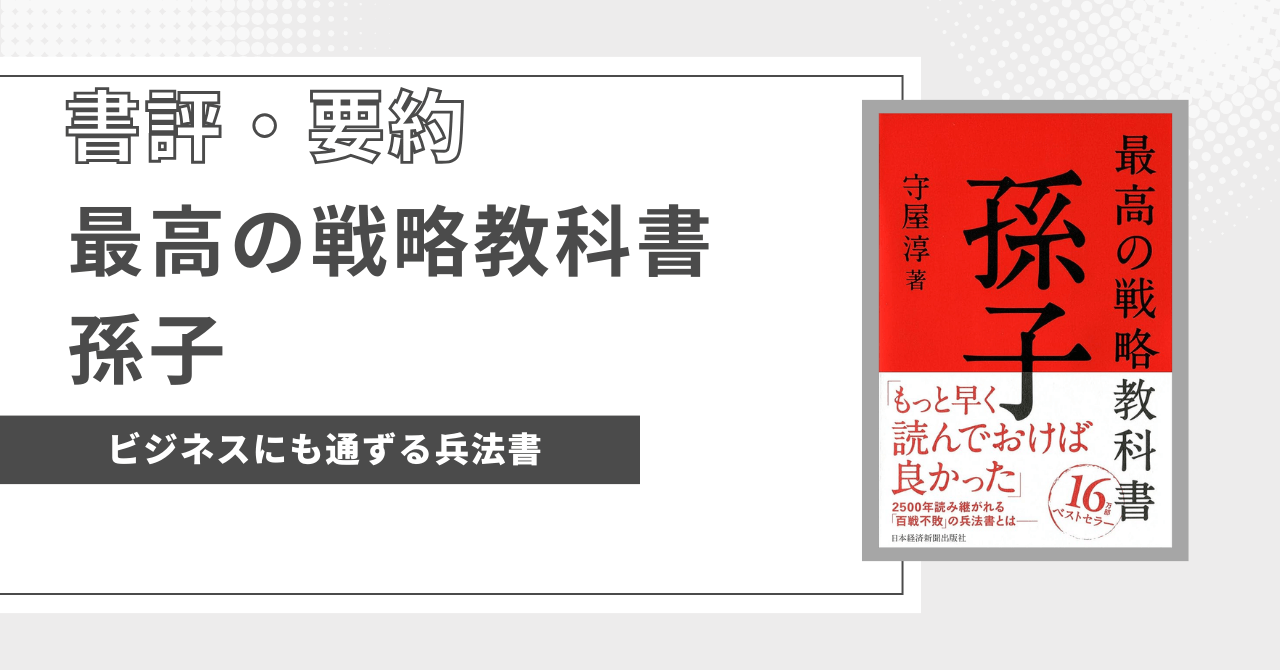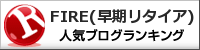中国の戦略家「孫子」をご存知の方も多いでしょう。
今回は「孫子の兵法」で著されている戦略の極意を著者が解釈した解説本『最高の戦略教科書 孫子』のご紹介です。
2,000年以上も読み継がれている兵法書に詰め込まれた英知を、現代のビジネスに活かすための本書。
手に取ったのは、こんなことを思っていたからです。
 きつね
きつね「孫子の兵法」について勉強したいなー
でも漢語が並びまくってる本は読みたくないしなー
孫子の兵法について網羅的に触れているわけではないと思うものの、筆者の解釈も織り交ぜて解説されており、重要な要素には触れることができるのではないかと思います。
経営コンサルタント・経営企画、部長職など、会社や事業の戦略や方向性を定める立場にいらっしゃる方は読んでほしいですね。
他にも古典好きや歴史好きの方、更にはキングダムという漫画が好きな方にも読んでほしいです!
キングダムは春秋戦国時代に秦の始皇帝が中国統一をする時代を取り扱っているので時代は異なりますが、戦略の考え方や「将」に求められる要素は共通するものがありますよ。
『最高の戦略教科書 孫子』オススメ読者
- 『孫子の兵法』の入門書を探している方
- 経営コンサルタント・経営企画や部長職の方
- 歴史好き・「キングダム」好きのビジネスパーソン
ここで質問です。
「出世をして年収を上げたい・キャリアアップをしたい!」
「副業/複業に挑戦したい!」
「投資をして不労所得を得たい!」
筆者「きつね」と同じく、あなたもそう考えたことはありませんか?
書籍から知識を得ることであなたの目的達成に近づきますが、本を購入すると費用も場所も負担になりますよね・・・。
そんなお悩みを持つあなたにオススメするのが『Amazon Kindle Unlimited』です。
200万冊以上の本が読み放題になるAmazon(アマゾン)の電子書籍読み放題サービスで、「あなたの年収を上げる・サイドFIRE実現を助ける・不労所得をゲットする」本が見つかります!
電子書籍よりも紙の本が好きという方もいるかもしれませんが、初めてご利用の方は30日間の無料体験が可能です。
使いにくければ30日経過する前に解約をしましょう。
無料期間終了後は月額980円で使えます。
「1か月だと読み切れないし、1年だと長すぎるかも・・・。」
もちろん、いつでも解約できるので3か月くらい集中して本を読み漁って解約するという使い方でも良いかもしれません。
>>Amazon Kindle Unlimitedを無料で試してみる\ 初回利用は30日間無料!200万冊以上の本が読み放題 /
『最高の戦略教科書 孫子』概要
著者のご紹介と目次を一覧化しました。
どんなことが書いてあるのか概観しましょう。
著者 守屋 淳(モリヤ アツシ)
著者は守屋 淳(モリヤ アツシ) さん。
著者情報
- 守屋淳(モリヤアツシ)
- 作家、中国古典研究家
- 1965年、東京都生まれ
- 早稲田大学第一文学部卒
- 大手書店勤務を経て、現在は中国古典、主に『孫子』『論語』『老子』『荘子』『三国志』などの知恵を現代にどのように活かすかをテーマとした執筆や、企業での研修・講演を行う。
中国古典を現代風に解釈されて執筆・講演されている方です。
お父様の守屋 洋(モリヤ ヒロシ)さんも中国文学者です。
中国古典のサラブレッドですね。
目次・章構成
孫子の兵法を現代風に解釈しなおして解説している本書。
昔ながらの古典的な解釈や歴史的な背景を重視する方には向かないかもしれません。
逆に、20代や30代で「気軽に孫子の兵法を学んでみたい。触れてみたい。」という方にはピッタリな1冊です。
前半は孫子が活躍した時代のこと、兵法を著してどのように活躍をしていたのか(=「孫子とは?」)を知ることができます。
孫子の兵法をついての前提知識を得たうえで、ビジネスパーソンが現代のビジネスシーンで活かす方法を考察しています。
『 最高の戦略教科書 孫子 』目次
- I部 『孫子』はそもそも何を問題とし、何を解決しようとしたのか
- 第1章 百戦百勝は善の善なる者にあらず
- 第2章 敵と味方の比べ方
- 第3章 戦いにおける二つの原則――不敗と短期決戦
- 第4章 兵は詭道なり
- 第5章 情報格差のある状況での戦い方――各個撃破と急所
- 第6章 情報格差が作れないときの戦い方 1主導権と裏の読みあい
- 第7章 情報格差が作れないときの戦い方 2無形と勢い
- 第8章 自国内での戦い方――地形とゲリラ戦
- 第9章 勝は度から導き出される
- 第10章 勝てる組織と将軍の条件
- 第11章 情報を制する者は戦いを制す
- II部 『孫子』の教えをいかに活用するか
- 第12章 そもそも人生やビジネスに、戦いなんて必要ないのではないか
- 第13章 そもそも戦略と戦術とは、どう違うのか
- 第14章 試行錯誤ばかりしていたら心が折れそうなんですけど
- 第15章 ジリ貧状態では、不敗なんて守っていられないのではないか
- 第16章 相手の急所をつけば、すぐに決着などついてしまうのではないか
- 第17章 詭道やだましあいなんて、品性下げそうでいやなんですけど
- 第18章 「各個撃破」なら勝てるのに、なぜ「選択と集中」では失敗するのか
- 第19章 追いつめる以外の「勢い」の出し方はないのか
- 第20章 弱者はどのように振る舞えばよいのか
書籍詳細
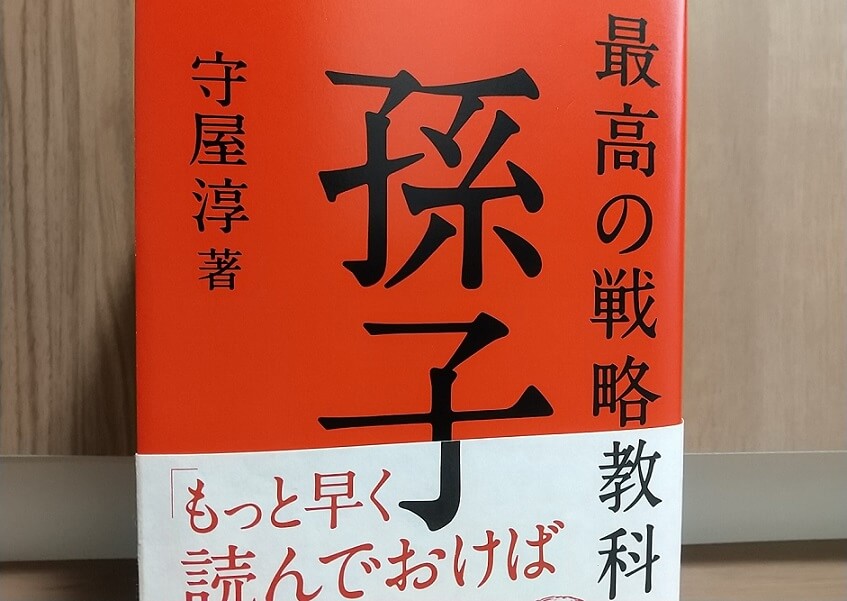
前後半に分けて、内容を簡単に要約していきます。
オススメは最初から読むことで、孫子の兵法に関する概要を把握したうえで、応用編としてⅡ部を読むことですが、好きなところから読んでも大丈夫な書き方にはなっていました。
I部 『孫子』はそもそも何を問題とし、何を解決しようとしたのか
まず「孫子とは?」という点を理解することからスタートです。
『孫子』を著したのは、春秋時代末期に活躍した孫武という将軍だと言われています。
戦国時代は生きるか死ぬか、一発勝負の時代。
一方で現代のビジネスは価値観や需要が多様化しており、「トライ&エラー」「PDCA」「アジャイル」という言葉が流行しているように、小さく生み出して失敗からの学びを次に生かすことを是とする時代です。
時代背景が大きく異なることを踏まえつつ、現代に活かせる学びを得ることが重要。
その点で言えば「勝てない戦いはしない」という考えが、孫子の兵法には根底として流れているように感じました。
如何に負けない状況を作り出すか。
第5章において説かれている「先手をとって引きずり回す」「各個撃破の原理」の考え方は現代において、とても有効な戦略だと思います。
過去の日本は高度経済成長期のように、生産すること自体が需要を満たすことに等しかったので、画一的な商品・サービスであろうと作れば売れました。
しかし、価値観と需要が多様化した現代では、企業側もどのような製品を作れば良いか手探り状態なのです。
そんな状況で、競合企業が自社の予想もしない一手を繰り出してきたら、自社の戦略は揺らいでしまうでしょう。
IT企業が銀行業に手を出すような動きがありますが、これも従来の金融機関からすると対応にリソースを割かなければならない状況を作り出しています。
うまく協業している金融機関であれば良いですが、それ以外の金融機関は活路を見出すために、本業にも身が入らないことでしょう。
そうして奔走している間に、決済機能の提供から始まり、預金口座を押さえ、為替や証券などの分野もIT企業が牛耳ってしまう。
このシナリオが現実に起こるであろうことは、想像に難くありません。
IT企業によう金融業界の席巻は、先手を打って敵を翻弄し、戦力が分散した機に各個撃破で着実に領土を広げる戦国時代にも通ずる戦略だと解釈できます。
II部 『孫子』の教えをいかに活用するか
孫子の教えというのは、全体的に抽象度が高く具体的ノウハウは説かれていないようです。
理由は本書の冒頭でも明かされるように、著者と考えらている孫武は、現代の経営コンサルタントのような存在。
具体的なノウハウを本に書ききってしまっては、本業で稼げなくなります。
ですから、我々が直接的に「孫子の兵法」を活かすことはできないのです。
そこで重要になってくるのが「抽象化と応用力」です。
後半のⅡ部では、孫子の教えを抽象的に捉え、現代に応用解釈する流れが記されています。
様々な例が書かれていますが、第十八章で書かれている「キリンとアサヒ」の例はわかりやすくと思います。
アサヒビールがスーパードライを発売して、当時最大63%のシェアを誇っていたキリンに逆転した背景。
「ラガー」という熱処理済みのビールでシェアを取りすぎていたキリンは、生ビールである「スーパードライ」を売り出して人気を得たアサヒに対抗する術がなかったのです。
単純に考えれば「同質化戦略」として、キリンも生ビールを製造すれば良かったはず。
しかし、できなかった。
なぜなら、キリンが生ビールの美味しさを肯定して新商品を出すことは、当時自社の看板商品であった「ラガー」を否定することになるからです。
逆に「苦い・苦くない」「軽い・重い」と様々な嗜好をカバーしようと戦力を分散させてしまい、各個撃破されてシェアを低下させてしまった。
相手の立場も考慮した参入障壁が形成されていたのですね。
他にもベンチャーや中小企業が大手企業を脅かす存在になっている例を、孫子の兵法を元に解釈した章もあります。
『孫子』の入門書に最適
『孫子の兵法』が現代のビジネスシーンにも応用が利く考えであることを理解して、自身のビジネス環境へ応用させる思考を持つことが、本書の一番大きな学びとなるはずです。
現代の「将」である管理職や「戦略家・参謀」である経営コンサルタントの方々は、ぜひともご一読のうえ、自身のビジネスへどのように応用することができるのかを考える機会としください。
スキマ時間・休日の自己投資にオーディオブックサービスを活用
「休日を充実させる自己投資がしたい!」
「仕事で忙しいけど、スキマ時間に勉強をしたい!」
「たくさんビジネス書を読んで、活躍できるビジネスパーソンになりたい!」
あなたも同じ考えではありませんか?
そんな人にオススメできるのが、会員数250万人を突破したオーディオブック配信サービス【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】です。
【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】のおすすめポイント
- 年割プラン料金なら「月額833円」で15,000点以上のコンテンツを聴ける
- 14日間の「聴き放題お試し」が提供されている
- 厳選されたプロがナレーターとして本を朗読する
\ 14日間の「聴き放題お試し」あり /
本をたくさん買う人には、オーディオブックの方が安くなることもあります。
audiobook.jpの年割プラン料金なら「月額833円」で15,000点以上のコンテンツを聴くことができます。
14日間の「聴き放題お試し」が提供されているので、いちど気になる作品を聴いて継続利用するかお考えてみてください。
ちなみに、Amazonの子会社であるAudible Inc.が提供するオーディオブック・サービス【Audible】の料金は月額1,500円です。
外国語のコンテンツも多いので、英語学習をしたい方はAudibleをオススメしますが、多くの方には月額880円で「聴き放題月額プラン」が使えるaudiobook.jpをオススメします。
audiobook.jpには定額の「聴き放題プラン」以外にも「チケットプラン」があります。
「チケットプラン」は通常価格 ¥1,500で1枚のチケットを購入します。
購入したチケットと聴きたい作品を交換することができます。
チケット交換した作品は永久に何度も聴くことができるので、何度も聴き返したいオーディオブックコンテンツはチケット交換がオススメです。
ビジネス書は1冊2,000円以上することもあるので、「聴き放題プラン」「チケットプラン」のどちらでもコスパが良いですよね!
最近ではAIが音声を読み上げるオーディオブックサービスもありますが、厳選されたプロがナレーターとして本を朗読するaudiobook.jpが聴き心地は良いですね。
ぜひ、スキマ時間や休日の自己投資にオーディオブック配信サービス【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】を活用してみてください!
\ 14日間の「聴き放題お試し」あり /
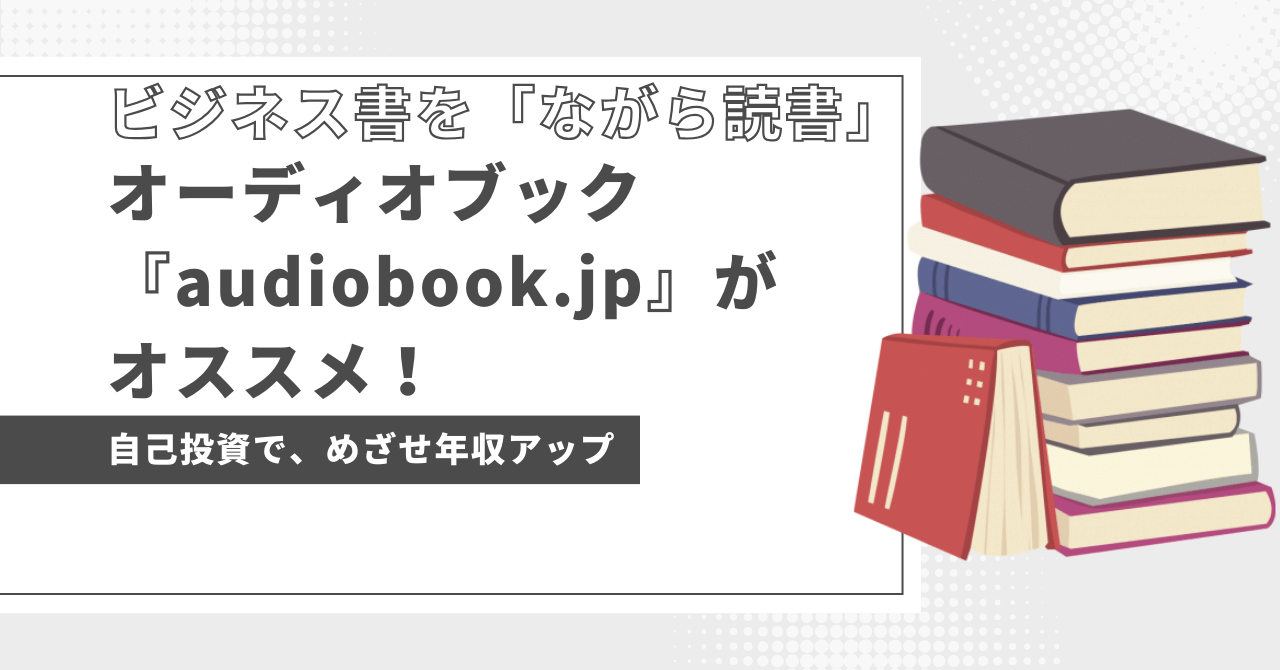
コンサルティング業界転職体験談まとめ
筆者「きつね」がコンサル転職を2回した体験談をまとめています!
30代で資産3,000万円を築いて、サイドFIREを実現したい。
そのためにコンサルティング業界で働いて年収を上げるため頑張っています。
転職をすることで年収を上げる、もしくは労働環境を改善させながら年収を維持することも可能です。
コンサル転職の成功は人それぞれですが、あなたのコンサル転職を成功させるため、ぜひ筆者「きつね」の体験談を参考にしてもらえたら嬉しいです!
コンサル転職体験談のオススメ記事
- 【オススメ】コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
- 【コンサル転職体験談】20代で年収1,000万!コンサルタントが年収を上げてきた思考法を伝授!
- 客先常駐=高級派遣?アクセンチュアやベイカレントなどの総合系コンサルが揶揄される理由
- 【コンサル転職体験談】転職候補はアクセンチュアソング、デロイト、PwC、インキュデータ
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職スケジュール公開!実際の転職ステップで要点を解説!
- 【3つの理由】「20代でコンサルタント就職・転職」が市場価値を高め、生涯年収を上げる!
- コンサル流「20代で市場価値を上げる休日の過ごし方」を紹介!暇な社会人こそ自己研鑽!
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職ならホワイト500の日系総合コンサルがオススメ!
- 【コンサル転職体験談】30代マネージャーが総合系コンサルファームを辞める理由は?
- 【コンサル転職体験談】面接でした逆質問を紹介!志望度を間接的に伝える重要要素
- 【コンサル転職体験談】コンサル就職・転職前に必読!ケース面接の対策本3選!
- 【コンサル転職体験談】職務経歴書|書き方のコツ!書類選考は全社通過!
- 【高年収】コンサルタントの種類?コンサルタントの職位・相場年収って?
- 【コンサル転職】転職活動おすすめの「企業の口コミサイト」を紹介!
- 【未経験30代のコンサル転職】コンサル転職に失敗する人の特徴3選
コンサル転職を成功させるため転職エージェントを複数利用
筆者「きつね」が内定までサポートしてもらった転職エージェントはアクシスコンサルティングでした。
>>コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
もちろんオススメですが、コンサルティング業界・ポストコンサル転職を目指すなら、転職エージェントは複数登録しておいた方が良いでしょう。
1つの転職エージェントから得られる求人情報は偏ってしまいますし、キャリア相談におけるセカンドオピニオンを得られることが複数の転職エージェントを活用するメリットです。
以下が筆者「きつね」も利用した転職エージェントです!
最近はコーチングにお金を払って転職をサポートするエージェントもいますよね。
ご紹介しているサービスはあくまで転職エージェントなので、無料で利用可能です!
転職活動の初期は複数の転職エージェントから求人情報をもらいつつ、担当さんとの相性も見極めましょう!
アクシスコンサルティング
アクシスコンサルティングは、コンサルティング業界の転職を目指すなら登録必須です。
コンサルティングファームの採用担当者と密に連携をしており、あなたの希望にあった非公開求人を紹介してくれます。
長年コンサル業界の転職を支援しているので、ケース面接対策もバッチリです。
\ コンサルティング業界に特化した転職面接サポート!! /
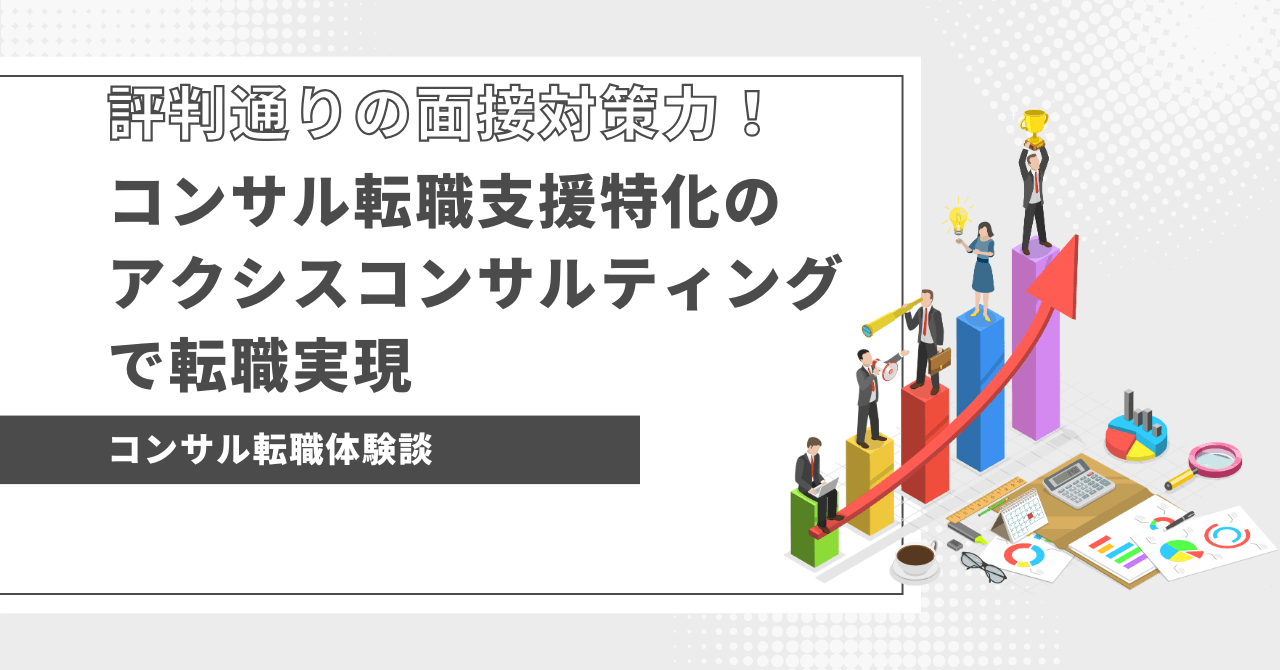
MyVision
コンサル業界出身者・人材会社出身者が立ち上げた新進気鋭のコンサル転職特化の転職支援サービスです。
200社・1,000ポジション以上の広範な紹介先ネットワークを有しているので、希望につながる転職先が見つかるはずです。
受賞歴も凄まじいですね!
コンサル転職を検討しているなら登録をオススメします。

\ コンサル転職ならMyVision /
コトラ
ハイクラス転職に強く、特に金融業界の転職に強いのが「コトラ」です。
コンサル業界の転職も支援をしてくれます。
CFOや金融業界を専門としたコンサルを目指すなら登録必須だと思います。
コンサルタントとして金融業界の支援経験がある方も登録をしておくと良いでしょう。
\ ハイクラス転職に強い! /
マスメディアン
広告業界やマーケティング職の転職を考えているなら「マスメディアン」の登録がオススメです。
「宣伝会議」という広告やマーケティングに関する出版社が運営する転職エージェントで、出版社としてのコネクションを活かした転職情報が魅力的です。
\ 広告・Web・マスコミの求人情報・転職なら! /
DODA
大手転職エージェントdodaは約12万件ある求人情報から、あなた専任のキャリアアドバイザーが希望に合致した求人情報をリストアップしてくれます。
ワークライフバランスを見直したり、業種・職種を広く検討したい場合はdodaがオススメです。
\ 大手ならでは!!安心のサポート力!! /
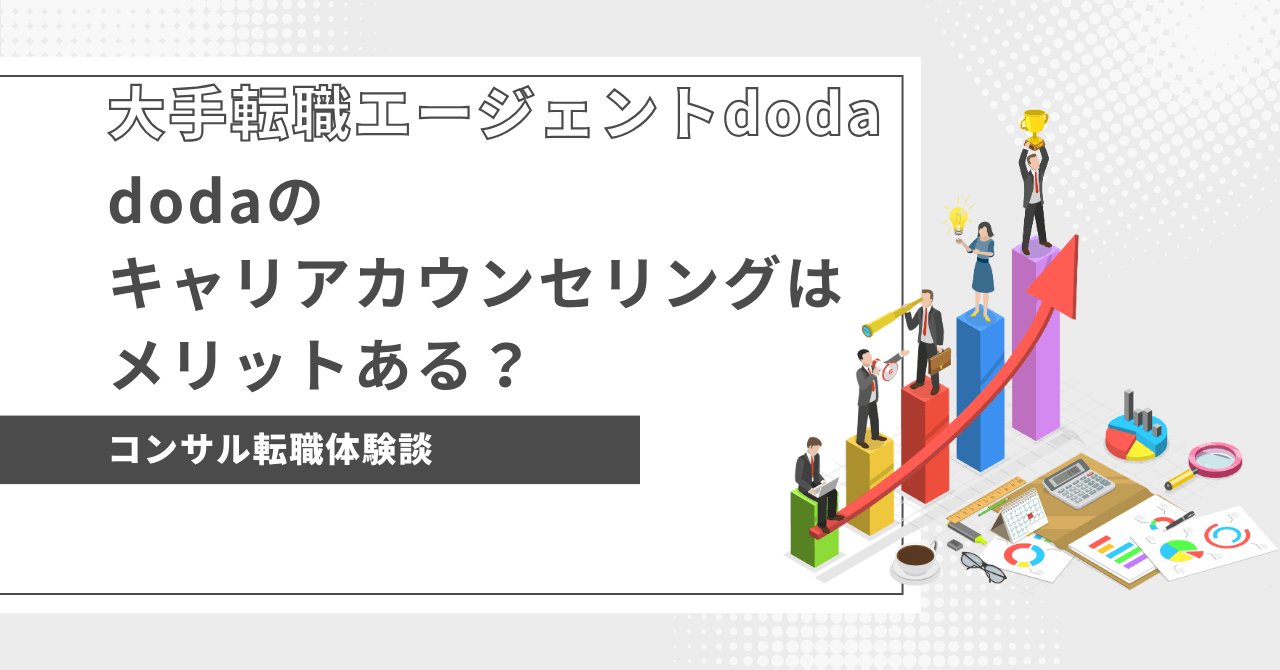
リクルートエージェント
\ 10万件以上の非公開求人! /