コンサルの 最長アベイラブル期間 は○か月が限度です。
コンサルとして一番辛い期間は「アサインされないとき」ではないでしょうか。
アベイラブルが続いて、暇な時間が続くと「自分って必要とされているのかな」と考えてしまいますよね。
でも、ピンチはチャンス。
アベイラブルこそ、キャリアアップのチャンスです!
あなたの才能を開花させる「アサインされない暇なコンサルが行うべき、アベイラブル期間の過ごし方」をご紹介します。
コンサルティング業界におけるアベイラブルとは
まずは「アベイラブル」とは何かを説明します。
※ご存知の方は読み飛ばしてください。
アベイラブルの説明
アベイラブルはavailableという英単語がもとになっています。
英単語としての意味は、「(すぐに)利用可できる」という意味です。
この英単語がコンサルティング業界で使われるときは、「コンサルタントとして、すぐに利用可能」=「プロジェクトに参画していない」ことを意味します。
つまりは待機中ということ。
コンサルティングファーム内で、職探しをしている状態になります。
アベイラブル期間は、プロジェクトで必要人員数やスキルセットによって変動します。
しかし、多様なスキルセットや高度な経験・知識を有しているコンサルタントであれば、支援中プロジェクトの終結フェーズに次のプロジェクトアサイン(参画)が決まります。
コンサル業界の アベイラブル最長期間 は?
上記のような引く手あまたのコンサルタントでなくとも、普通に活躍できる素養があるコンサルタントであれば、2週間がアベイラブル期間の平均になると思います。
「プロジェクトの合間にリフレッシュをしたい」ということで休暇を取得するコンサルタントも珍しくなく、アベイラブル期間が1ヶ月になるケースもあります。
プロジェクトを開始するための契約やクライアントとの調整もありますから、アベイラブル期間として1か月以内であれば、そこまで大きな問題にはならないでしょう。
聞いた話ではありますが、最長3ヶ月アベイラブル期間を過ごして、そのまま退職をしたコンサルタントもいたようです・・・。
休職したり、休職明けですぐにアサイン面談が組めないという事情がある場合も見てきました。
しかし、優秀なコンサルタントは基本的に、現在のプロジェクトが終わる前に次のプロジェクトが決まっていたり、プロジェクトを決めてから休暇に入っているものです。
アベイラブル期間が長くなると、ファーム内でも「あいつはアベりまくってる」とか「アベイラブル期間長いから使えないんだろう」と悪評が立ってしまいます。
変な噂を避けるためにも、アベイラブル期間は最長でも1か月程度にしたいものです。
アベイラブルによる影響(給料・評価・キャリア)
では、アベイラブル期間が長くなることで、どのような影響があるのか整理していきましょう。
コンサルタントといっても、大半の人が会社員です。
たとえアベイラブル期間があったとして、給料自体は支払われます。
一見すると給料をもらいながら、仕事をしなくてもよいという「願ったり叶ったり」の状態です。
ですが、このアベイラブル期間が続くとコンサルタントとしての評価(正確には社内評価)がどんどん悪化していきます。
コンサルタントというのはクライアントを支援する対価としてフィーをいただきます。
アベイラブル期間は当然ながら、クライアントを支援するプロジェクトに参画していないのでフィーをいただいていない。
にもかかわらず、給料は支払われる。
その給料は他のコンサルタントが得たフィーから捻出されている構図です。
コンサルティングファームの経営目線に立てば、こんな状態が受け容れられるはずがありません。
「誰かに給料を稼いでもらっているコンサルタント」となれば当然に人事評価は下がっていきます。
アベイラブル期間が長いことで、翌年度以降の報酬・給与に影響を与えるわけです。
さらに報酬・給与面のみならず、こちらも当然にキャリア形成上も悪影響が出てきます。
プロジェクトの契約タイミングなども影響しますが、休暇などと組み合わせたとしてもアベイラブル期間は長くても1か月が限度だと思います。
プロジェクトが月初に始まることも多いので、アサイン前の準備期間があったりします。
N月に前のプロジェクトが終わったとしたら、N+1月にアベイラブル期間としてアサイン面談や次のプロジェクト参画に向けたキャッチアップを行います。
そして、N+2月に新しいプロジェクトに参画する。
このサイクルが1年に1回程度であれば大きな問題はありません。
しかし、「アベイラブル期間が長い・アベイラブルになる頻度が多い」という場合は注意が必要です。
間接的に「使えないコンサルタント」という風に評価されていきます。
仕事ができないと評されるコンサルタントには、キャリアアップに繋がるプロジェクトの話はなかなか来ないのが実態でしょう。
ファームとしても仕事ができないコンサルタントには、難易度が低いが最低限の給料分を賄えるプロジェクトに参画してもらうか、見込みがなければ「辞めてもらう」ことを遠回しに促すしかなくなってしまいます。
仮に難易度の低いプロジェクトに参画できても、年齢が上がるに連れて、社会的に期待される役割などは自然と上がっていきます。
でも、実際に声がかかるのは難易度の低いプロジェクト。
そこには自分より若いけど優秀なコンサルタントがリーダーとして活躍している。
このような実態が、コンサルタントとしてのキャリアを閉ざすことに繋がってしまう方は一定数存在するでしょう。
アベイラブルになるコンサルの特徴
コンサルタントのプロジェクト参画に際し、アサイン面談ということが行われるのが常です。
プロジェクトを率いるマネージャー以上のシニアなコンサルタントが、メンバーとして迎え入れるコンサルタントを面談します。
アサイン面談を通して「プロジェクトメンバーとして期待する役割を果たせるのか」を判断します。
また、プロジェクトに参画することで被面談者であるコンサルタントが活躍し、将来的 なキャリアにプラスになるかという点も検討の俎上に上げます。
面談観点としては、主に以下となっています。
アサイン面談における確認観点
- スキル
- 経験
- 知識
- パーソナリティ(性格・キャラクター)
- キャリアプラン
アベイラブルになるコンサルの特徴①|アサイン面談下手
問題は被面談者であるコンサルタント側が面談下手だったとき。
面談を受けるコンサルタントが自身のスキルやパーソナリティの良さ、ないしはプロジェクトへの適合度を伝えることができないというケースが考えられます。
正直なところ、こういった面談というのは得手不得手もあります。
が、コンサルタント自身がクライアントに評価される仕事である以上、自社のシニアなコンサルタントに対してもアピールできないとプロジェクトに参画したとしても不幸になります。
対策としては、いわゆる面接対策しかないでしょう。
アサイン面談だからと特別なことはなく、就職・転職面接と同じように自身の強み・弱みなどを踏まえて「どう活躍できるか」をアピールする。
この練習を行うに限ります。
慣れも大きな要素です。
なので、社内外にアサイン面談をする立場のシニアなコンサルタントと繋がりがあるようでしたら、面談練習をお願いすることが最善策だと思います。
アベイラブルになるコンサルの特徴②|根本的にスキル/経験/知識不足
ここからはアサイン面談時の確認観点を細分化した理由説明になります。
「うまくアピールはできるのだけど・・・」という前提になります。
まずは、最も理由として多いであろう「スキルアンマッチ系」です。
スキル/経験/知識。
これらがプロジェクトの一員として求められる役割に適していないのであれば、致し方ありません。
アサイン面談を組む時点である程度のフィルタリングはなされているものです。
しかしながら、実際に面談をすることで期待役割を果たせないと判断されることもあります。
単純に「他の候補者の方が良かった」ということも当然にあります。
もしも、この記事を読んでくださっているあなたが若手コンサルタントであれば、そこまで気にする必要はありません。
「愚直に自己研鑽を続けていくことで、引く手あまたの人気コンサルタントになれる可能 性は充分にあります。
一方、ある程度の年齢(30代半ば以上が目安)で「スキルアンマッチ系」が理由に「アサインされない⇒アベイラブル期間が長引く」のであれば、キャリアについて考え直した方がよいタイミングかもしれません。
コンサルタントにおける30代はマネージャー以上として、プロジェクトをリードする役割が求められます。
そのような業界風潮において、30代半ばを超えてもスキルアンマッチを理由に「アサインがされない・いつもアベイラブル」という状況だと、そもそも働く環境が適していない可能性が高いです。
中長期的視点で考えて、キャリアプランを考える良い機会だと思います。
- コンサルティング業界に留まるのが良いのか
- 他の業界に転職した方が良いのか
- 現在のファームに留まるのが良いのか
- 独立した方が良いのか
上記のようなことが考えられるでしょう。
コンサルティング業界の転職やポスト・コンサルタント転職に特化した アクシスコンサルティングにご相談することをオススメします。
アベイラブルになるコンサルの特徴③|性格に難あり
この点は単純に「一緒に働きたいと思えるか」です。
ケースとしては2つに分類できます。
1つは、いくら優秀でも人として一緒に働きたくないケース。
もう1つは、プロジェクト全体を考えて「性格的にはまらない」と判断されるケース。
前者は職人気質な方に発生する可能性があります。
「実力があれば問題ない」という考えをお持ちの方ですね。
性格難を補って余りあるような、ずば抜けた実力があれば問題ないのですが、そんな人材は稀。
特にコンサルティング業界においては。
素養として優秀な人材が集まりやすく、そこから自己研鑽を続けるプロフェッショナルが集まる業界。
ずば抜けた実力を維持し続けることは難しいのが実態かと思います。
とは言え、生まれ持った気質も影響してくるので、一概に悪いとも言えないですね。
このケースにおいても、もしかしたら転職を考える良い機会かもしれません。
次に、後者の「性格的にはまらない」ケース。
完全に運が悪かっただけですね。笑
「同じテーマの、他クライアントであれば問題ないけど、今回に限っては」という感じです。
クライアント企業にも社風や文化があります。
体育会系なのか、理知的なサイエンス集団なのか、和気あいあいとした雰囲気なのか。
そこに合うか合わないか、というだけなので特に気にする必要はないと思います。
アベイラブルになるコンサルの特徴④|こだわりが強い
補足すると「キャリアに対する」こだわりが強いケースです。
自身の描くキャリアプランを実現する為にアサイン面談自体を受けないとか、アベイラブル期間が延びたとしても長い目でみて得たい経験があるから気にしないケース。
前向きな判断ではあるのですが、プロジェクトに参画していないという点は紛れもない事実。
社内評価という意味では、望ましいことではありません。
「中長期的なキャリアプラン・キャリア形成」と「短期的な人事評価」のバランスですので、自身の判断であるなら問題はないかと思います。
懸念はアベイラブル期間を延ばすことで、望むようなプロジェクトの話が来るか。
ファームとして力を入れているプロジェクトであれば良いですが、例えば「組織・人事改善のコンサルタントとしての経験を積みたい」と思っているのにIT系のファームに在籍していても意味がない、ということです。
アベイラブル期間中にキャリアプランについて悩むようでしたら、他のコンサルティングファームについて考えてみてください。
一度、真剣に考えることで、あなたのキャリアが拓かれるはずです。
アベイラブルになるコンサルの特徴⑤|社内営業力不足
社内営業力と題しましたが、要は「アサイン面談のお声が掛かるか」ということ。
社内的に埋もれているという感じ。
アサイン面談を組もうとなったときに、面談候補者の俎上にすら上がらない。
もちろんファームとしてコンサルタントを売り込んでいくのですが、一定の人脈形成をしていって、顔を売っておく活動が必要になります。
社内営業力が高かったり社内人脈形成がなされていると、アサイン面談を組みやすくなったり、バイネーム(面談なんかを組まずに指名買い)で引き合いが来るようになります。
特別意識せず、仕事を普通に行っていきながら、勉強会や社内サークルに参加すると効果的に人脈形成ができますよ。
暇なんてない!アベイラブル期間おすすめの過ごし方

ここから、筆者「きつね」がオススメする暇なアベイラブル期間の過ごし方をご紹介します。
アベイラブル期間を短くしたい・早くアサインされたい場合
アベイラブル期間は暇になりますし、評価にも影響するので、なるべく短くしたいという考えの方ですね。
社内人脈を使ってアサイン面談を組んでもらうように駆け回るのが最優先でしょう。
そして、自身のキャリアプランなどもいったんは脇に置くという心がけが必要です。
あとは「提案のお手伝いをする」というのが優良な手です。
新しくプロジェクトを立ち上げる前にクライアントに提案をするという段階があります。
ほぼほぼプロジェクト受注が決まっている前提の形式的な提案もあれば、コンペのように他社と競い合う本格的な提案もあります。
特に後者の場合は提案資料を作成するためのリサーチだったり、資料作成の作業者が不足するケースが多いです。
そこに「提案手伝いたいです!」というコンサルタントがいるのであれば、使わない手はありません。
うまくいけば、提案が通ったときにアサイン面談をパスして「お手伝いメンバーをそのままプロジェクトメンバーとして採用」という流れもあり得ます。
ただ、少しリスクもあります。
- 提案資料作成時にうまくパフォーマンスを出せない
- 提案自体が通らない
こうなってしまっては提案が終わった時点でメンバーとして参画できることはないでしょう。
アベイラブル期間を活用して、自己研鑽をしたい場合
アベイラブル期間は短い(アベイラブル期間に入ったばかり)・焦ってはいないけど、何か勉強をしたいという方の場合です。
過去に参画していたプロジェクトで実力不足を感じたとか、新しいキャリアの方向性が見えた場合は、アベイラブル期間の過ごし方として自己研鑽をするのも良いでしょう。
アサイン面談自体は少し受け身で待つような感じです。
この期間があまりにも長いと人事評価としては「稼げないコンサルタント」と見なされてしまうのですが、長い目でみて自身のキャリアプランを実現するための投資期間と捉えれば問題ないと思います。
自己研鑽にも色々とありますが、大きくは3つに分けられると思います。
- 強みの強化
- 弱みの補強
- 視野を広げるためのインプット
当然に人によって行うべきことは変わりますが、どこかのタイミングで「体系的な知識を学ぶ」ことには挑戦をしていただきたいです。
そんなときの参考になる記事をまとめています。
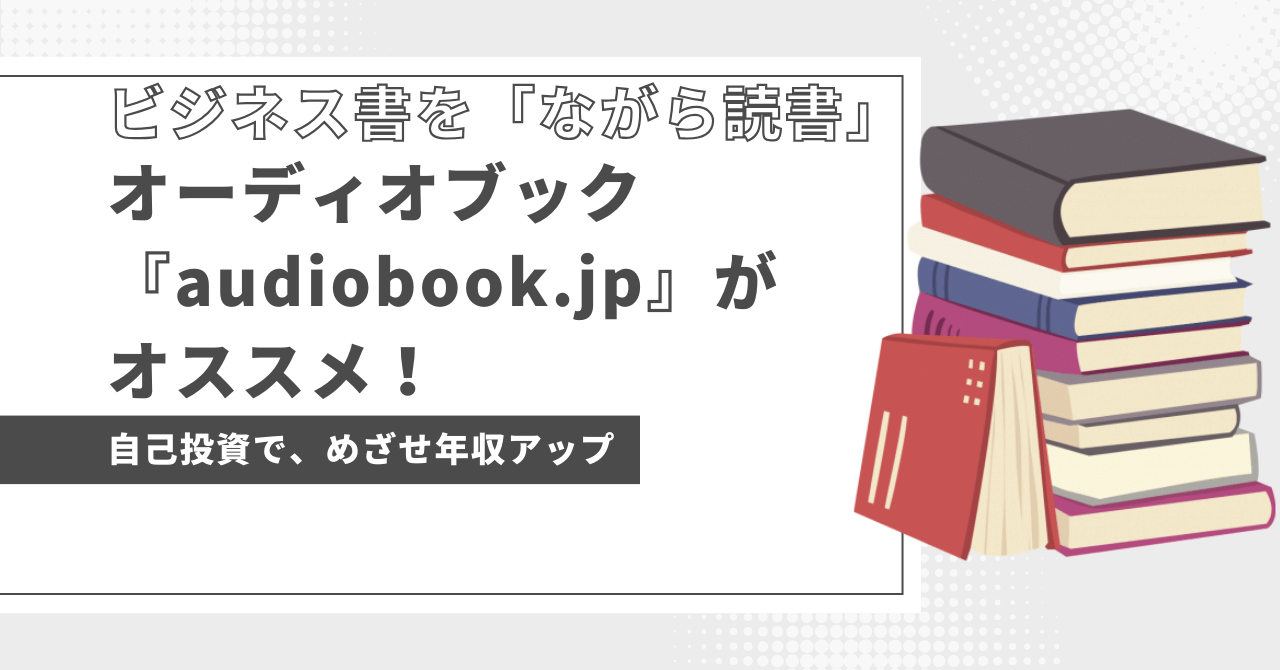
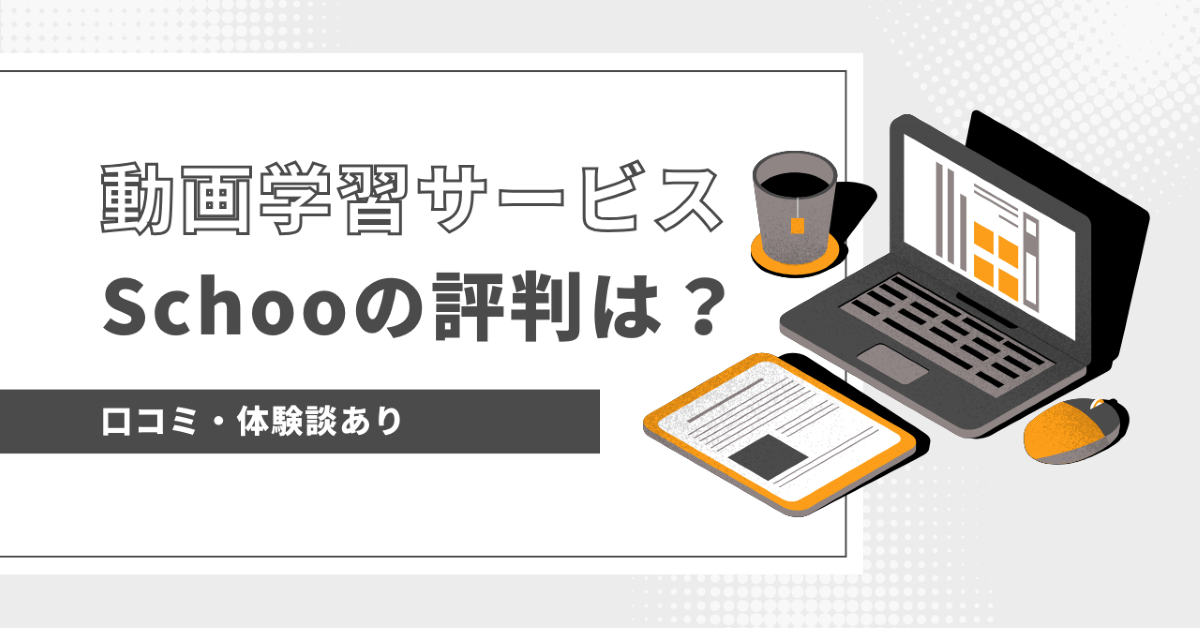
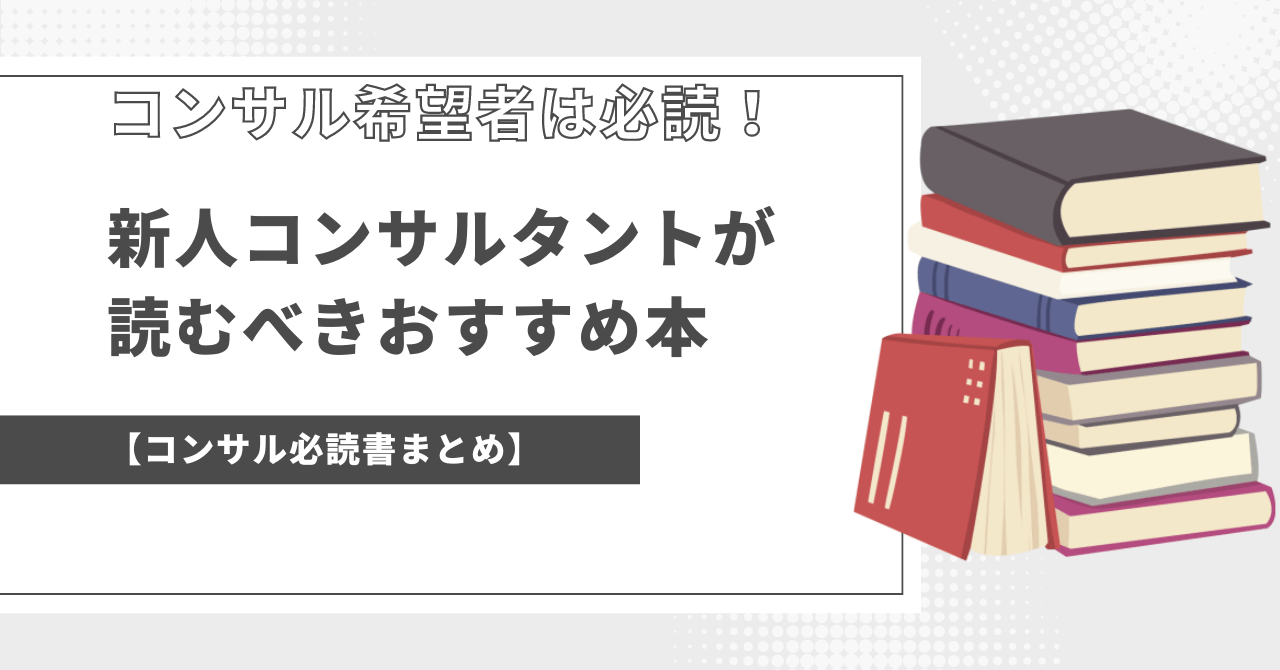
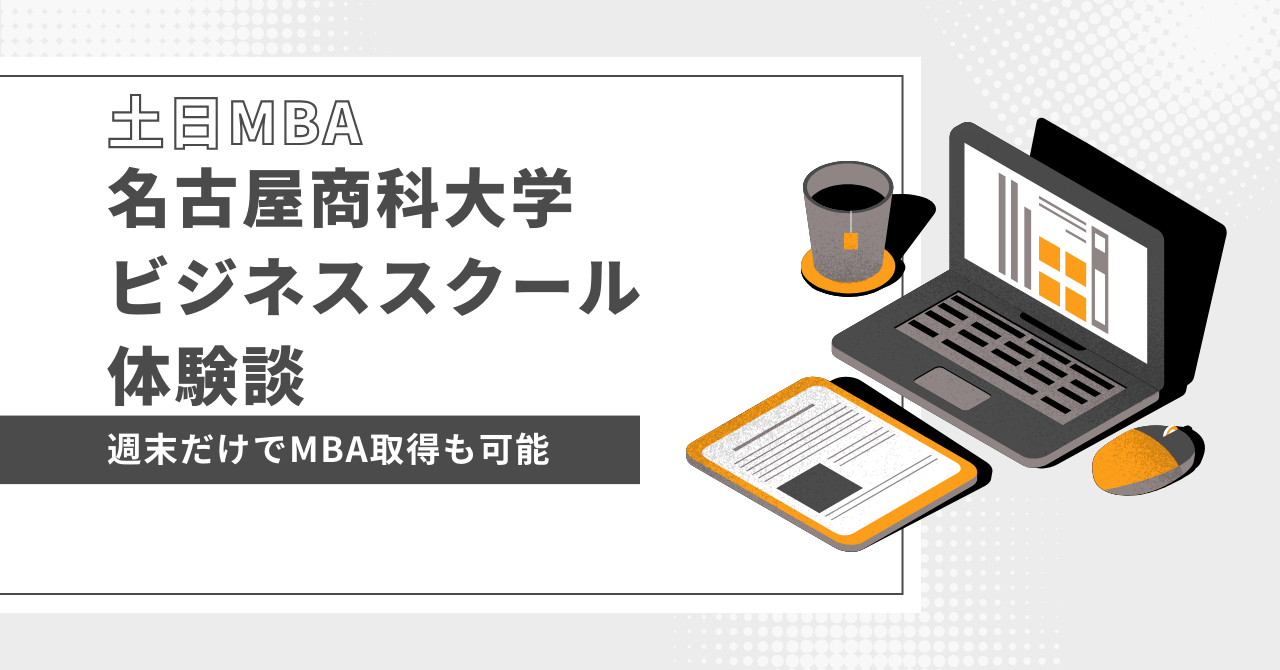
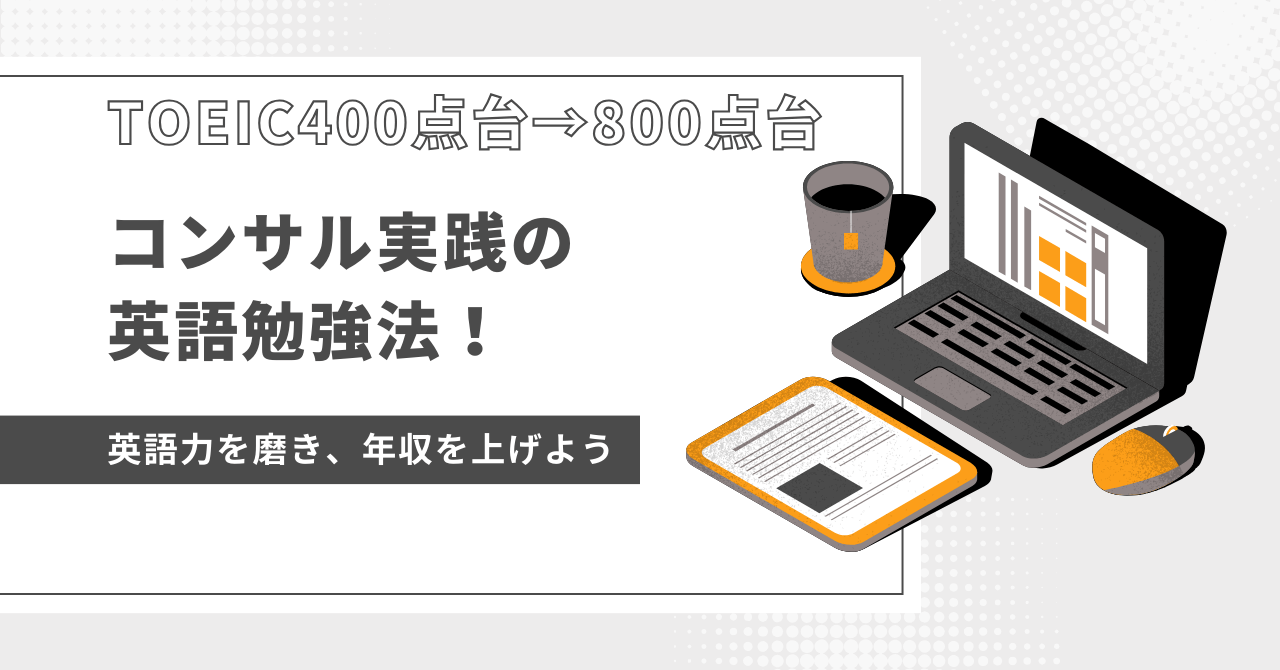
アベイラブル期間に資産運用・投資について学びたい場合
時間のあるうちに、自己投資だけではなく、金融知識を身につけて株式投資や不動産投資に挑戦することも良いと思います。
コンサルティング業界で年収を上げていくと、所得税が驚くほど控除されます・・・。
労働所得よりも金融資産や不動産投資からの所得の方が税率も低く、不動産投資においては節税効果も見込みます。
投資について詳しく学びたいあなたにはお金の教養講座がオススメです。
家計改善・資産運用・年金(老後資金)対策など、人生に関するお金の悩みを丸ごと、無料で学ぶことができます。
累計で60万人以上が受講しており、満足度は98%を超えています!
あなたに向いた「資産運用の仕方や家計改善のノウハウを知りたい!」という方は、ぜひ無料で学べる「お金の教養講座」を受講してください!
教室で受けるセミナーだけではなく、自宅で受ける動画セミナーもあるので、あなたのご都合に合わせて受講が可能ですよ。
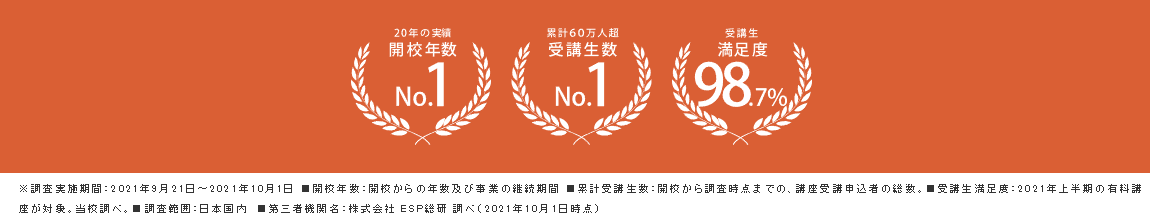
\ 累計60万人超が受講した「資産を増やすコツ」が学べる講座 /
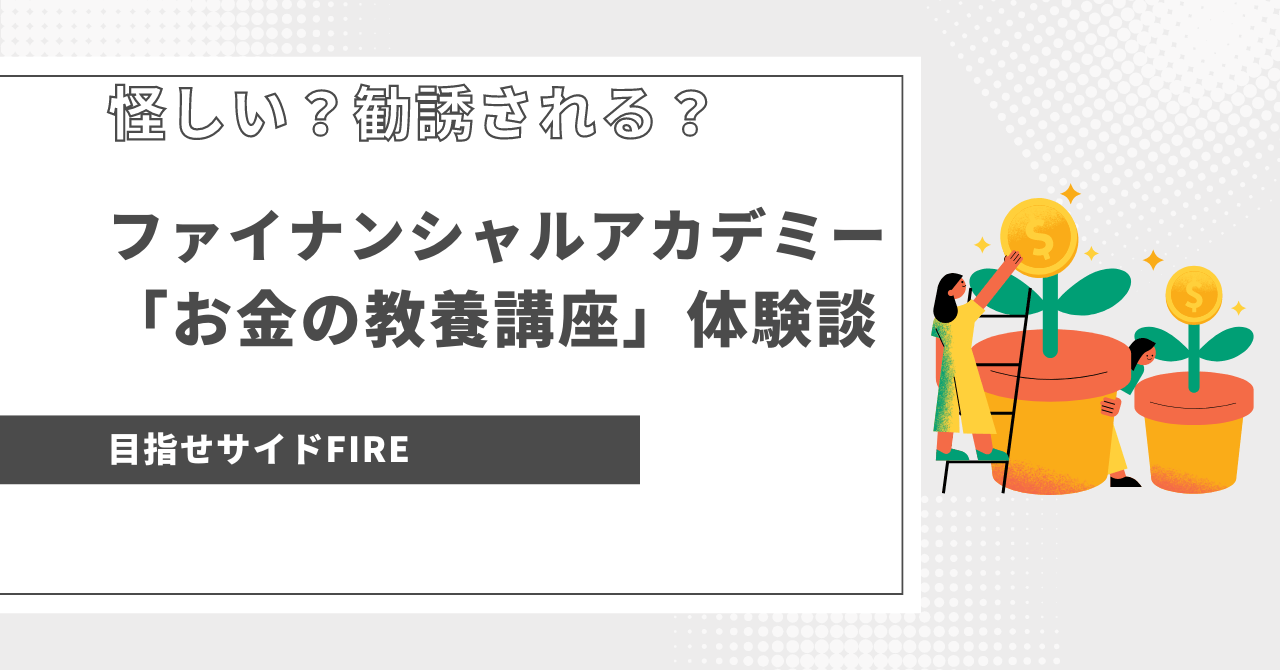
無料で不動産投資について学べる【不動産投資スクール】
特に不動産投資に興味がある方は、同じく株式会社FinancialAcademyが運営する「不動産投資スクール」がオススメです!
不動産投資に関する知識・スキルをゼロから学べますよ!
知識を増やせば増やすほど、投資のリスクを抑えることにもつながるので、ぜひ勉強してみてください!
\ 不動産投資家に必要なスキルがゼロから学べるスクールを無料体験! /
アベイラブル期間にリフレッシュしたい場合
がんばったので休みたいというシンプルな話です。笑
有給休暇が余っているのであれば、申請してしっかりとリフレッシュしましょう!
夏季休暇や冬季休暇と繋がる形で有給休暇を取得できて、かつ、アベイラブル期間であれば、かなりのリフレッシュとなります。
自己研鑽とリフレッシュを兼ねて、アベイラブル期間中にフィリピンへ語学留学に行きました。
このケースはアベイラブル期間を意図的に延ばす感じですかね。
コンサルティングファームによるでしょうが、激務・長期間のプロジェクトを終えたあとは、リフレッシュも兼ねて1か月程度のアベイラブル期間を取るのも良い選択だと思います。
アベイラブル期間を活かして転職したい場合
自身のやりたいプロジェクトや磨きたい専門性に近い経験を得られないなら、転職をしましょう。
コンサルティング業界の中での転職、コンサルティング業界から事業会社への転職。
どちらもオススメです。
所属しているコンサルティングファームとの相性・クライアント業界との相性が合わないだけで、あなたの強みが発揮できる場所は他にあると思います。
その場合、アサイン面談の話が来ても断るか、面談を組まれても採用されないように振舞ってください。
転職活動を開始したばかりだったり、内定を正式にもらう前に面談に参加してアサインが決まってしまうと、後々面倒になってしまいます。
コンサルタントとしてのキャリアについて考えるなら、コンサルティング業界の転職やポスト・コンサルタント転職に特化した アクシスコンサルティングにご相談するのが良いでしょう。
現在所属しているファームで希望の経験を積めなさそうであれば、他のファームに転職することやフリーランスのコンサルタントになる道もあります。
最近は、フリーランスのコンサルタントとプロジェクトをマッチングするプラットフォームビジネスが多数あるります。
いくつか登録をしてみると希望の経験を積める可能性がファーム内よりも高いか判断できるかもしれません。
他の転職エージェントにも相談した体験を踏まえて言えるのは、アクシスコンサルティングは「コンサル業界への知識と役員や人事とのパイプによる非公開求人」・「ケース面接含めた面接対策力」が圧倒的であるということです!
フリーランスのコンサルタントとしてのキャリア形成やマッチングサービスも展開しているので、アクシスコンサルティングに相談すれば一気通貫で悩み解消できるかもしれませんね。
きっと、あなたのキャリアプランを踏まえた転職支援やキャリアカウンセリングをしてくれるはずです。
コンサル特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』をオススメする3つの理由
- コンサル転職を長年支援してきた実績と積み重ねられてきた面接対策力
- コンサルファームの役員やパートナー、採用担当との人脈による非公開求人
- 転職希望者の長期的キャリアを見据えたキャリアコンサルティング力
筆者「きつね」が実際にアクシスコンサルティングに転職相談をした体験談をまとめているので、「いきなり登録するのは・・・。」と思う方は一度ご覧になってから決めてください!
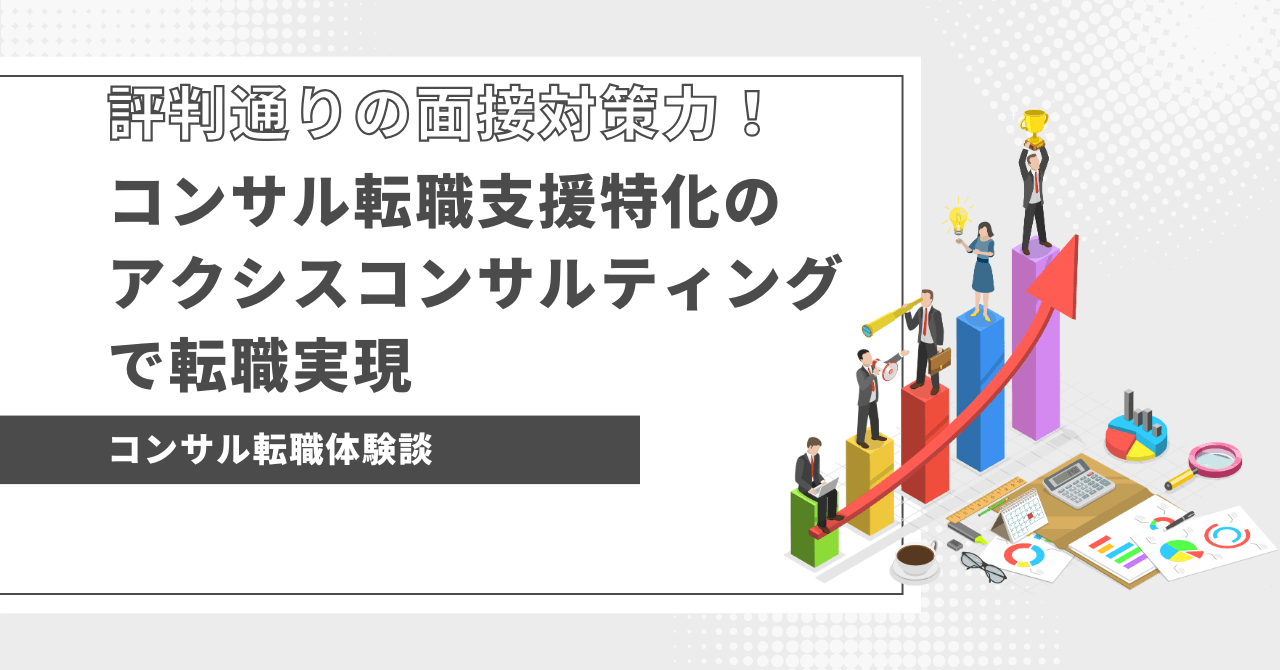
転職するならSPI対策は必須
転職の際、数多くの企業で導入されている適性試験にSPI試験があります。
人手不足で売り手市場と言われていますが、ライバルも同じ状況です。
企業は多くの求職者からできるだけ優秀な人材を採用するため、SPIを中心にした適性試験でふるいにかけます。
新卒の就職活動時に勉強した方は多いと思いますが、第二新卒であろうと経験者の転職であろうと、SPIを実施する企業はあります。
憧れの企業を見つけたのにSPIで落とされては悲しいですよね。
転職エージェントもさすがにSPI試験の対策まではフォローできません。
特に非言語分野は苦手意識を持つ人も多く、対策が必要になってきます。
筆者「きつね」も非言語は苦手です。
同じようにSPIに苦手意識を持っている方にオススメしたいのが【SMART/SPI-G】です。
書籍や動画では得ることのできない、本番試験そっくりな模擬試験を繰り返し学習することが可能なサービスとなっています。
出題傾向や解き方のコツなど、解答テクニックを掲載した解説もあるので高得点を狙う方は利用必須です。
お試し版模擬テストもあるので、まずは力試しにやってみるのも良いですね。
\ SPI対策をして転職を成功させよう!! /
アベイラブル期間を有意義に過ごしてキャリアを充実させよう
コンサルタントとして働いていると、多少のアベイラブル期間が発生することはあるでしょう。
アベイラブル期間は暇になりがちです。
何もせずダラダラと過ごすのはNGです。
しかし、次のプロジェクトアサインに向けた動きをしたり、中長期的にキャリアを見つめなおす活動をするのはOKです。
有意義な過ごし方をして、暇になりがちなアベイラブル期間に、コンサルタントとしてのキャリアアップを目指して活動していきましょう!
コンサルタントとして開花するかはアベイラブル期間の過ごし方次第
一般的な事業会社と比較して、コンサルタントという職業は自身でキャリアを切り開いていくことが求められます。
「個人事業主の集まり」のような側面もあるので、自立したキャリアプラン構築や継続的なスキルアップが欠かせません。
もちろんスキルだけではなく、プロジェクトや組織を率いていく立場でもあるので人格面も磨いていくことが求められます。
ですが、一度プロジェクトにアサインされると忙しい日々を過ごすことで、キャリアについて時間をかけて考える機会は得にくいものです。
アベイラブル期間というのは、忙しいコンサルタントが自身の人生やキャリアを見つめなおす良い機会です。
せっかくの機会を無駄にしないように、今回ご紹介した過ごし方を参考に、悔いのないコンサルタント人生を送ってください。
いつも思うのは、どれだけ才能があって本来は優秀な人材でも、環境次第では活躍するチャンスも成長する試練の場も得にくいということ。
あなたに適さない環境に身を置きつづけることで、人材としての市場価値が下がってからでは遅いのです。
コンサルティング業界転職体験談まとめ
筆者「きつね」がコンサル転職を2回した体験談をまとめています!
30代で資産3,000万円を築いて、サイドFIREを実現したい。
そのためにコンサルティング業界で働いて年収を上げるため頑張っています。
転職をすることで年収を上げる、もしくは労働環境を改善させながら年収を維持することも可能です。
コンサル転職の成功は人それぞれですが、あなたのコンサル転職を成功させるため、ぜひ筆者「きつね」の体験談を参考にしてもらえたら嬉しいです!
コンサル転職体験談のオススメ記事
- 【オススメ】コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
- 【コンサル転職体験談】20代で年収1,000万!コンサルタントが年収を上げてきた思考法を伝授!
- 客先常駐=高級派遣?アクセンチュアやベイカレントなどの総合系コンサルが揶揄される理由
- 【コンサル転職体験談】転職候補はアクセンチュアソング、デロイト、PwC、インキュデータ
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職スケジュール公開!実際の転職ステップで要点を解説!
- 【3つの理由】「20代でコンサルタント就職・転職」が市場価値を高め、生涯年収を上げる!
- コンサル流「20代で市場価値を上げる休日の過ごし方」を紹介!暇な社会人こそ自己研鑽!
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職ならホワイト500の日系総合コンサルがオススメ!
- 【コンサル転職体験談】30代マネージャーが総合系コンサルファームを辞める理由は?
- 【コンサル転職体験談】面接でした逆質問を紹介!志望度を間接的に伝える重要要素
- 【コンサル転職体験談】コンサル就職・転職前に必読!ケース面接の対策本3選!
- 【コンサル転職体験談】職務経歴書|書き方のコツ!書類選考は全社通過!
- 【高年収】コンサルタントの種類?コンサルタントの職位・相場年収って?
- 【コンサル転職】転職活動おすすめの「企業の口コミサイト」を紹介!
- 【未経験30代のコンサル転職】コンサル転職に失敗する人の特徴3選
コンサル転職を成功させるため転職エージェントを複数利用
筆者「きつね」が内定までサポートしてもらった転職エージェントはアクシスコンサルティングでした。
>>コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
もちろんオススメですが、コンサルティング業界・ポストコンサル転職を目指すなら、転職エージェントは複数登録しておいた方が良いでしょう。
1つの転職エージェントから得られる求人情報は偏ってしまいますし、キャリア相談におけるセカンドオピニオンを得られることが複数の転職エージェントを活用するメリットです。
以下が筆者「きつね」も利用した転職エージェントです!
最近はコーチングにお金を払って転職をサポートするエージェントもいますよね。
ご紹介しているサービスはあくまで転職エージェントなので、無料で利用可能です!
転職活動の初期は複数の転職エージェントから求人情報をもらいつつ、担当さんとの相性も見極めましょう!
アクシスコンサルティング
アクシスコンサルティングは、コンサルティング業界の転職を目指すなら登録必須です。
コンサルティングファームの採用担当者と密に連携をしており、あなたの希望にあった非公開求人を紹介してくれます。
長年コンサル業界の転職を支援しているので、ケース面接対策もバッチリです。
\ コンサルティング業界に特化した転職面接サポート!! /
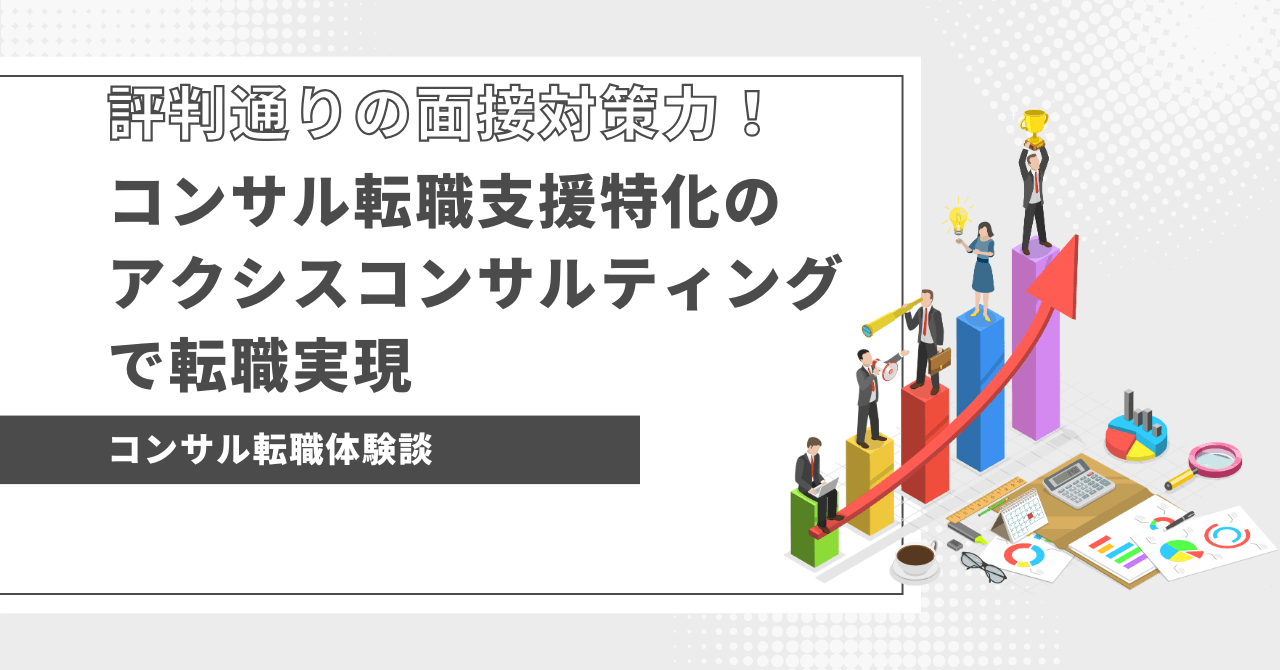
コトラ
ハイクラス転職に強く、特に金融業界の転職に強いのが「コトラ」です。
コンサル業界の転職も支援をしてくれます。
CFOや金融業界を専門としたコンサルを目指すなら登録必須だと思います。
コンサルタントとして金融業界の支援経験がある方も登録をしておくと良いでしょう。
\ ハイクラス転職に強い! /

マスメディアン
もし、あなたがコンサルティング業界にこだわらず、広告業界やマーケティング職の転職を考えているなら「マスメディアン」の登録がオススメです。
「宣伝会議」という広告やマーケティングに関する出版社が運営する転職エージェントで、出版社としてのコネクションを活かした転職情報が魅力的です。
多くの事業会社におけるマーケティング職や広告・クリエイティブ職の求人情報が掲載されています。
大手転職エージェント・転職サイトでは見つけにくい専門的な職種の情報が掲載されていますし、マスメディアンの担当者も職種特化で知識も豊富。
マーケティング職にキャリアチェンジしたい場合、マーケティング職としてキャリアアップを目指したい場合も力になってくれるはずです。
\ 広告・マーケティングの求人情報・転職なら! /
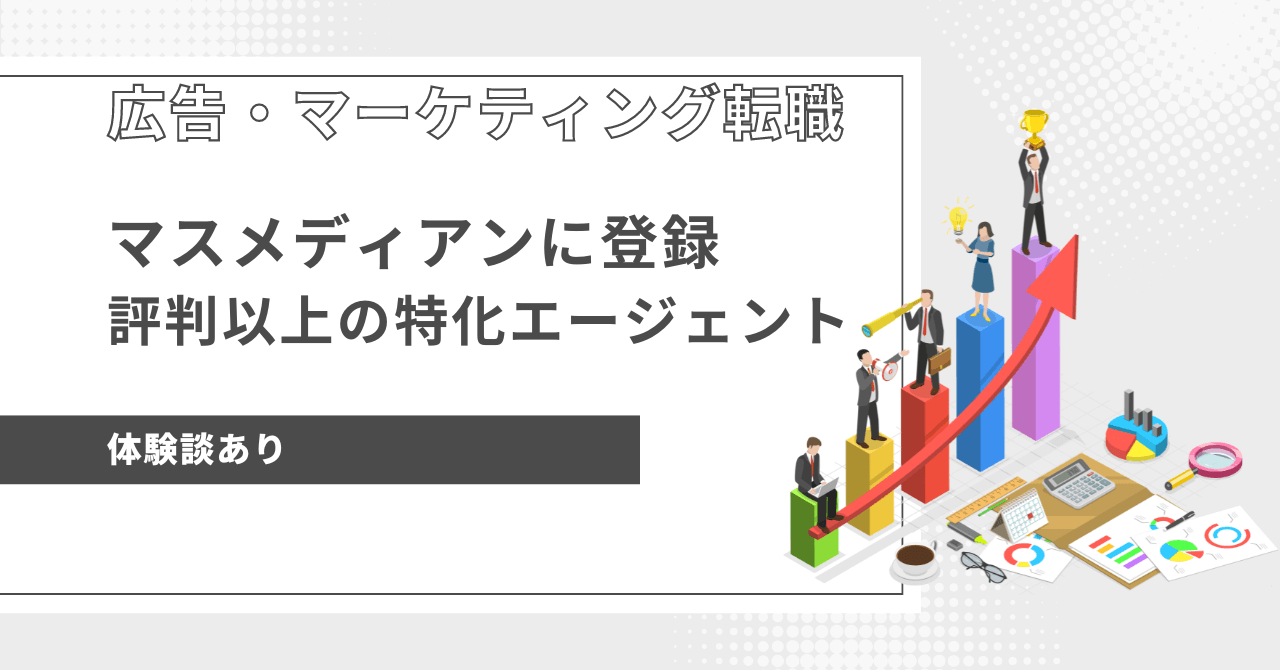
DODA
大手転職エージェントdodaは約12万件ある求人情報から、あなた専任のキャリアアドバイザーが希望に合致した求人情報をリストアップしてくれます。
ワークライフバランスを見直したり、業種・職種を広く検討したい場合はdodaがオススメです。
\ 大手ならでは!!安心のサポート力!! /
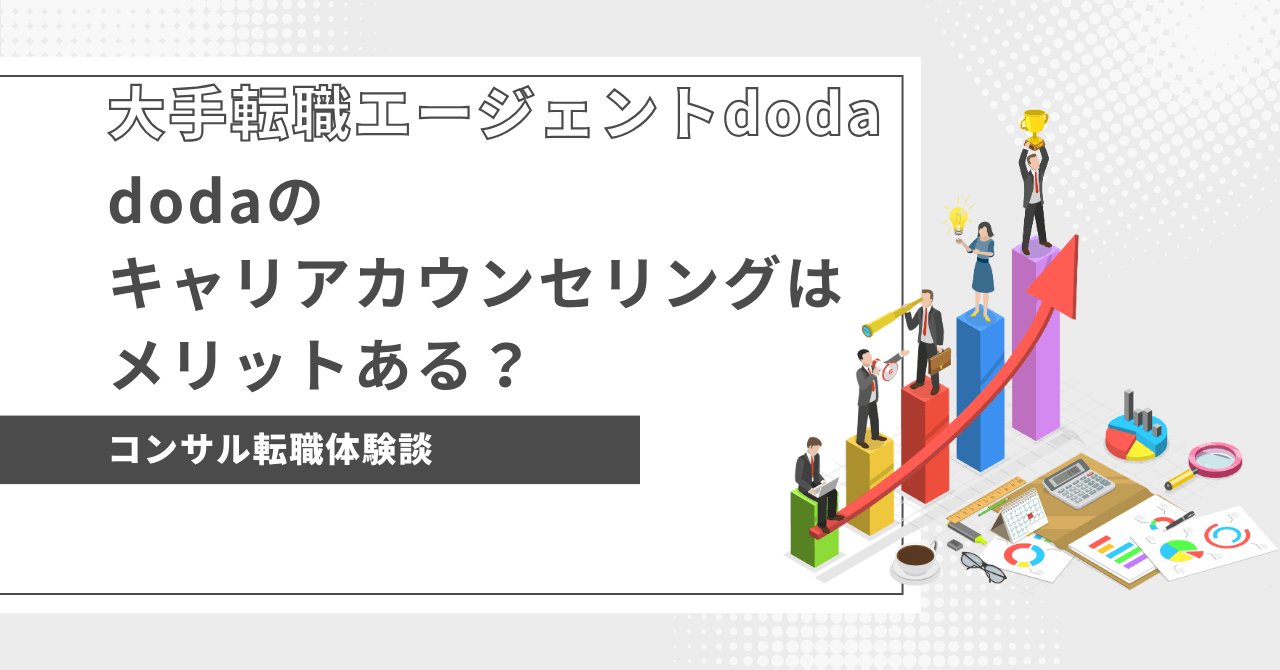
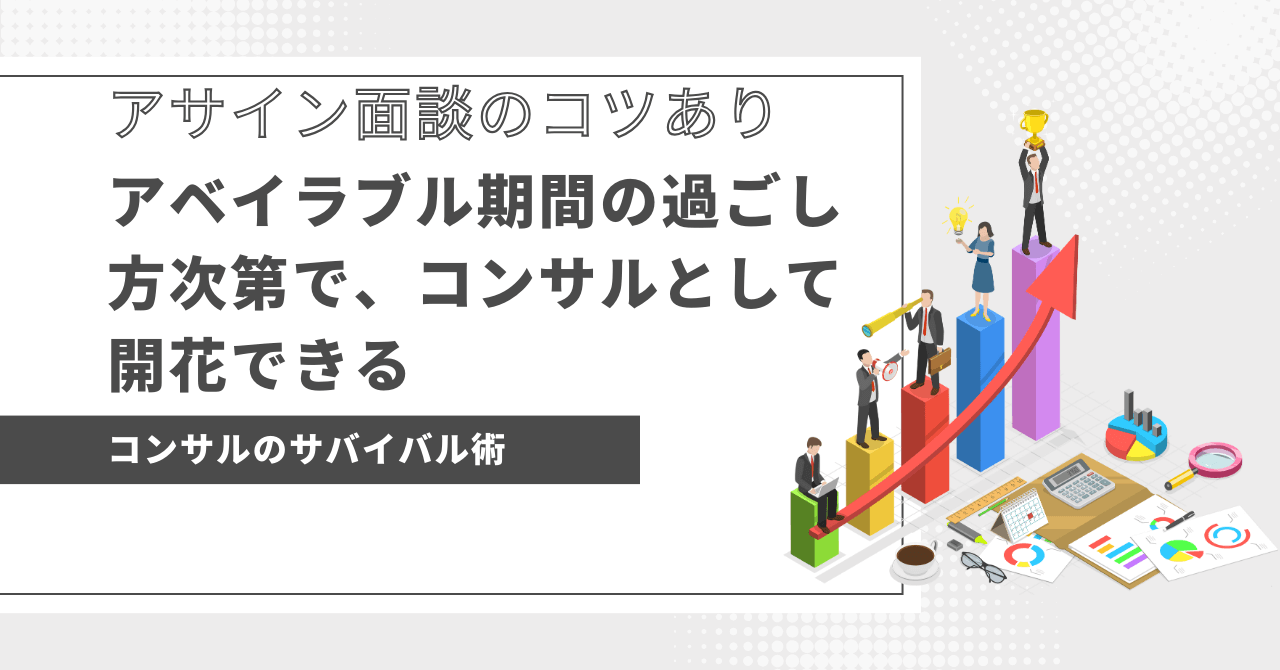



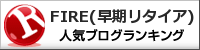
コメント