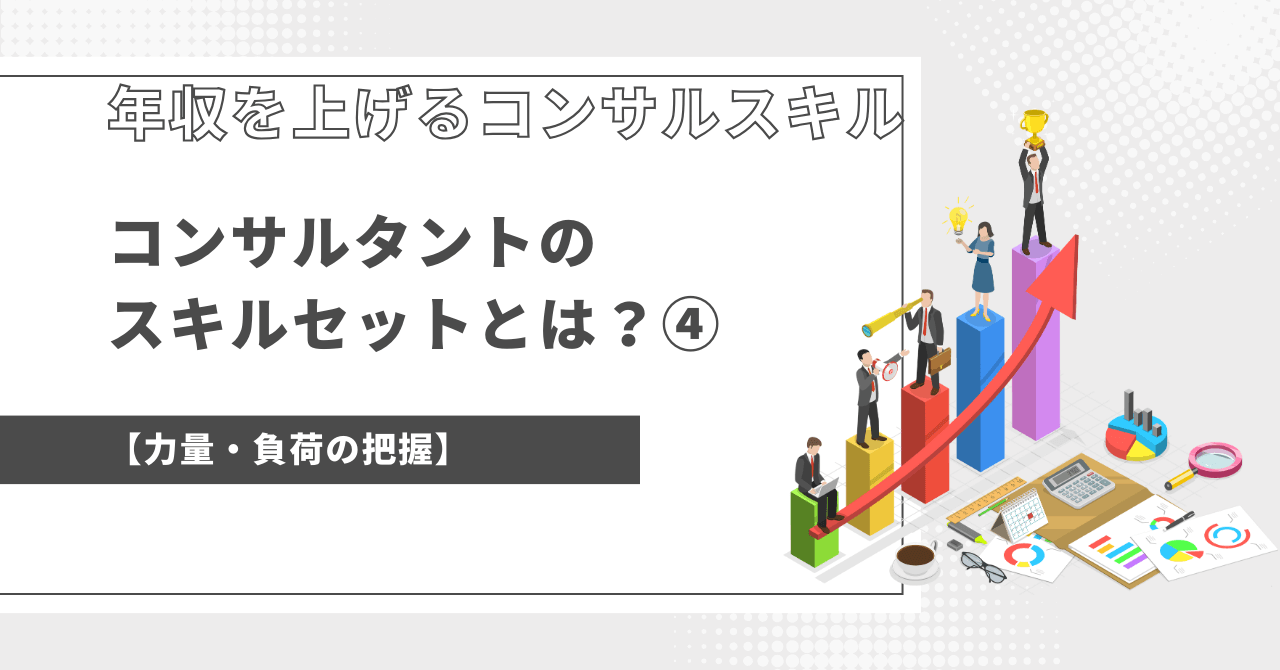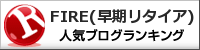コンサルタントに転職を検討している、もしくはコンサルタントに転職したのであれば、その目的は年収を上げるということも含まれていますよね。
筆者「きつね」もコンサルティングファームで働いていますが、その目的は年収を上げて投資に回す力(入金力)を上げるためです。
投資をした先にはサイドFIREを目指しています。
あなたもサイドFIREを目指しているかはわかりませんが、年収を上げたいと思ってこの記事にたどり着いたのだと思います。
筆者「きつね」がコンサルティングファームで指導を受けてきたエース級の人々の共通スキルセットをお伝えすることで、あなたも年収を上げるヒントになる。
そう思って「年収を上げるコンサルタントが備える5つのスキルセット」紹介記事を5つ書いています。
今回は4記事目になります。
高年収で活躍しているコンサルタントは、なぜかクライアントや部下の状況を本当によく理解しています。
クライアントや部下が経験してきた仕事内容や知識・スキルがどのようなものか、仕事の仕方や雑談から情報を得るように常に意識しているのです。
仕事に関することだけではなく、プライベートでなにかパフォーマンスに影響を及ぼすことが起こっていないかもアンテナを張っています。
仕事の成果に繋がることを知っているから・・・。
コンサルタントとして「年収を上げるスキル」とは
年収を上げるには、仕事ができるようになる必要があります。
「仕事ができるようになるには」
誰しもが一度は考えますよね?
仕事ができるようになるには、スキルを磨く必要があります。
私も新人時代は毎日のように考えて、反省して、本を読んではスキルを磨くために実践して・・・。
その繰り返しと上司からの厳しくも温かいご指導を受けて、クライアントからも評価されるほどには成長できました。
同じような悩みを持つ方は年齢問わずにいらっしゃることでしょう。
しかし、その立場や経験によって「仕事ができる」ということの捉え方が変わってきます。
「作業者」としてではなく「コンサルタント」という役割を念頭にした「仕事ができる人」が備えているスキルセットを5つお伝えしていきます。
再掲ですが、これまで私が出会ったマネージャー以上の優秀なコンサルタントに共通していたスキルセットです。
年収を上げるスキルセット④:関係者の力量や負荷状況を把握している
プロジェクトやチームを率いるマネージャーには、プロジェクト関係者の実力や心身の健康を考慮したタスクの割り振りが求められます。
しかし、他人の実力や心身の健康状態を把握するというのは「言うは易く行うは難し」です。
管理責任者としてプロジェクトを成功させると共に、特にメンバーに対してはモチベーション管理やメンタルヘルスケアなども求められます。
モチベーションやメンタルヘルスケアに関して、心理学的知見に基づいた専門理論(動機付け理論や職業性ストレスモデル等々)はたくさん存在しています。
「これらの理論が頭に入っていればメンバーへの接し方や管理にヒントを得られるのではないか。」
そのように思われる方もいらっしゃるでしょう。
もちろん、心理学的知見に基づいた専門理論を知っているに越したことはないのです。
でも難しいことを考え過ぎず、自分専用の「ステークホルダー管理簿」と「定期的な非公式面談」でメンバーの実情を把握しましょう。
ステークホルダー管理簿
まずはプロジェクトマネジメントとして基本的なお話からです。
プロジェクト体制図や組織体制図などからステークホルダー(プロジェクトに関係する人や組織)の役割・印象・期待を整理しましょう。
形式的な体制図はどのプロジェクトにも存在すると思います。
体制図から一段階深掘りした自分専用の「ステークホルダー管理簿」を作成するのです。
自分が直接関わった人について以下のことをメモしていくのです。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 氏名 | そのままですが、自分が分かれば良いので愛称でも良いです。 |
| 所属 | 組織体(会社名やチーム名)を記載してください。 |
| 役割 | 所属している組織における役割や果たすべき責任です。ここまでは形式的な情報です。 |
| 印象 | あなたの抱く印象を書いてください。 「話しやすそうなのか・とっつきにくいのか」程度でも構いません。 |
| 期待 | 「この人がこう動いてくれたら」という期待です。 あくまでプロジェクト推進に寄与する内容である必要があります。 |
形式的なステークホルダーマネジメントではなく、自分がプロジェクト推進していくことを考えるのであれば、自分が直接関与できる人に対する実情把握に労力を割いた方が効果的です。
上記5点について、自分の理解をそのままに書いてください。
そして、印象や期待の通りに関係者がプロジェクトに影響を与えているのかそうでないのか、暫く観察してください。
そうすることで相手の実情が見えてきます。
また「数カ月前は期待通りだったのに、最近は少し・・・。」という違和感を感じたら、相手の身に何か起こっている予兆かもしれません。
これは公式的な資料ではなく、自分用の資料です。
テキストでもExcelの表でも良いです。
ですが、保存場所は少なくとも自分専用ストレージに留めておくことをオススメします。
「定期的な非公式面談」のすすめ
メンバーの状況を把握するためには、日頃の人間関係も重要ですが「非公式面談」を実施することがオススメです。
前提として、人事評価には影響を与えないことを伝えましょう。
「非公式」という意味はこの点にあります。
人事評価としての面談だと意識させてしまうと、本音での会話ができなくなります。
部下が安心して本音を話せるように人事評価に直接的な影響はないことを明言しましょう。
もう1つのポイントはあくまでも話す主体は部下であるという点です。
非公式面談は「上司としてのあなたが部下であるメンバーのことを聞かせてもらう場」です。
上司は聞き役に徹するつもりで、共感や同調といった傾聴スキルを駆使して部下の悩み事や不満・不安、もしくは仕事への意気込みや意欲などを引き出してください。
非公式な面談であればこそ、人と人との会話ということで本音が伺える機会が増えていきます。
最初は部下も警戒するでしょうが、面談を繰り返していく内に徐々に心を開いてくれます。
非公式という前提付きでも心の壁があると感じた場合は、あなたの方から本音を語ってみましょう。
「実は最近、疲れが取れなくてね・・・。」
「やっぱりプロモーションを考えているときは楽しいな!」
このように自己開示をしていくと、少しずつですが相手も「私も話そうかな」という気持ちになってきます。
ぜひお試しください。
メンバーからの「謝罪」が増えたら要注意
日頃のコミュニケーションや非公式面談をするときに、意識していただきたいことがあります。
それは「謝罪の言葉は増えていないか」ということです。
負荷が高まり疲労が溜まると自尊心が低くなりがちです。
これは自分の体験談ですが、心身ともに疲労が溜まっていたときは、明らかにメールでの謝罪文面が多くなっていました。
仕事の手伝いをお願いするときも、普段なら「ありがとうございます」なのに、疲れているときは「申し訳ないのですが」という言葉を使っていることに気付きます。
私は自身の謝罪が増えたら危ないサインだと知っていますが、知らない方もいらっしゃるでしょう。
あなたの部下もそのことを知らない可能性があります。
日頃から部下の謝罪が増えていないかを意識して、あなたが気付いてあげてください。
他にもある「年収を上げるコンサルタントのスキルセット」
「マネジメント」という言葉にはプロジェクトやタスクに対するマネジメントだけではなく、人に対するマネジメントも含まれています。
人に対して興味を持てない・成果物の品質を高めることに集中したいという堅気な職人タイプの方もいるでしょうから、年収を上げるスキルとして必須とは言えないかもしれません。
しかし、多くの場合は人に対するマネジメントスキルは求められることが多いです。
あなたも非公式面談を含めたコミュニケーションを通して、ステークホルダーの状況を掴んでおくようにしましょう。
他にもある高年収を実現した優秀なコンサルタントたちが有するスキルを学んで、あなたの年収を上げるヒントになれば嬉しいです。
コンサルティング業界転職体験談まとめ
筆者「きつね」がコンサル転職を2回した体験談をまとめています!
30代で資産3,000万円を築いて、サイドFIREを実現したい。
そのためにコンサルティング業界で働いて年収を上げるため頑張っています。
転職をすることで年収を上げる、もしくは労働環境を改善させながら年収を維持することも可能です。
コンサル転職の成功は人それぞれですが、あなたのコンサル転職を成功させるため、ぜひ筆者「きつね」の体験談を参考にしてもらえたら嬉しいです!
コンサル転職体験談のオススメ記事
- 【オススメ】コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
- 【コンサル転職体験談】20代で年収1,000万!コンサルタントが年収を上げてきた思考法を伝授!
- 客先常駐=高級派遣?アクセンチュアやベイカレントなどの総合系コンサルが揶揄される理由
- 【コンサル転職体験談】転職候補はアクセンチュアソング、デロイト、PwC、インキュデータ
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職スケジュール公開!実際の転職ステップで要点を解説!
- 【3つの理由】「20代でコンサルタント就職・転職」が市場価値を高め、生涯年収を上げる!
- コンサル流「20代で市場価値を上げる休日の過ごし方」を紹介!暇な社会人こそ自己研鑽!
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職ならホワイト500の日系総合コンサルがオススメ!
- 【コンサル転職体験談】30代マネージャーが総合系コンサルファームを辞める理由は?
- 【コンサル転職体験談】面接でした逆質問を紹介!志望度を間接的に伝える重要要素
- 【コンサル転職体験談】コンサル就職・転職前に必読!ケース面接の対策本3選!
- 【コンサル転職体験談】職務経歴書|書き方のコツ!書類選考は全社通過!
- 【高年収】コンサルタントの種類?コンサルタントの職位・相場年収って?
- 【コンサル転職】転職活動おすすめの「企業の口コミサイト」を紹介!
- 【未経験30代のコンサル転職】コンサル転職に失敗する人の特徴3選
コンサル転職を成功させるため転職エージェントを複数利用
筆者「きつね」が内定までサポートしてもらった転職エージェントはアクシスコンサルティングでした。
>>コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
もちろんオススメですが、コンサルティング業界・ポストコンサル転職を目指すなら、転職エージェントは複数登録しておいた方が良いでしょう。
1つの転職エージェントから得られる求人情報は偏ってしまいますし、キャリア相談におけるセカンドオピニオンを得られることが複数の転職エージェントを活用するメリットです。
以下が筆者「きつね」も利用した転職エージェントです!
最近はコーチングにお金を払って転職をサポートするエージェントもいますよね。
ご紹介しているサービスはあくまで転職エージェントなので、無料で利用可能です!
転職活動の初期は複数の転職エージェントから求人情報をもらいつつ、担当さんとの相性も見極めましょう!
アクシスコンサルティング
アクシスコンサルティングは、コンサルティング業界の転職を目指すなら登録必須です。
コンサルティングファームの採用担当者と密に連携をしており、あなたの希望にあった非公開求人を紹介してくれます。
長年コンサル業界の転職を支援しているので、ケース面接対策もバッチリです。
\ コンサルティング業界に特化した転職面接サポート!! /
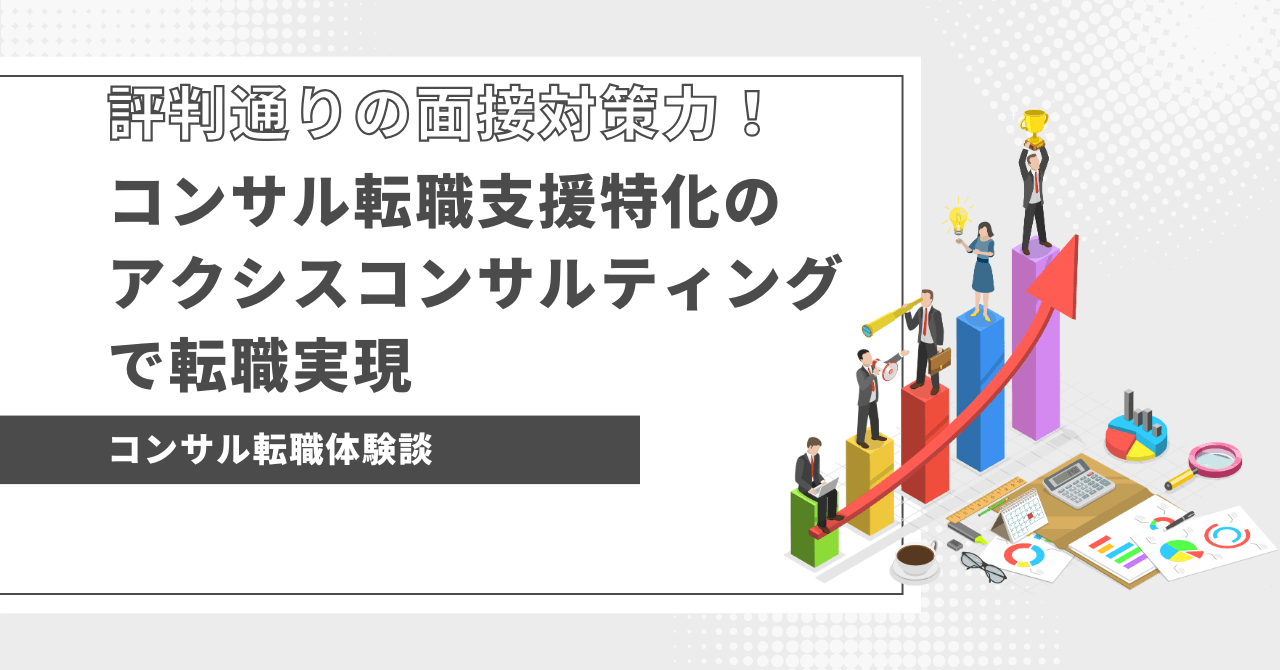
MyVision
コンサル業界出身者・人材会社出身者が立ち上げた新進気鋭のコンサル転職特化の転職支援サービスです。
200社・1,000ポジション以上の広範な紹介先ネットワークを有しているので、希望につながる転職先が見つかるはずです。
受賞歴も凄まじいですね!
コンサル転職を検討しているなら登録をオススメします。

\ コンサル転職ならMyVision /
コトラ
ハイクラス転職に強く、特に金融業界の転職に強いのが「コトラ」です。
コンサル業界の転職も支援をしてくれます。
CFOや金融業界を専門としたコンサルを目指すなら登録必須だと思います。
コンサルタントとして金融業界の支援経験がある方も登録をしておくと良いでしょう。
\ ハイクラス転職に強い! /
マスメディアン
広告業界やマーケティング職の転職を考えているなら「マスメディアン」の登録がオススメです。
「宣伝会議」という広告やマーケティングに関する出版社が運営する転職エージェントで、出版社としてのコネクションを活かした転職情報が魅力的です。
\ 広告・Web・マスコミの求人情報・転職なら! /
DODA
大手転職エージェントdodaは約12万件ある求人情報から、あなた専任のキャリアアドバイザーが希望に合致した求人情報をリストアップしてくれます。
ワークライフバランスを見直したり、業種・職種を広く検討したい場合はdodaがオススメです。
\ 大手ならでは!!安心のサポート力!! /
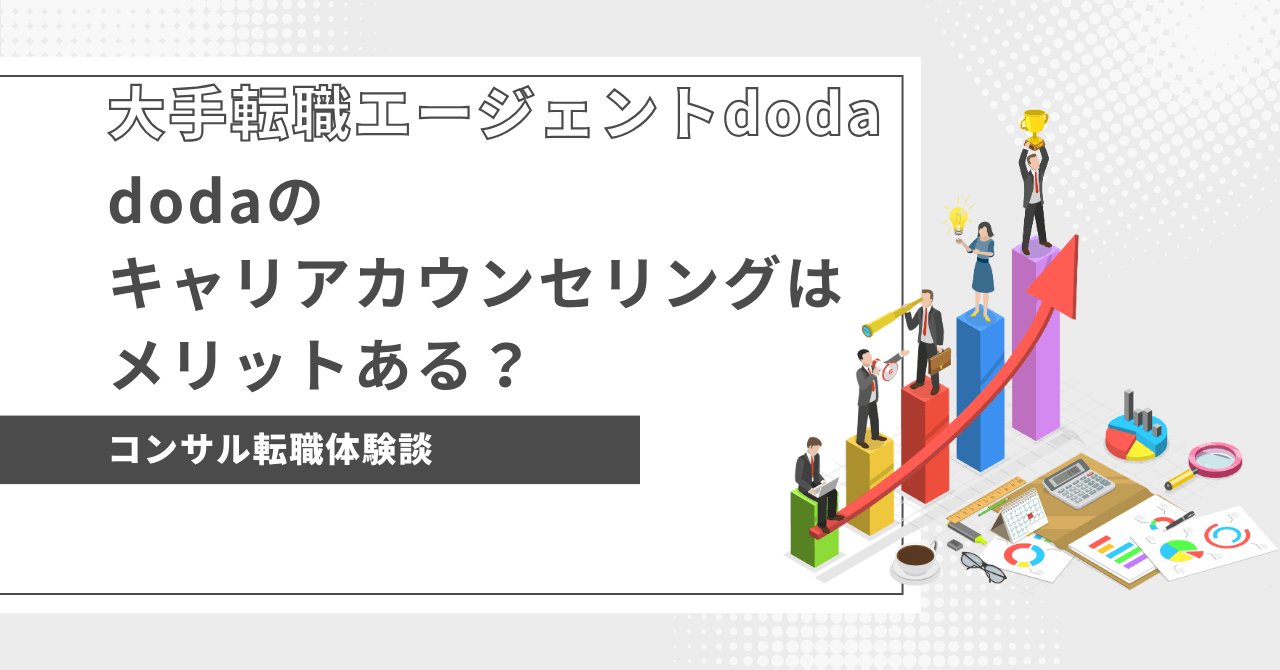
リクルートエージェント
\ 10万件以上の非公開求人! /