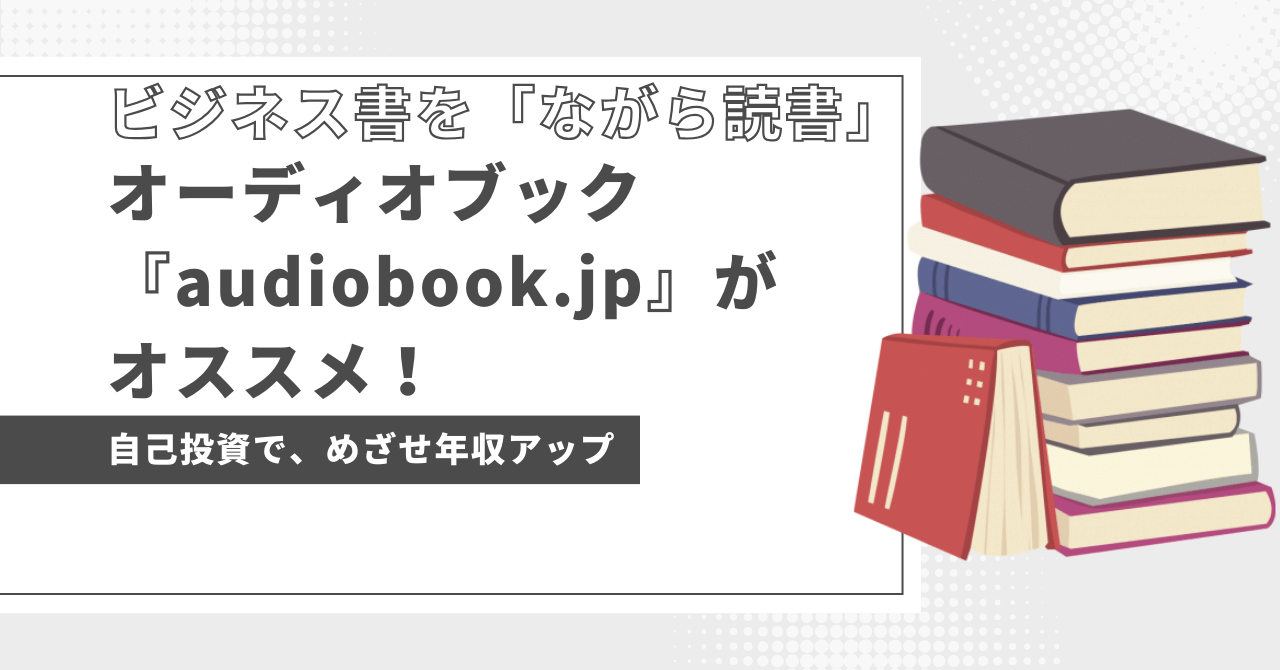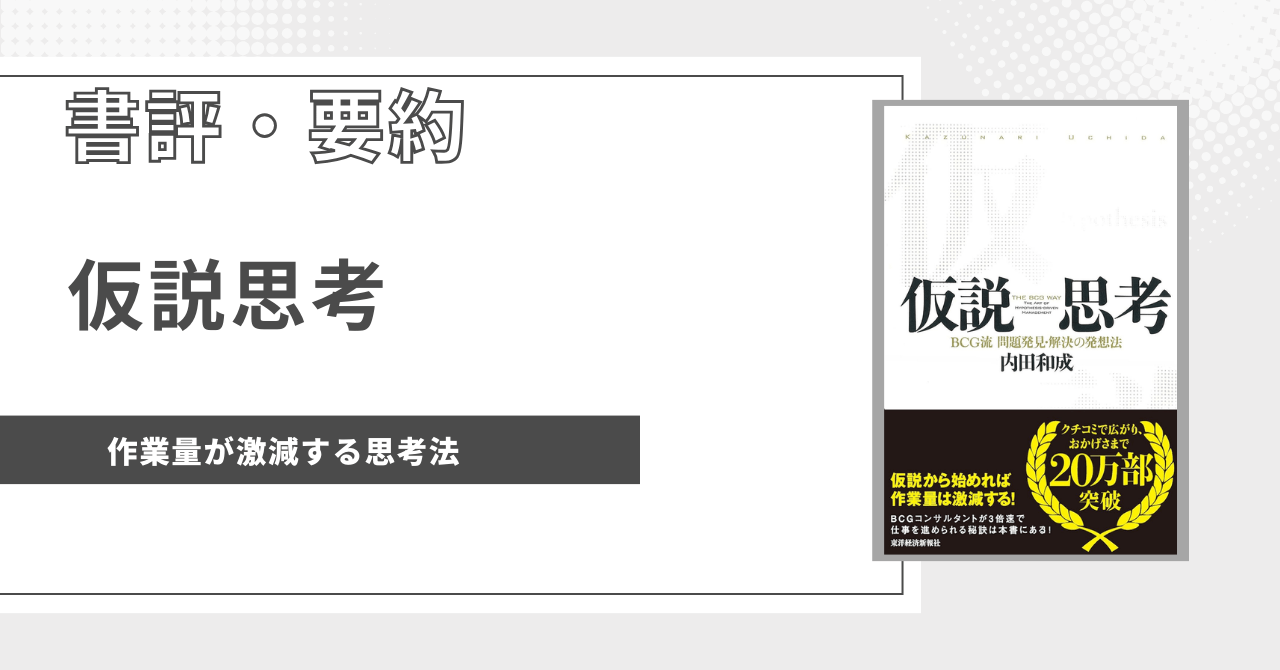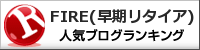手当たり次第に情報を集めてから考える。
考えた結果、何か違う。
でも、何が違うのか、次に何をすれば良いのか分からなくて途方に暮れる。
このような仕事の仕方を続けていては、仕事はいつまでも片付きません。
そこで取り入れたい課題解決力を底上げする考え方が説かれている『 仮説思考 』の書評と要約です。
仮説思考|概要
さっそくですが、『 仮説思考 』の概要と要約としてのまとめポイントをご紹介します。
『仮説思考』のまとめ
- 手元にある少ない情報から決めた「仮の答え」を検証する形で調査や分析を行うことで効率的に必要な情報を収集できる。(=不要な情報を切り捨てられる)
- 「仮の答え」が間違っていることが明確になったのなら、何が間違っていたのかを整理して「仮の答え」を進化させていくことが効率的な意思決定に繋がる。
コンサルタントに限らず、課題解決に関わる全ての方が読むことで、日本の生産性が高まるのではないかと思っています。
あなたが何かの企画を考えるとき、とりあえず関係ありそうな事柄や他社事例を調査していませんか?
「何か自分の企画や提案に活かせそうなことはないか」と調査作業を進めることは、一見すると普通のことでしょう。
しかし、限りある自分の人生。
そのような非効率な進め方では、心も体も疲弊してしまいます。
仮の答えを検証する形で、自分の企画や提案をブラッシュアップしていきましょう。
仮説思考|おすすめ読者
- 自分の仕事が遅いと悩む新人コンサルタント
- 転職したばかりで事業会社との思考法の違いに苦しむ方
- 意思決定力を高めたいリーダーやマネージャー層の方
ここで質問です。
「出世をして年収を上げたい・キャリアアップをしたい!」
「副業/複業に挑戦したい!」
「投資をして不労所得を得たい!」
筆者「きつね」と同じく、あなたもそう考えたことはありませんか?
書籍から知識を得ることであなたの目的達成に近づきますが、本を購入すると費用も場所も負担になりますよね・・・。
そんなお悩みを持つあなたにオススメするのが『Amazon Kindle Unlimited』です。
200万冊以上の本が読み放題になるAmazon(アマゾン)の電子書籍読み放題サービスで、「あなたの年収を上げる・サイドFIRE実現を助ける・不労所得をゲットする」本が見つかります!
電子書籍よりも紙の本が好きという方もいるかもしれませんが、初めてご利用の方は30日間の無料体験が可能です。
使いにくければ30日経過する前に解約をしましょう。
無料期間終了後は月額980円で使えます。
「1か月だと読み切れないし、1年だと長すぎるかも・・・。」
もちろん、いつでも解約できるので3か月くらい集中して本を読み漁って解約するという使い方でも良いかもしれません。
>>Amazon Kindle Unlimitedを無料で試してみる\ 初回利用は30日間無料!200万冊以上の本が読み放題 /
仮説思考|著者紹介
『仮説思考』を著したのはボストン・コンサルティング・グループ(BCG)の日本代表も務めていらした内田 和成さんです。
著者
- 内田 和成(うちだ かずなり)
- 1951年生まれ
- 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 (KBS) 修了
⇒日本航空勤務
⇒ボストン・コンサルティング・グループ
⇒同社日本代表やシニア・アドバイザー
⇒早稲田大学ビジネススクール教授
姉妹本として「論点思考」もお読み頂きたいです。
こちらでご紹介しています。
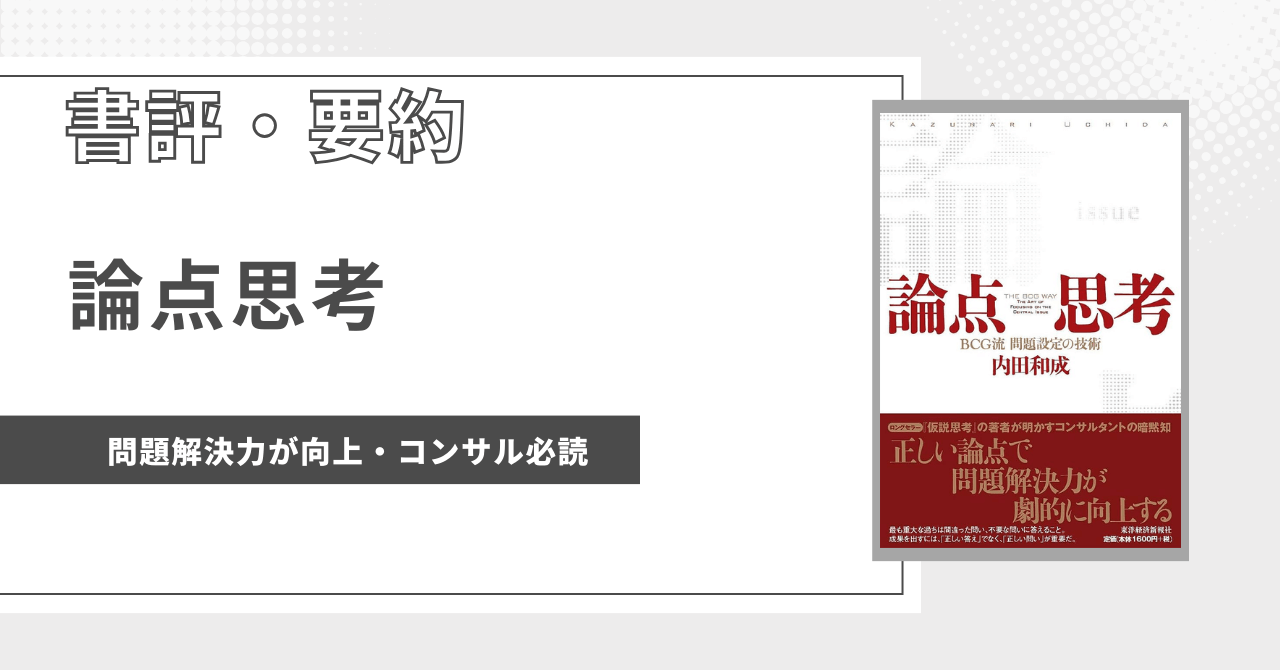
ここで質問です。
「出世をして年収を上げたい・キャリアアップをしたい!」
「副業/複業に挑戦したい!」
「投資をして不労所得を得たい!」
筆者「きつね」と同じく、あなたもそう考えたことはありませんか?
書籍から知識を得ることであなたの目的達成に近づきますが、本を購入すると費用も場所も負担になりますよね・・・。
そんなお悩みを持つあなたにオススメするのが『Amazon Kindle Unlimited』です。
200万冊以上の本が読み放題になるAmazon(アマゾン)の電子書籍読み放題サービスで、「あなたの年収を上げる・サイドFIRE実現を助ける・不労所得をゲットする」本が見つかります!
電子書籍よりも紙の本が好きという方もいるかもしれませんが、初めてご利用の方は30日間の無料体験が可能です。
使いにくければ30日経過する前に解約をしましょう。
無料期間終了後は月額980円で使えます。
「1か月だと読み切れないし、1年だと長すぎるかも・・・。」
もちろん、いつでも解約できるので3か月くらい集中して本を読み漁って解約するという使い方でも良いかもしれません。
>>Amazon Kindle Unlimitedを無料で試してみる\ 初回利用は30日間無料!200万冊以上の本が読み放題 /
仮説思考|書籍詳細
タイトルにもなっている「仮説」とは何か、本の内容を引用して確認していきます。
仮説とは呼んで字のごとく「仮の説」であり、われわれコンサルタントの世界では、「まだ証明はしていないが、最も答えに近いと思われる答え」である。
引用:仮説思考, p16
この定義における「答え」の部分が、解くべき「問題」か問題に対する「解決策」なのかは状況に応じて解釈を変える必要があります。
この本では、様々な状況で役に立つ「仮説思考」について、仮説の立て方から検証、仮説思考力の高め方も含めて体系的に記されています。
「仮説思考」の章構成
- 序章:仮説思考とは何か
- 第1章:まず、仮説ありき
- 第2章:仮説を使う
- 第3章:仮説を立てる
- 第4章:仮説を検証する
- 第5章:仮説思考力を高める
- 終章:本書のまとめ
序章:仮説思考とは何か
概要:
・情報が多ければ良い意思決定ができるとは限らない。
・「最も答えに近い」と思われる答えを早い段階で持つ。
第1章:まず、仮説ありき
概要:
・「課題分析⇒答え」ではなく「仮の答え⇒分析⇒証明」のプロセスが重要。
・網羅的に全ての事象を考慮するのは非効率であり、仮説を元に全体像(ストーリー)を描くことで効率的な情報収集に繋がる。
・間違った仮説を元にしたアプローチも仮説再構築を実施することで、結果的には網羅的アプローチよりも効率的な結果が得られる。
第2章:仮説を使う
概要:
・「問題発見の仮説」と「問題解決の仮説」の2段構えの「仮説」を使う。
・「仮説⇒実験⇒検証」のプロセスを繰り返すことで仮説を進化させる。
・仮説思考で作り上げた全体像(ストーリー)を用いることで、大局観を他者と共有できる為、人を動かすにも有効に働く。
第3章:仮説を立てる
概要:
・仮説が思いつく瞬間はディスカッション、分析、インタビューと様々であり定石は存在しない。
・仮説を立てる為の頭の使い方としては以下がある。
方法1:反対側から見る(=立場を変えてみる)
方法2:両極端に振って考える(=真逆の概念について考えてみる)
方法3:ゼロベースで考える(=既存の枠組みを捨て、白紙から考える)
・よい仮説の条件には以下がある。
条件1:掘り下げられている(「なぜ、そうなのか」が考えられている)
条件2:アクションに結びつく(仮説証明時に具体的な行動を開始できる)
第4章:仮説を検証する
概要:
・「実験」による検証は、現場での変化やプロトタイプの地域限定的販売等である。
・「ディスカッション」による検証は、バラエティ豊かなメンバーで仮説を進化させることを目的に実施する。
・「分析」による検証は、定量分析が中心となり、「比較・差異」「時系列」「分布」「因数分解」という手法がある。
第5章:仮説思考力を高める
概要:
・「So What?を常に考える」「なぜを繰り返す」ことが仮説思考を鍛えるトレーニングとなる。
・日常生活の中でも、気になることや疑問に思うことの理由や背景について仮説を立ててみる。
・「知的に打たれ強く」なり自身で仮説を進化させられることが、成長に繋がる。
終章:本書のまとめ
概要:
・仮説の効用は、生産性の向上(仕事が速くなり、質が上がる)である。
・慣れるまでの気持ち悪さを乗り越えて結論から考える。
・失敗を繰り返して「枝葉ではなく幹が描ける人間」を目指す。
仮説思考|読んだ感想
仮説で動くことへの恐怖心を克服することが最初にして最大の壁のように感じています。
特に間違うことや失敗することに慣れていない人、周りの評価が気になる人にとっては難しい考え方だと思います。
まずは自分の私生活でも良いですし、失敗しても影響の少ない仕事等で心と頭を慣らしていくことからスタートさせてみてください。
さぁ、窓を開けてみてください。
「明日の天気は何だと思いますか?」
コンサル転職・自己研鑽に有効な資格は?
筆者「きつね」が実際に合格/勉強して、コンサルティング業務や自己研鑽に役立ったと思える資格を紹介します。
ぜひ、あなたのコンサル転職・自己研鑽の参考としてください!
コンサル転職前のオススメ資格/勉強記事
>>20代コンサルにおすすめ!年収を上げるIT資格【応用情報技術者試験】
>>【基本情報技術者試験】20代のコンサル転職で年収を上げるIT資格
>>【対策本あり】文系こそ取得すべき国家資格『ITパスポート』取得メリットを紹介
>>文系のIT未経験コンサルタントがプログラミングを学ぶべき3つの理由
>>【本も紹介】図解思考の技術・モデリング技術で概念を具体化【資格のUMTPもオススメ】
>>【合格体験談】マーケティング検定3級の体感難易度は簡単!勉強時間に参考書も紹介
>>【コンサル転職体験談】資格挑戦:マーケティング検定2級に挑戦|いきなり合格は無理?難易度は3級より確実に高い!
>>TOEIC400点台から800点台!コンサル実践の英語勉強法
>>【PMBOK】5つのプロセスと10の知識エリアはコンサル必修科目
>>新人コンサルにおすすめの資格「ビジネス会計検定3級」:簿記との違い・難易度・合格率をまとめた!
>>【オススメ】動画学習サービスSchoo(スクー)は評判がいい!
>>【無料あり】マーケティングが学べるオススメ動画学習サービス5選
コンサル転職に有利な資格合格に向けて
コンサル転職・転職後の自己研鑽として、資格取得を目指して勉強することはオススメです。
コンサルティング業界で働いていると、常に試験勉強をするように新しい知識をキャッチアップしないといけないので「勉強慣れ」をしておくとよいでしょう。
【STUDYing】中小企業診断士・応用情報技術者などをカバー
上記の資格をフルサポートしているわけではありませんが、スキマ時間で効率的に中小企業診断士などの資格合格を目指すなら、STUDYingも使うのもオススメです。
STUDYing中小企業診断士講座の2022年2次試験の最終合格実績が「業界No.1」
- 【合格実績 No.1!】
- ※12022年2次試験合格者数:167名
- 【合格者続々輩出中!】
- 2023年1次試験合格者数:510名
※1:同種の資格講座を提供している業者について、KIYOラーニング株式会社が2023年11月6日時点でHP上に記載されている合格者実績を調査した範囲での比較となります。
【診断士ゼミナール】格安で中小企業診断士を目指す!
高難易度ですが、コンサル転職に有利な資格として有名な「中小企業診断士」を目指すなら、低価格&高品質な中小企業診断士試験合格講座である【診断士ゼミナール】も検討してみてください!
>>42,000円からの中小企業企業診断士講座【診断士ゼミナール】【アガルート】MBA取得・中小企業診断士合格を目指す!
「中小企業診断士」の合格や「MBA取得」を検討している方は【アガルート】で対策をするのもオススメです!
講義はオンライン・フルカラーのテキストが届くので、印刷の手間なく勉強を始められますよ。
コンサルティング業界転職体験談まとめ
筆者「きつね」がコンサル転職を2回した体験談をまとめています!
30代で資産3,000万円を築いて、サイドFIREを実現したい。
そのためにコンサルティング業界で働いて年収を上げるため頑張っています。
転職をすることで年収を上げる、もしくは労働環境を改善させながら年収を維持することも可能です。
コンサル転職の成功は人それぞれですが、あなたのコンサル転職を成功させるため、ぜひ筆者「きつね」の体験談を参考にしてもらえたら嬉しいです!
コンサル転職体験談のオススメ記事
- 【オススメ】コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
- 【コンサル転職体験談】20代で年収1,000万!コンサルタントが年収を上げてきた思考法を伝授!
- 客先常駐=高級派遣?アクセンチュアやベイカレントなどの総合系コンサルが揶揄される理由
- 【コンサル転職体験談】転職候補はアクセンチュアソング、デロイト、PwC、インキュデータ
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職スケジュール公開!実際の転職ステップで要点を解説!
- 【3つの理由】「20代でコンサルタント就職・転職」が市場価値を高め、生涯年収を上げる!
- コンサル流「20代で市場価値を上げる休日の過ごし方」を紹介!暇な社会人こそ自己研鑽!
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職ならホワイト500の日系総合コンサルがオススメ!
- 【コンサル転職体験談】30代マネージャーが総合系コンサルファームを辞める理由は?
- 【コンサル転職体験談】面接でした逆質問を紹介!志望度を間接的に伝える重要要素
- 【コンサル転職体験談】コンサル就職・転職前に必読!ケース面接の対策本3選!
- 【コンサル転職体験談】職務経歴書|書き方のコツ!書類選考は全社通過!
- 【高年収】コンサルタントの種類?コンサルタントの職位・相場年収って?
- 【コンサル転職】転職活動おすすめの「企業の口コミサイト」を紹介!
- 【未経験30代のコンサル転職】コンサル転職に失敗する人の特徴3選
コンサル転職を成功させるため転職エージェントを複数利用
筆者「きつね」が内定までサポートしてもらった転職エージェントはアクシスコンサルティングでした。
>>コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
もちろんオススメですが、コンサルティング業界・ポストコンサル転職を目指すなら、転職エージェントは複数登録しておいた方が良いでしょう。
1つの転職エージェントから得られる求人情報は偏ってしまいますし、キャリア相談におけるセカンドオピニオンを得られることが複数の転職エージェントを活用するメリットです。
以下が筆者「きつね」も利用した転職エージェントです!
最近はコーチングにお金を払って転職をサポートするエージェントもいますよね。
ご紹介しているサービスはあくまで転職エージェントなので、無料で利用可能です!
転職活動の初期は複数の転職エージェントから求人情報をもらいつつ、担当さんとの相性も見極めましょう!
アクシスコンサルティング
アクシスコンサルティングは、コンサルティング業界の転職を目指すなら登録必須です。
コンサルティングファームの採用担当者と密に連携をしており、あなたの希望にあった非公開求人を紹介してくれます。
長年コンサル業界の転職を支援しているので、ケース面接対策もバッチリです。
\ コンサルティング業界に特化した転職面接サポート!! /
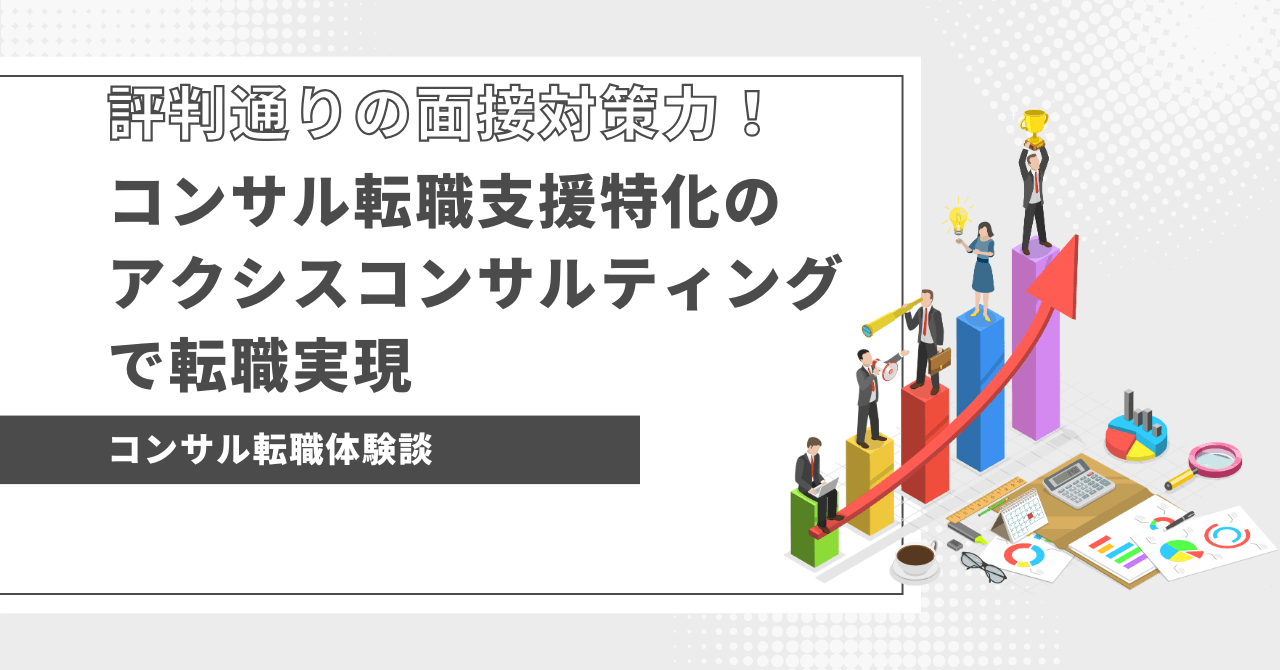
MyVision
コンサル業界出身者・人材会社出身者が立ち上げた新進気鋭のコンサル転職特化の転職支援サービスです。
200社・1,000ポジション以上の広範な紹介先ネットワークを有しているので、希望につながる転職先が見つかるはずです。
受賞歴も凄まじいですね!
コンサル転職を検討しているなら登録をオススメします。

\ コンサル転職ならMyVision /
コトラ
ハイクラス転職に強く、特に金融業界の転職に強いのが「コトラ」です。
コンサル業界の転職も支援をしてくれます。
CFOや金融業界を専門としたコンサルを目指すなら登録必須だと思います。
コンサルタントとして金融業界の支援経験がある方も登録をしておくと良いでしょう。
\ ハイクラス転職に強い! /
マスメディアン
広告業界やマーケティング職の転職を考えているなら「マスメディアン」の登録がオススメです。
「宣伝会議」という広告やマーケティングに関する出版社が運営する転職エージェントで、出版社としてのコネクションを活かした転職情報が魅力的です。
\ 広告・Web・マスコミの求人情報・転職なら! /
DODA
大手転職エージェントdodaは約12万件ある求人情報から、あなた専任のキャリアアドバイザーが希望に合致した求人情報をリストアップしてくれます。
ワークライフバランスを見直したり、業種・職種を広く検討したい場合はdodaがオススメです。
\ 大手ならでは!!安心のサポート力!! /
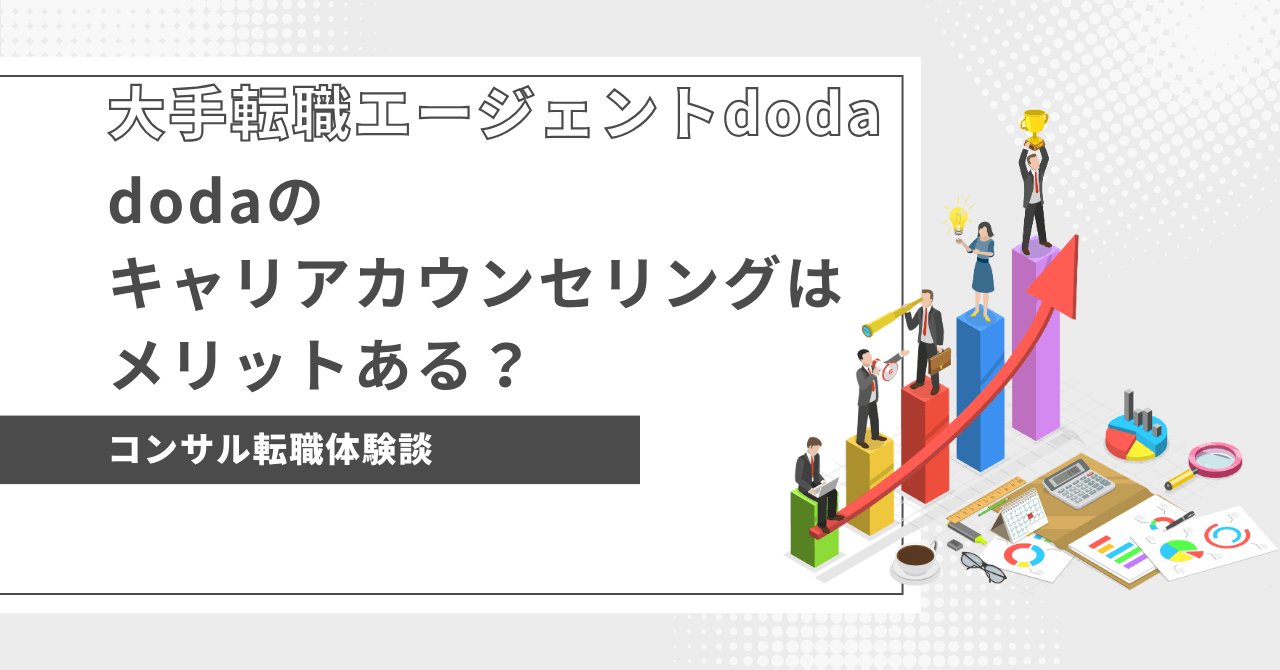
リクルートエージェント
\ 10万件以上の非公開求人! /
スキマ時間・休日の自己投資にオーディオブックサービスを活用
「休日を充実させる自己投資がしたい!」
「仕事で忙しいけど、スキマ時間に勉強をしたい!」
「たくさんビジネス書を読んで、活躍できるビジネスパーソンになりたい!」
あなたも同じ考えではありませんか?
そんな人にオススメできるのが、会員数250万人を突破したオーディオブック配信サービス【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】です。
【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】のおすすめポイント
- 年割プラン料金なら「月額833円」で15,000点以上のコンテンツを聴ける
- 14日間の「聴き放題お試し」が提供されている
- 厳選されたプロがナレーターとして本を朗読する
\ 14日間の「聴き放題お試し」あり /
本をたくさん買う人には、オーディオブックの方が安くなることもあります。
audiobook.jpの年割プラン料金なら「月額833円」で15,000点以上のコンテンツを聴くことができます。
14日間の「聴き放題お試し」が提供されているので、いちど気になる作品を聴いて継続利用するかお考えてみてください。
ちなみに、Amazonの子会社であるAudible Inc.が提供するオーディオブック・サービス【Audible】の料金は月額1,500円です。
外国語のコンテンツも多いので、英語学習をしたい方はAudibleをオススメしますが、多くの方には月額880円で「聴き放題月額プラン」が使えるaudiobook.jpをオススメします。
audiobook.jpには定額の「聴き放題プラン」以外にも「チケットプラン」があります。
「チケットプラン」は通常価格 ¥1,500で1枚のチケットを購入します。
購入したチケットと聴きたい作品を交換することができます。
チケット交換した作品は永久に何度も聴くことができるので、何度も聴き返したいオーディオブックコンテンツはチケット交換がオススメです。
ビジネス書は1冊2,000円以上することもあるので、「聴き放題プラン」「チケットプラン」のどちらでもコスパが良いですよね!
最近ではAIが音声を読み上げるオーディオブックサービスもありますが、厳選されたプロがナレーターとして本を朗読するaudiobook.jpが聴き心地は良いですね。
ぜひ、スキマ時間や休日の自己投資にオーディオブック配信サービス【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】を活用してみてください!
\ 14日間の「聴き放題お試し」あり /