新年度を迎えたとき、転職をしたとき等に直面する問題。
それは「仕事ができない上司」の元に配属されることです。
コンサルティングファームで働くと「上司は優秀な人ばかりなんだろう」と思われる方も多いかもしれません。
大半が優秀な上司なのは間違いないのですが・・・。
「仕事ができない上司」の最たる特徴である「自分のために部下を働かせる」ことの是非を考えたいと思います。
「仕事ができる」とは?
「仕事ができる」ということは「組織・チームの中で求められる役割を果たしている」ということ。
上司としていうのが管理職であるなら、そこで求められる役割は大きく2つです。
- 組織・チームとしての成果創出
- 部下の育成
時と場合によっては相反する上記2つを成し得えるのが、仕事のできる上司となります。
仕事ができない上司の特徴 3選
さて、「仕事のできない上司とはどんなビジネスパーソン?」という話に移ります。
まず最初に言いたいのが「自分のために部下を働かせる上司」が最もアウトだと考えています。
自分のために部下を働かせる
一番NGな上司像です。
自分の仕事がいっぱいいっぱいで単純作業を部下に振るだけの上司や、上司の上司(要は部長層や経営者層)から受けた無理難題を下の人間に振るだけの上司。
プレイングマネージャーとして役割に対してキャパオーバーとなって、単純に手が回らない状態です。
この状況になると、管理職として見なければならない仕事の全体感を捉えることができておらず、部下が優秀で自立していない場合は組織戦で敗北する可能性が高まります。
部下が優秀であれば勝手に成長して、勝手に良い判断をして指示以上の仕事してくれます。
ただ、その結果を判断する余裕が上司にないケースがあります。
「暖簾に腕押し」状態が長く続くと優秀な部下も離れていってしまうので注意が必要です。
残念ながら、部下が指示待ち人間だった場合も考えてみましょう。
成長意欲もなく、受けた指示をこなすことだけを考え、それ以上の価値を創出しようとしない。
そんな部下がいた場合、単純作業しか振れないうえに単純作業以上の成果が出てこないので火の車状態から抜け出せません。
自分の経験が常に正しいと思う
次のケースは「過去にプレイヤーとして活躍していた上司」に起こりやすいです。
「俺の経験上、こうするのが正しい!」と絶対的な正義のように振りかざすタイプです。
もちろん、状況によっては過去の知見が有効であることは疑いようがありません。
とは言っても、時代と共に戦い方は変えるべきものです。
常に時代の変化を捉えようとアンテナを張っていて、環境変化(社内外含め)に応じて仕事の進め方や指示内容を変える上司は付いていく価値があります。
その柔軟性と受容力から、部下の立場で学ぶことも多いでしょう。
社内の声しか気にしていない
最後に挙げる特徴は「社内の声しか」気にしない上司です。
組織戦であるビジネスにおいて、社内の声を気にするのは大変重要です。
無駄な苦労を避けたり、変な抵抗勢力をhuウニ方取ってしまうt生み出さないためにも。
でも、過剰に気にし過ぎてはいけません。
「上司の承認を如何に得るか・社内決裁を通しやすくするためにはどうしたらいいのか」ということを意識し過ぎた上司がいると、若手には良い影響を与えません。
本来であれば、ビジネスという営みは「顧客・市場に対して価値を提供し、その対価として金銭をいただくもの」です。
若手ビジネスパーソンが本来のビジネス思考を会得する前に、
社内調整思考に染まってしまっては大事な若手、そして組織の将来を潰してしまいます。
仕事ができない上司に対して、部下の立場で出来ることは?
これらの「仕事ができない上司」の元に配属されたしまった場合、部下の立場で出来ることは何があるのでしょうか?
対策としては、ブラック企業・ブラック職場の対策と重なる部分があります。
仕事ができない上司に対して「面従腹背」する
これは短期的な対症療法です。
表面上は従うように振る舞いつつ、内心では他の価値観をしっかりと取り入れておく。
そうして「仕事のできない上司」と一線を画して精神安定を図りながら、他の対策に向けた準備を水面下で進めるのです。
仕事ができない上司と離れる部署へ「人事異動」を希望する
可能であれば、人事異動の希望を人事部に出しましょう。
もちろん、理由などは前向きなものでなければいけません。
今回ご紹介したようなケースでの「仕事ができない上司」は、決して悪意のあるブラック上司ではありません。
「上司がダメだから」という理由が社内的に納得感のあるものになることはないでしょう。
定期的に人事異動をして人材をローテーションしている大企業であれば比較的叶いやすい対策だと思います。
仕事ができない上司がいなそうな会社に「転職」する
「転職」は人事異動が叶わない場合に残された、奥の手です。
自分に適さない環境に長く居続けることはキャリア上、望ましいことではありません。
転職エージェントなどに相談をして、自分が望むワークスタイルや社風をしっかりと固めてください。
そうでないと転職をしても同じ轍を踏む可能性もありますからね。
ちなみに、コンサルティング業界での働き方は一般的な事業会社と比べて、良くも悪くも変動的です。
数か月から年単位でプロジェクトが変わり、そのたびに上司や部下が変わることがほとんどです。
クライアントもプロジェクトごとに変わるため、多様なビジネスパーソンに会えることはコンサルティング業界の良さではありますね。
若手ビジネスパーソンの方は最終手段として、意外にホワイト化しているコンサルティング業界への転職を考えてみてください!!
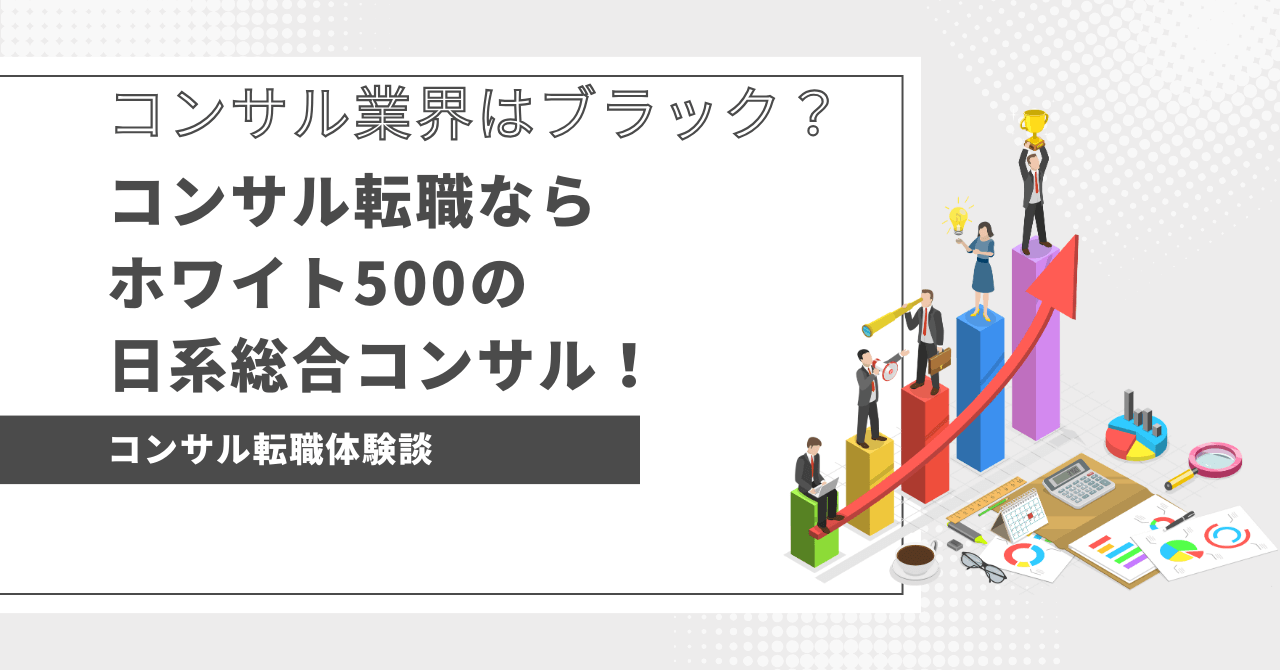
コンサル転職・自己研鑽に有効な資格は?
筆者「きつね」が実際に合格/勉強して、コンサルティング業務や自己研鑽に役立ったと思える資格を紹介します。
ぜひ、あなたのコンサル転職・自己研鑽の参考としてください!
コンサル転職前のオススメ資格/勉強記事
>>20代コンサルにおすすめ!年収を上げるIT資格【応用情報技術者試験】
>>【基本情報技術者試験】20代のコンサル転職で年収を上げるIT資格
>>【対策本あり】文系こそ取得すべき国家資格『ITパスポート』取得メリットを紹介
>>文系のIT未経験コンサルタントがプログラミングを学ぶべき3つの理由
>>【本も紹介】図解思考の技術・モデリング技術で概念を具体化【資格のUMTPもオススメ】
>>【合格体験談】マーケティング検定3級の体感難易度は簡単!勉強時間に参考書も紹介
>>【コンサル転職体験談】資格挑戦:マーケティング検定2級に挑戦|いきなり合格は無理?難易度は3級より確実に高い!
>>TOEIC400点台から800点台!コンサル実践の英語勉強法
>>【PMBOK】5つのプロセスと10の知識エリアはコンサル必修科目
>>新人コンサルにおすすめの資格「ビジネス会計検定3級」:簿記との違い・難易度・合格率をまとめた!
>>【オススメ】動画学習サービスSchoo(スクー)は評判がいい!
>>【無料あり】マーケティングが学べるオススメ動画学習サービス5選
コンサル転職に有利な資格合格に向けて
コンサル転職・転職後の自己研鑽として、資格取得を目指して勉強することはオススメです。
コンサルティング業界で働いていると、常に試験勉強をするように新しい知識をキャッチアップしないといけないので「勉強慣れ」をしておくとよいでしょう。
【STUDYing】中小企業診断士・応用情報技術者などをカバー
上記の資格をフルサポートしているわけではありませんが、スキマ時間で効率的に中小企業診断士などの資格合格を目指すなら、STUDYingも使うのがオススメです。
STUDYing中小企業診断士講座の2022年2次試験の最終合格実績が「業界No.1」
- 【合格実績 No.1!】
- ※1 2022年2次試験合格者数:167名
- 【合格者続々輩出中!】
- 2023年1次試験合格者数:510名
※1:同種の資格講座を提供している業者について、KIYOラーニング株式会社が2023年11月6日時点でHP上に記載されている合格者実績を調査した範囲での比較となります。
コンサルティング業界転職体験談まとめ
筆者「きつね」がコンサル転職を2回した体験談をまとめています!
30代で資産3,000万円を築いて、サイドFIREを実現したい。
そのためにコンサルティング業界で働いて年収を上げるため頑張っています。
転職をすることで年収を上げる、もしくは労働環境を改善させながら年収を維持することも可能です。
コンサル転職の成功は人それぞれですが、あなたのコンサル転職を成功させるため、ぜひ筆者「きつね」の体験談を参考にしてもらえたら嬉しいです!
コンサル転職体験談のオススメ記事
- 【オススメ】コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
- 【コンサル転職体験談】20代で年収1,000万!コンサルタントが年収を上げてきた思考法を伝授!
- 客先常駐=高級派遣?アクセンチュアやベイカレントなどの総合系コンサルが揶揄される理由
- 【コンサル転職体験談】転職候補はアクセンチュアソング、デロイト、PwC、インキュデータ
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職スケジュール公開!実際の転職ステップで要点を解説!
- 【3つの理由】「20代でコンサルタント就職・転職」が市場価値を高め、生涯年収を上げる!
- コンサル流「20代で市場価値を上げる休日の過ごし方」を紹介!暇な社会人こそ自己研鑽!
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職ならホワイト500の日系総合コンサルがオススメ!
- 【コンサル転職体験談】30代マネージャーが総合系コンサルファームを辞める理由は?
- 【コンサル転職体験談】面接でした逆質問を紹介!志望度を間接的に伝える重要要素
- 【コンサル転職体験談】コンサル就職・転職前に必読!ケース面接の対策本3選!
- 【コンサル転職体験談】職務経歴書|書き方のコツ!書類選考は全社通過!
- 【高年収】コンサルタントの種類?コンサルタントの職位・相場年収って?
- 【コンサル転職】転職活動おすすめの「企業の口コミサイト」を紹介!
- 【未経験30代のコンサル転職】コンサル転職に失敗する人の特徴3選
コンサル転職を成功させるため転職エージェントを複数利用
筆者「きつね」が内定までサポートしてもらった転職エージェントはアクシスコンサルティングでした。
>>コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
もちろんオススメですが、コンサルティング業界・ポストコンサル転職を目指すなら、転職エージェントは複数登録しておいた方が良いでしょう。
1つの転職エージェントから得られる求人情報は偏ってしまいますし、キャリア相談におけるセカンドオピニオンを得られることが複数の転職エージェントを活用するメリットです。
以下が筆者「きつね」も利用した転職エージェントです!
最近はコーチングにお金を払って転職をサポートするエージェントもいますよね。
ご紹介しているサービスはあくまで転職エージェントなので、無料で利用可能です!
転職活動の初期は複数の転職エージェントから求人情報をもらいつつ、担当さんとの相性も見極めましょう!
アクシスコンサルティング
アクシスコンサルティングは、コンサルティング業界の転職を目指すなら登録必須です。
コンサルティングファームの採用担当者と密に連携をしており、あなたの希望にあった非公開求人を紹介してくれます。
長年コンサル業界の転職を支援しているので、ケース面接対策もバッチリです。
\ コンサルティング業界に特化した転職面接サポート!! /
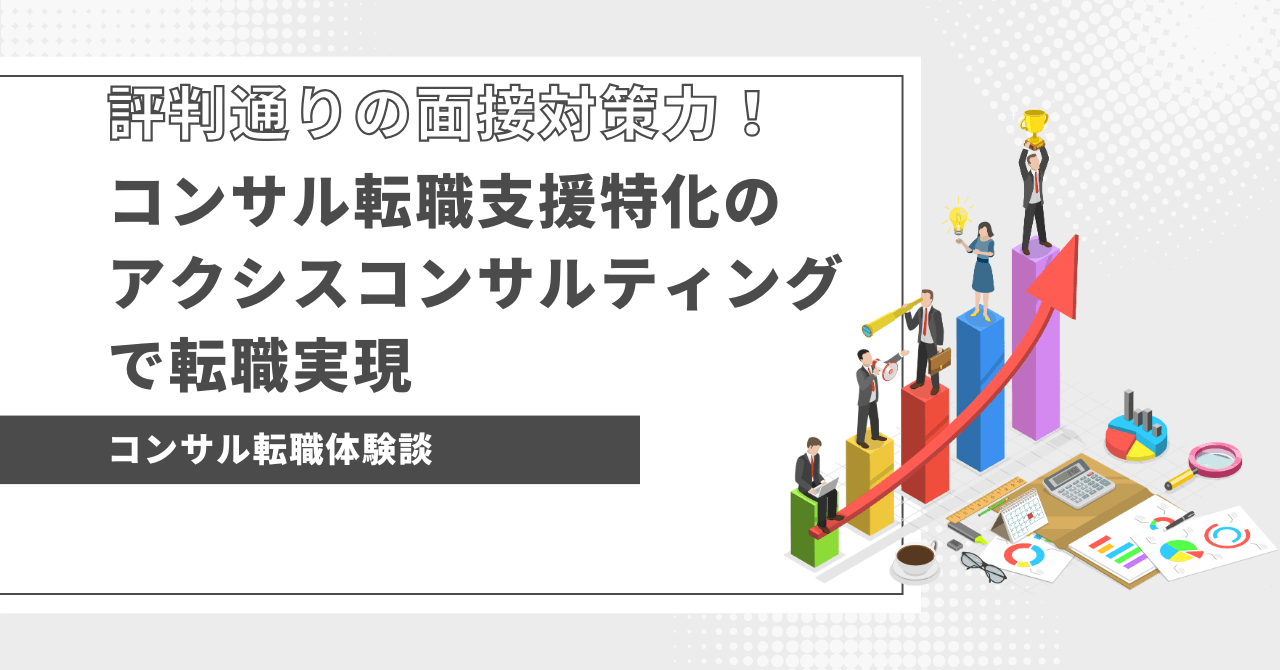
コトラ
ハイクラス転職に強く、特に金融業界の転職に強いのが「コトラ」です。
コンサル業界の転職も支援をしてくれます。
CFOや金融業界を専門としたコンサルを目指すなら登録必須だと思います。
コンサルタントとして金融業界の支援経験がある方も登録をしておくと良いでしょう。
\ ハイクラス転職に強い! /

マスメディアン
もし、あなたがコンサルティング業界にこだわらず、広告業界やマーケティング職の転職を考えているなら「マスメディアン」の登録がオススメです。
「宣伝会議」という広告やマーケティングに関する出版社が運営する転職エージェントで、出版社としてのコネクションを活かした転職情報が魅力的です。
多くの事業会社におけるマーケティング職や広告・クリエイティブ職の求人情報が掲載されています。
大手転職エージェント・転職サイトでは見つけにくい専門的な職種の情報が掲載されていますし、マスメディアンの担当者も職種特化で知識も豊富。
マーケティング職にキャリアチェンジしたい場合、マーケティング職としてキャリアアップを目指したい場合も力になってくれるはずです。
\ 広告・マーケティングの求人情報・転職なら! /
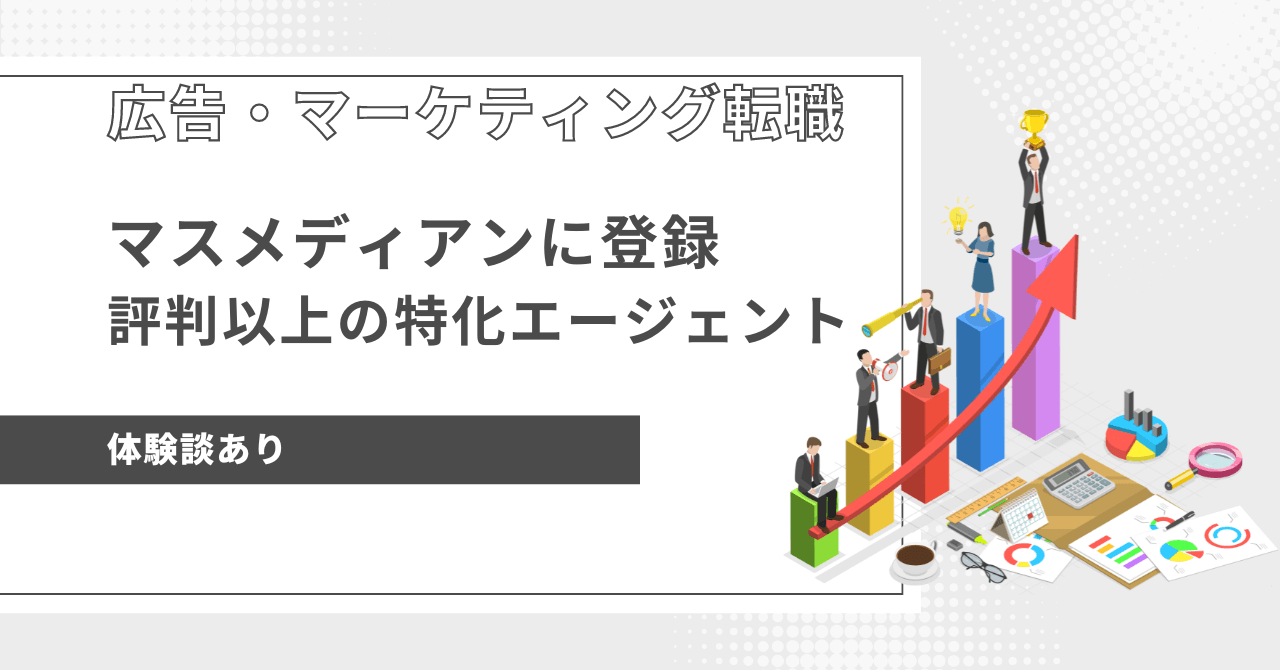
DODA
大手転職エージェントdodaは約12万件ある求人情報から、あなた専任のキャリアアドバイザーが希望に合致した求人情報をリストアップしてくれます。
ワークライフバランスを見直したり、業種・職種を広く検討したい場合はdodaがオススメです。
\ 大手ならでは!!安心のサポート力!! /
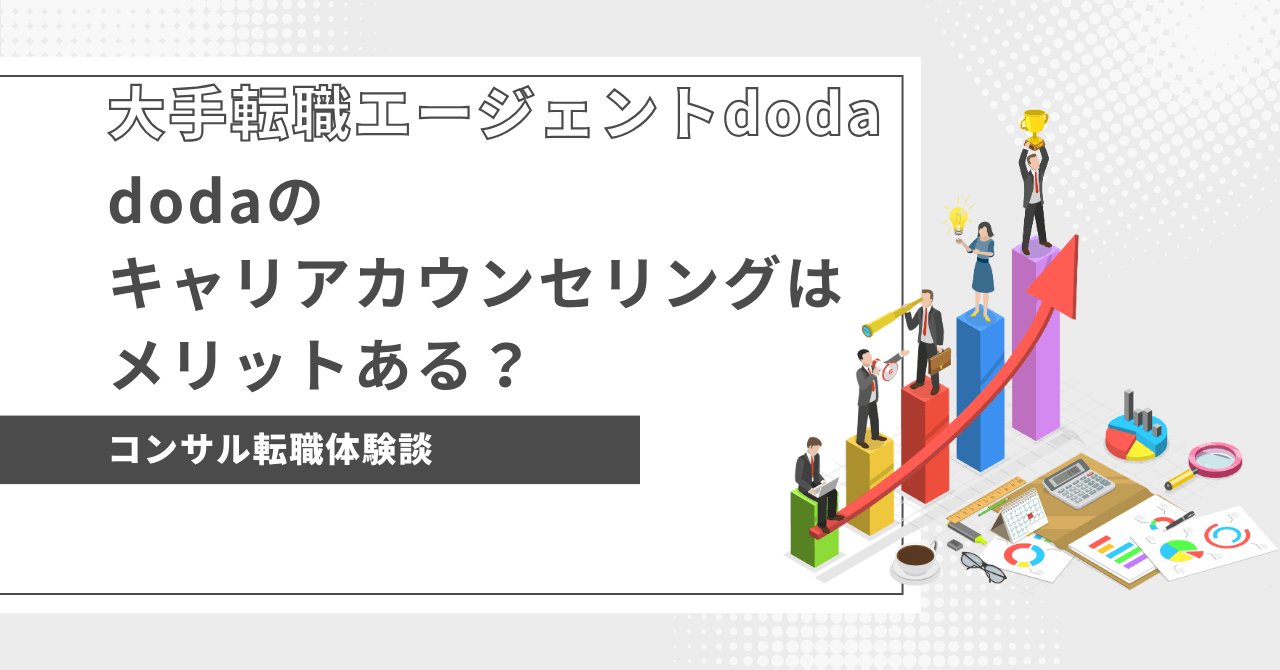



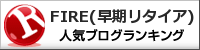

コメント