「このまま今の会社にいていいのか?」
本のタイトルと同じ悩みを抱くビジネスパーソンは多いでしょう。
30歳になる頃には、多くの方が一度くらいは転職について考えた経験があるのではないでしょうか?
「転職は悪いのか。裏切りなのか。」
「現在の経験やスキルで転職なんて無理じゃないか。」
「転職に失敗しないために、信頼できるエージェントと出会いたい。」
そんな悩み・不安を抱くあなたに。
『マンガ 転職の思考法』を読んでもらいたい。
市場価値を高め、あなたが活躍できる場所を見つける転職の思考法を一緒に学びましょう!
マンガのもとになった20万部越えのベストセラー書籍も読むことで、より深く「転職の思考法」を理解できます!
『転職の思考法』オススメ読者
30歳を目前にして、これからのキャリアを考えはじめた。
でも、新卒からお世話になった現在の会社を離れることは、仲間の負担が増えそうで、申し訳ない気もする。
仲間を大切に思う優しいあなたにこそ、読んでほしいと思います。
転職というのは、決して裏切りではないのです。
自分は普通で取柄もない。
こんな風に思う自信がない、あなたにも読んでほしい。
あなたが輝ける、活躍できる場所を探すために転職をするのです。
『マンガ 転職の思考法』オススメ読者
- 「このままで良いのか」と漠然とした不安を持つ30歳前後の若手ビジネスパーソン
- 市場価値と社内評価のギャップを知って、いつでも「転職できる」状態に自分を保ちたい方
- 転職準備を始めたけど、信頼できる転職エージェントが分からず、なかなか意思決定ができない方
ここで質問です。
「出世をして年収を上げたい・キャリアアップをしたい!」
「仕事のできるビジネスパーソンになって、周囲の評判をひっくり返したい!」
「ビジネス力を高めて、収入上げて、投資で不労所得を得たい!」
筆者「きつね」と同じく、あなたもそう考えたことはありませんか?
書籍から知識を得ることであなたの目的達成に近づきます。
ですが、本を購入すると費用もかかりますし、保管場所も負担になりますよね・・・。
そんなお悩みを持つあなたにオススメできるサービスがあります。
200万冊以上の本が読み放題になるAmazon(アマゾン)の電子書籍読み放題サービスです。
「あなたの年収を上げる・サイドFIRE実現を助ける・不労所得をゲットする」本が見つかります!
電子書籍よりも紙の本が好きという方もいるかもしれません。
ですが、初めてご利用の方は30日間の無料体験が可能です。
使いにくければ30日経過する前に解約をしましょう。
無料期間終了後は月額980円で使えます。
「1か月だと読み切れないし、1年だと長すぎるかも・・・。」
もちろん、いつでも解約できます。
ですので、3か月くらい集中して本を読み漁って解約するという使い方でも良いかもしれません。
>>Amazon Kindle Unlimitedを無料で試してみる\ 初回利用は30日間無料!200万冊以上の本が読み放題 /
『転職の思考法』概要とあらすじ
気軽にマンガを読みながら、主人公の「奈美」と共に思考の転職法」を学ぶことができる本書。
『マンガ 転職の思考法』は、「あなたが輝ける会社を見つけるための考え方」を教えてくれます。
転職という意思決定は大きな決断です。
これまでの慣れ親しんだ同僚やお客様とも離れ、新しい人間関係や仕事内容に慣れないといけません。
そういった不安を乗り越える価値を見つけるための考え方を知っていれば、きっとワクワク感に変わるはず。
あなたが「自分で、自分のキャリアを築いていく会社を見つけ、同時に何かを手放すことを決める」思考法を教えてくれる本を、読むことで見つかるはずです。
著者(北野 唯我)
本書を著したのは「 北野 唯我(きたの ゆいが)」さんです。
北野さんは博報堂の経営企画局・経理財務局で勤務したのち、外資系戦略コンサルティングファームのBCG(ボストンコンサルティンググループ)に転職をされています。
そしてワンキャリアという就活サイトを運営する企業に参画し、取締役を務めています。
事業会社、コンサル、経営層と様々な立場で多くのビジネスパーソンに出会ってきた北野さん。
経験の多さからか、「個々人が望ましい生き方を描き、実現できること」を願っているように感じました。
価値観は多様であり、絶対の正解はない。
その中で、世界・社会に貢献しつつ、自分自身の生き方を充実させられる選択肢を、自分で見つけ出してほしい。
そんな風に考えていらっしゃると思います。
- 1987年、兵庫県生まれ
- 神戸大学経営学部卒
- 博報堂⇒ボストンコンサルティンググループ⇒ワンキャリアに参画
- 子会社の代表取締役などを経て、現在、ワンキャリア取締役
- 著書
- 『このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思ったら読む転職の思考法』
- 『OPENNESS 職場の 「空気」が結果を決める』
- 『天才を殺す凡人』
- 『分断を生むエジソン』
- 『これからの生き方。』
あらすじ要約と章構成
個人の価値観に基づいてキャリアを描いていくことは、本書の主人公である「奈美」にとっても勇気のいる判断でした。
奈美は30歳を目前にしながらも、自分の希望していた海外に関する仕事とは程遠い、総務部で備品管理などの仕事をしていました。
22歳に当時の彼氏からプロポーズをされるも、仕事(夢)を優先した結果、プロポーズを断ってしまいます。
当時は、希望の会社に就職して、夢だった海外を飛び回る仕事ができると夢を見て・・・。
でも、現実は甘くありません。
これといったチャンスも実績もスキルもなく、気付けば30歳手前に。
プライベートでは周囲の友人が結婚や出産、夢の仕事で活躍する姿に触れ、劣等感や焦りが。
なんとか充実させたい・・・。
そんなときに自分の勤める会社が外資系企業に買収されることに。
人事担当者としてやってきたのが子供の頃に「近所のお兄ちゃん」と親しんでいた「青野トオル」。
外資系企業に買収されたことをチャンスと思い、海外事業部への異動を面談で伝えるも「大学時代にTOEIC650点」という結果から一蹴される。
「もう自分にはどうしようもないのか」
希望部署への異動を諦めかけていたときに「青野トオル」から『転職の思考法』を学びます。
「自分には武器がないから転職は無理だ。」
「転職は裏切りなんじゃないか?」
「転職エージェントを信じて良いのか。」
「会社に残るか、転職するか。最後は何を基準に判断すれば。」
誰もが抱く悩みや不安を乗り越えて、奈美は自分の納得する「生き方」を見つける。
そんなお話になっています。
以下の目次に沿って、奈美は少しずつ少しずつ、強くなっていく姿に勇気を貰えます。
- はじめに 「情報」に惑わされないための「思考法」
- 主な登場人物
- プロローグ 私には「武器」がない
- 原則1 転職は悪ではない
- 原則2 市場価値と社内評価は一致しなくていい
- 原則3 9割の人は、S級人材ではない
- 黒岩のコトバ 転職に必要なのは、情報ではなく思考法である
- 第1章 私の「市場価値」
- あなたのマーケットバリュー(市場価値)はいくら?
- マーケットバリューを高める3つの方法
- 「伸びている業界で働いた経験」には価値がある
- 「やりたいこと」はなくてもいい
- 黒岩のコトバ 意味のある意思決定は必ず、何かを捨てることを伴う
- 第2章 転職は「裏切り」?
- 大事なのは転職よりも「転職できる」というカード
- 自分自身の棚卸しのやり方① 過去やってきたことを書き出す
- 自分自身の棚卸しのやり方② 再現性を見つける
- 黒岩のコトバ 一生食えるかどうかは「上司を見て生きるか」「マーケットを見て生きるか」で決まる
- 第3章 いいエージェント、ダメなエージェント
- 転職するための5つのチャネル
- 転職エージェントのビジネスモデルを知る
- いいエージェント、ダメなエージェントを見分ける方法
- 黒岩のコトバ いつでも転職できるような人間がそれでも転職しない会社。それが最強だ
- 第4章 もう、後悔したくない
- 会社選びの3つの基準
- 迷ったときは「未来のマーケットバリュー」を取る
- もし今の会社から引き留めにあったら
- 退職するときに気をつけたい3つのこと
- 転職で活躍できる人、活躍できない人の違い
- 黒岩のコトバ 才能は不平等だが、ポジショニングは平等だ
- エピローグ 私たちは「居場所」を選べる
- おわりに
書籍詳細
それでは各章の内容を概観していきましょう。
プロローグ 私には「武器」がない
自分の希望通りの部署で働くことも、(他人から見たら)希望部署への異動を掴むための努力も認められない主人公の奈美。
トオルから言われたのは、「自分自身の市場価値(マーケットバリュー)を知らない」という一言。
9割の人間は「普通の会社員」です。
それでも、自分のこれまでの経験を活かす場があること、社内の評価と社外の評価は一致しているとは限らないということが、まずは「転職の思考法」の第一歩だと教わるのです。
その前提に立ち、ますは自分の市場価値を把握する方法を次の章では学びます。
第1章 私の「市場価値」
では、社外評価=市場価値(マーケットバリュー)とはどんな要素で決まるのでしょうか?
市場価値(マーケットバリュー)を構成する3要素
- 技術資産:職種に紐づく「専門性」とリーダーやマネジメントなどの「経験」に分けられる。
- 人的資産:「人脈」のことであり、年齢を経るほどに大きな影響を持つ。
- 業界の生産性:業界自体の利益率が高いかの指標であり、同じ仕事でも業界の粗利に比例して給料は変わる。
この3要素について、現在の自分がどれほどの資産を保有しているのか測れる「9の質問」が本書で書かれています。
ぜひ本書を手にして、あなたの市場価値を把握してください。
そのうえで、自分は「to do型」なのか「being型」なのか考えてみてください。。
「to do型」は大きな目標や野望を抱き、「○○を実現する」というコト思考の人間。
一方の「being型」は、プライベート充実・周囲に感謝される等の「こうありたい」という状態思考の人間。
世の中には大きくこの2つがいるらしいのですが、大半の人間は「being型」だそうです。
「being型」の人間であれば、市場価値を高めることで「ありたい姿」に近づける可能性が高まります。
「to do型」であれば、自分の資産を活かして、「どうしたら実現できるか」を考えると良いでしょう。
第2章 転職は「裏切り」?
転職を含めて新しい道を歩もうとすると、必ずと言っていい程に壁が現れます。
それは「引き留める周囲の人間」と「勝手に湧き出る転職に対する罪悪感」です。
いずれも、考える必要はないのですが割り切れる人間の方が少ないでしょう。
コンサルタントという仕事をしているとプロジェクトごとにチームメンバーやクライアント企業が変わることが普通なので、転職に近しい経験を普通にしていますし、業界柄、転職して普通なので、個人的には全く抵抗感はないんですけどね。笑
モヤモヤが浮かんでくる場合、まずは「キャリアの棚卸」をすることだけも充分だと本書では説いています。
転職は絶対的な答えではないですからね。
周囲の人間を大切にしたいという感情も、「なんだか申し訳ないな」と思うのも、あなたの感情です。
無理に隠さず押し込まず、まずは本書に書かれているアドバイスを元にして「キャリアの棚卸」の実施をオススメします。
自分でも知らない「あなたの市場価値」を見つけられるかもしれませんよ!
第3章 いいエージェント、ダメなエージェント
第3章で奈美は遂に、転職エージェントと面談を行い、転職活動を始めます。
これまでトオルから学んだ「転職の思考法」のおかげか、転職活動で面接した企業からは高評価とのこと。
しかし、トオルは奈美に疑問を投げかけます。
「いい転職エージェントなのか」
転職エージェントのビジネスモデルはいわゆる「紹介業・マッチング業」です。
人を欲しがる企業に転職希望者を紹介して、就職が決まれば成功報酬をもらうというビジネスモデル。
本当にあなたのことを考えてくれているのか、それとも単に早く転職を決めてほしいだけなのか。
いいエージェント・ダメなエージェントを見極める5箇条が本書では紹介されているので、あなたが転職エージェントと面談をするときは、ぜひ5箇条に沿った質問を投げかけてみてください。
転職希望者のエージェント選別眼が鍛えられることで、転職市場がもっと良くなるはずです!
第4章 もう、後悔したくない
奈美はエージェントに流されず「自分にとって」良い会社を選ぶ基準をトオルから教わり、自分の歩む道を決めるのです。
良い会社を選ぶ3つの基準とは。
会社選び3つの基準
- マーケットバリュー
- 働きやすさ
- 活躍の可能性
当然な観点ですが、働き続けて年収が上がるうちに「社内評価」を重視してしまい、いつしか忘れてしまう基準たちです。
それでも悩むときは「未来のマーケットバリューをとる」ことを本書では推奨しています。
一時的に年収が下がったとしても、長い目でみればマーケットバリューと給料は一致するもの。
自分で人材市場での市場価値を高めていき、年収も上げていけば良いのです。
むしろ給料を重視すると、「社内評価」に視線が向いていた過去の自分と何も変わらないですもんね。
エピローグ 私たちは「居場所」を選べる
奈美は自分の選んだ道で、自分の夢を叶えます。
何年後かに後悔しないために、奈美のように自分の活躍できる可能性を信じて、自分でキャリアを切り拓いていきたいと強く思いました。
マンガで『転職の思考法』を学び会社に依存しない働き方を!
「転職」というのは人生における一大事件。
22歳で働き始めて、65歳まで働くとしたら約40年のキャリアプランを最初から綺麗に描ける人間はいません。
紆余曲折ありながらも、その都度で自分は納得できる選択肢を選ぶ。
いや「常に選べる状態にあるにはどうしたらいいか?」が「このまま今の会社にいていいのか?」の前に考えることだな、と 『マンガ 転職の思考法』 を読んで感じました。
「このまま今の会社にいていいのか?」 とあなたも思うなら、ぜひご一読ください。
ここまで読んでくださり、本当にありがとうございます。
最後に、1点お伝えしたいことがあります。
実は「きつね」の働くコンサルティング業界というのは、本書で語られる「転職の思考法」に近しいことを考える機会が多いのです。
基本的にプロジェクト形式で働くコンサルタント。
毎回クライアントやチームメンバーが異なることもあります。
さらにアサイン面談という「プロジェクトチームとして率いるコンサルタントを選抜する面談」を行います。
「アサイン」とは「割り当てる」という意味の英単語で、コンサルタントをプロジェクトに割り当てるという意味で使われる業界用語です。
つまり、ほとんど転職と同じ活動をコンサルタントは数か月から数年に1回は行うのです。
自然と「転職の思考法」に近い「アサインの思考法」を会得するコンサルタント。
「転職の思考法」を実践する機会が多々あり、市場価値も上がりやすいコンサルティング業界への挑戦は、あなたの人生を切り拓く一手になるかもしれません。
激務というイメージがあるかもしれませんが、最近ではコンサルティング業界もホワイト化しています。
第4章の「会社選び3つの基準」である「マーケットバリュー・働きやすさ・活躍の可能性に照らし合わせてみて、一度考えてみてください!
今回、筆者「きつね」が実際に読んだオススメの本をご紹介させていただきました。
他にもコンサルタントとして多くの本を読んだなかで、「これは必読!」と感じた本を厳選した紹介記事も書いています!
ぜひよろしくお願いいたします!
スキマ時間・休日の自己投資にオーディオブックサービスを活用
「休日を充実させる自己投資がしたい!」
「仕事で忙しいけど、スキマ時間に勉強をしたい!」
「たくさんビジネス書を読んで、活躍できるビジネスパーソンになりたい!」
あなたも同じ考えではありませんか?
そんな人にオススメできるのが、会員数250万人を突破したオーディオブック配信サービス【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】です。
【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】のおすすめポイント
- 年割プラン料金なら「月額833円」で15,000点以上のコンテンツを聴ける
- 14日間の「聴き放題お試し」が提供されている
- 厳選されたプロがナレーターとして本を朗読する
\ 14日間の「聴き放題お試し」あり /
本をたくさん買う人には、オーディオブックの方が安くなることもあります。
audiobook.jpの年割プラン料金なら「月額833円」で15,000点以上のコンテンツを聴くことができます。
14日間の「聴き放題お試し」が提供されているので、いちど気になる作品を聴いて継続利用するかお考えてみてください。
ちなみに、Amazonの子会社であるAudible Inc.が提供するオーディオブック・サービス【Audible】の料金は月額1,500円です。
外国語のコンテンツも多いので、英語学習をしたい方はAudibleをオススメします。
しかし、多くの方には月額880円で「聴き放題月額プラン」が使えるaudiobook.jpをオススメします。
audiobook.jpには定額の「聴き放題プラン」以外にも「チケットプラン」があります。
「チケットプラン」は通常価格 ¥1,500で1枚のチケットを購入します。
購入したチケットと聴きたい作品を交換することができます。
チケット交換した作品は永久に何度も聴くことができます。
何度も聴き返したいオーディオブックコンテンツはチケット交換がオススメです。
ビジネス書は1冊2,000円以上することもあるので、「聴き放題プラン」「チケットプラン」のどちらでもコスパが良いですよね!
最近ではAIが音声を読み上げるオーディオブックサービスもありますよね。
でも、厳選されたプロがナレーターとして本を朗読するaudiobook.jpが聴き心地は良いです。
ぜひ、スキマ時間や休日の自己投資にオーディオブック配信サービス【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】を活用してみてください!
\ 14日間の「聴き放題お試し」あり /
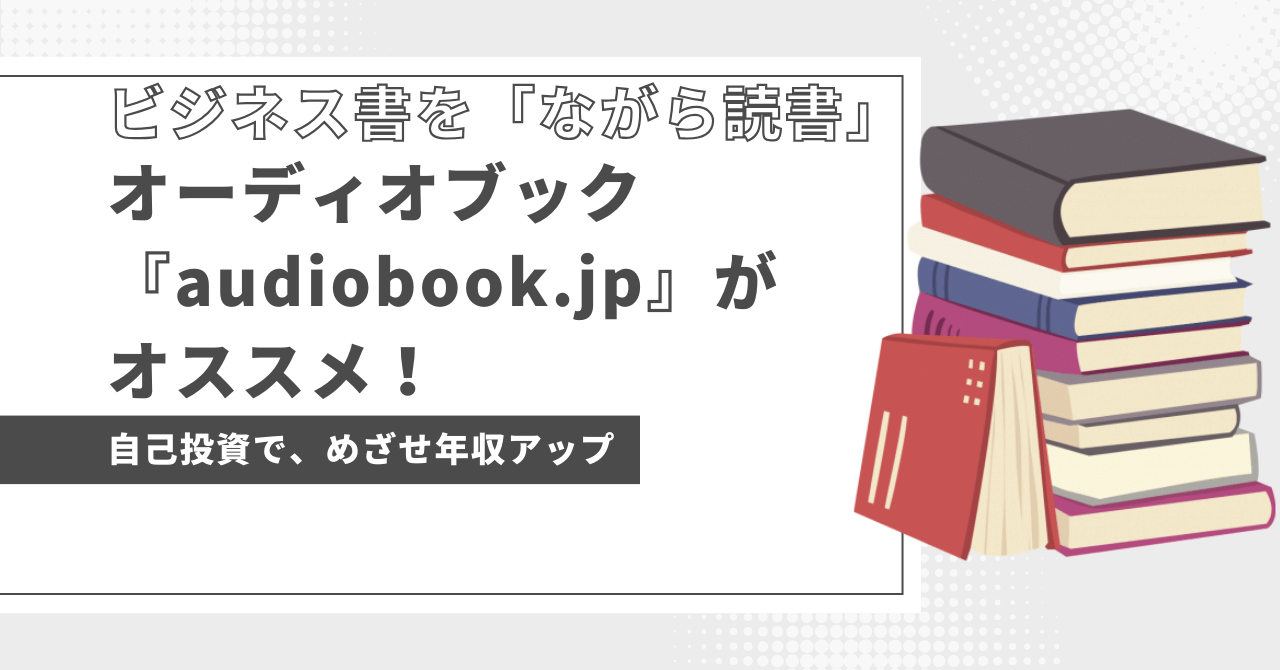
コンサル転職・自己研鑽に有効な資格は?
筆者「きつね」が実際に合格/勉強して、コンサルティング業務や自己研鑽に役立ったと思える資格を紹介します。
ぜひ、あなたのコンサル転職・自己研鑽の参考としてください!
コンサル転職前のオススメ資格/勉強記事
>>20代コンサルにおすすめ!年収を上げるIT資格【応用情報技術者試験】
>>【基本情報技術者試験】20代のコンサル転職で年収を上げるIT資格
>>【対策本あり】文系こそ取得すべき国家資格『ITパスポート』取得メリットを紹介
>>文系のIT未経験コンサルタントがプログラミングを学ぶべき3つの理由
>>【本も紹介】図解思考の技術・モデリング技術で概念を具体化【資格のUMTPもオススメ】
>>【合格体験談】マーケティング検定3級の体感難易度は簡単!勉強時間に参考書も紹介
>>【コンサル転職体験談】資格挑戦:マーケティング検定2級に挑戦|いきなり合格は無理?難易度は3級より確実に高い!
>>TOEIC400点台から800点台!コンサル実践の英語勉強法
>>【PMBOK】5つのプロセスと10の知識エリアはコンサル必修科目
>>新人コンサルにおすすめの資格「ビジネス会計検定3級」:簿記との違い・難易度・合格率をまとめた!
>>【オススメ】動画学習サービスSchoo(スクー)は評判がいい!
>>【無料あり】マーケティングが学べるオススメ動画学習サービス5選
コンサル転職に有利な資格合格に向けて
コンサル転職・転職後の自己研鑽として、資格取得を目指して勉強することはオススメです。
コンサルティング業界で働いていると、常に試験勉強をするように新しい知識をキャッチアップしないといけないので「勉強慣れ」をしておくとよいでしょう。
【STUDYing】中小企業診断士・応用情報技術者などをカバー
上記の資格をフルサポートしているわけではありませんが、スキマ時間で効率的に中小企業診断士などの資格合格を目指すなら、STUDYingも使うのがオススメです。
STUDYing中小企業診断士講座の2022年2次試験の最終合格実績が「業界No.1」
- 【合格実績 No.1!】
- ※1 2022年2次試験合格者数:167名
- 【合格者続々輩出中!】
- 2023年1次試験合格者数:510名
※1:同種の資格講座を提供している業者について、KIYOラーニング株式会社が2023年11月6日時点でHP上に記載されている合格者実績を調査した範囲での比較となります。
コンサルティング業界転職体験談まとめ
筆者「きつね」がコンサル転職を2回した体験談をまとめています!
30代で資産3,000万円を築いて、サイドFIREを実現したい。
そのためにコンサルティング業界で働いて年収を上げるため頑張っています。
転職をすることで年収を上げる、もしくは労働環境を改善させながら年収を維持することも可能です。
コンサル転職の成功は人それぞれですが、あなたのコンサル転職を成功させるため、ぜひ筆者「きつね」の体験談を参考にしてもらえたら嬉しいです!
コンサル転職体験談のオススメ記事
- 【オススメ】コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
- 【コンサル転職体験談】20代で年収1,000万!コンサルタントが年収を上げてきた思考法を伝授!
- 客先常駐=高級派遣?アクセンチュアやベイカレントなどの総合系コンサルが揶揄される理由
- 【コンサル転職体験談】転職候補はアクセンチュアソング、デロイト、PwC、インキュデータ
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職スケジュール公開!実際の転職ステップで要点を解説!
- 【3つの理由】「20代でコンサルタント就職・転職」が市場価値を高め、生涯年収を上げる!
- コンサル流「20代で市場価値を上げる休日の過ごし方」を紹介!暇な社会人こそ自己研鑽!
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職ならホワイト500の日系総合コンサルがオススメ!
- 【コンサル転職体験談】30代マネージャーが総合系コンサルファームを辞める理由は?
- 【コンサル転職体験談】面接でした逆質問を紹介!志望度を間接的に伝える重要要素
- 【コンサル転職体験談】コンサル就職・転職前に必読!ケース面接の対策本3選!
- 【コンサル転職体験談】職務経歴書|書き方のコツ!書類選考は全社通過!
- 【高年収】コンサルタントの種類?コンサルタントの職位・相場年収って?
- 【コンサル転職】転職活動おすすめの「企業の口コミサイト」を紹介!
- 【未経験30代のコンサル転職】コンサル転職に失敗する人の特徴3選
コンサル転職を成功させるため転職エージェントを複数利用
筆者「きつね」が内定までサポートしてもらった転職エージェントはアクシスコンサルティングでした。
>>コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
もちろんオススメですが、コンサルティング業界・ポストコンサル転職を目指すなら、転職エージェントは複数登録しておいた方が良いでしょう。
1つの転職エージェントから得られる求人情報は偏ってしまいますし、キャリア相談におけるセカンドオピニオンを得られることが複数の転職エージェントを活用するメリットです。
以下が筆者「きつね」も利用した転職エージェントです!
最近はコーチングにお金を払って転職をサポートするエージェントもいますよね。
ご紹介しているサービスはあくまで転職エージェントなので、無料で利用可能です!
転職活動の初期は複数の転職エージェントから求人情報をもらいつつ、担当さんとの相性も見極めましょう!
アクシスコンサルティング
アクシスコンサルティングは、コンサルティング業界の転職を目指すなら登録必須です。
コンサルティングファームの採用担当者と密に連携をしており、あなたの希望にあった非公開求人を紹介してくれます。
長年コンサル業界の転職を支援しているので、ケース面接対策もバッチリです。
\ コンサルティング業界に特化した転職面接サポート!! /
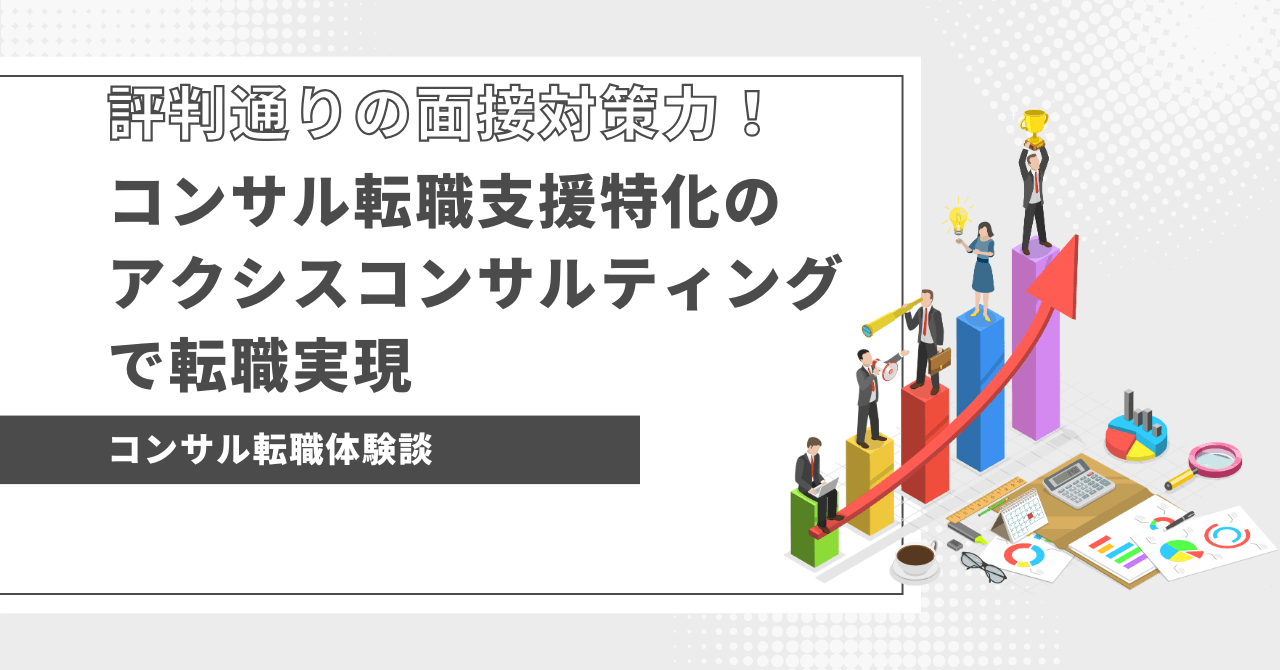
コトラ
ハイクラス転職に強く、特に金融業界の転職に強いのが「コトラ」です。
コンサル業界の転職も支援をしてくれます。
CFOや金融業界を専門としたコンサルを目指すなら登録必須だと思います。
コンサルタントとして金融業界の支援経験がある方も登録をしておくと良いでしょう。
\ ハイクラス転職に強い! /

マスメディアン
もし、あなたがコンサルティング業界にこだわらず、広告業界やマーケティング職の転職を考えているなら「マスメディアン」の登録がオススメです。
「宣伝会議」という広告やマーケティングに関する出版社が運営する転職エージェントで、出版社としてのコネクションを活かした転職情報が魅力的です。
多くの事業会社におけるマーケティング職や広告・クリエイティブ職の求人情報が掲載されています。
大手転職エージェント・転職サイトでは見つけにくい専門的な職種の情報が掲載されていますし、マスメディアンの担当者も職種特化で知識も豊富。
マーケティング職にキャリアチェンジしたい場合、マーケティング職としてキャリアアップを目指したい場合も力になってくれるはずです。
\ 広告・マーケティングの求人情報・転職なら! /
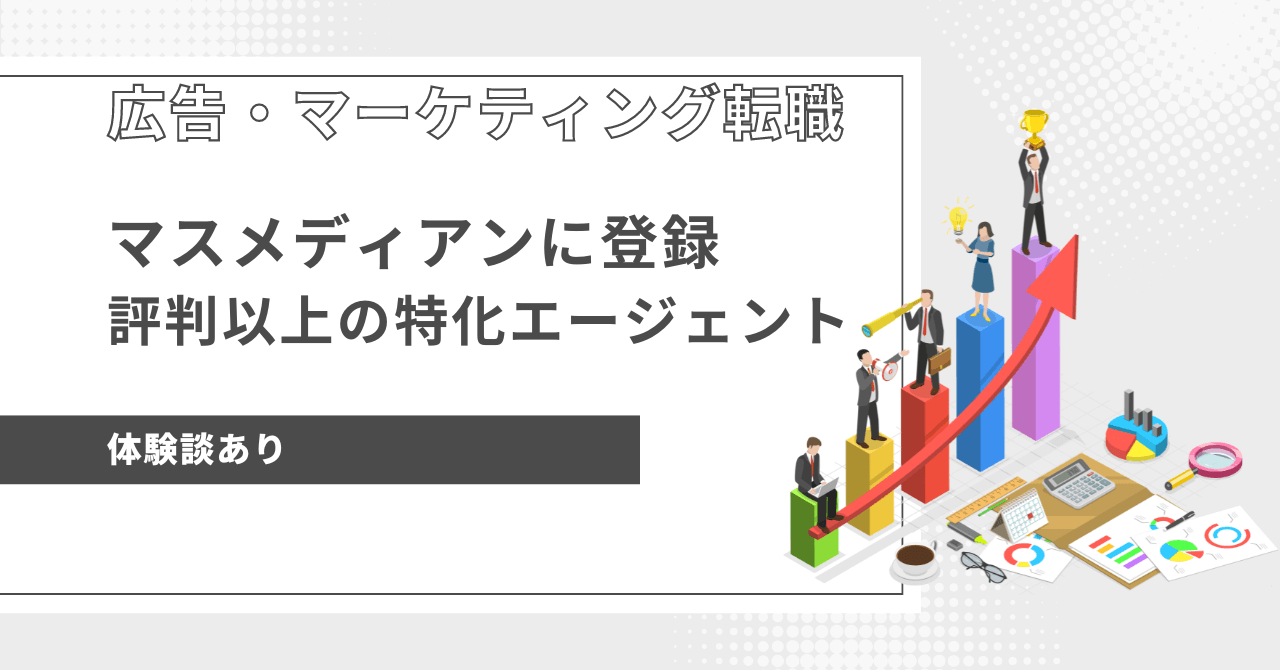
DODA
大手転職エージェントdodaは約12万件ある求人情報から、あなた専任のキャリアアドバイザーが希望に合致した求人情報をリストアップしてくれます。
ワークライフバランスを見直したり、業種・職種を広く検討したい場合はdodaがオススメです。
\ 大手ならでは!!安心のサポート力!! /
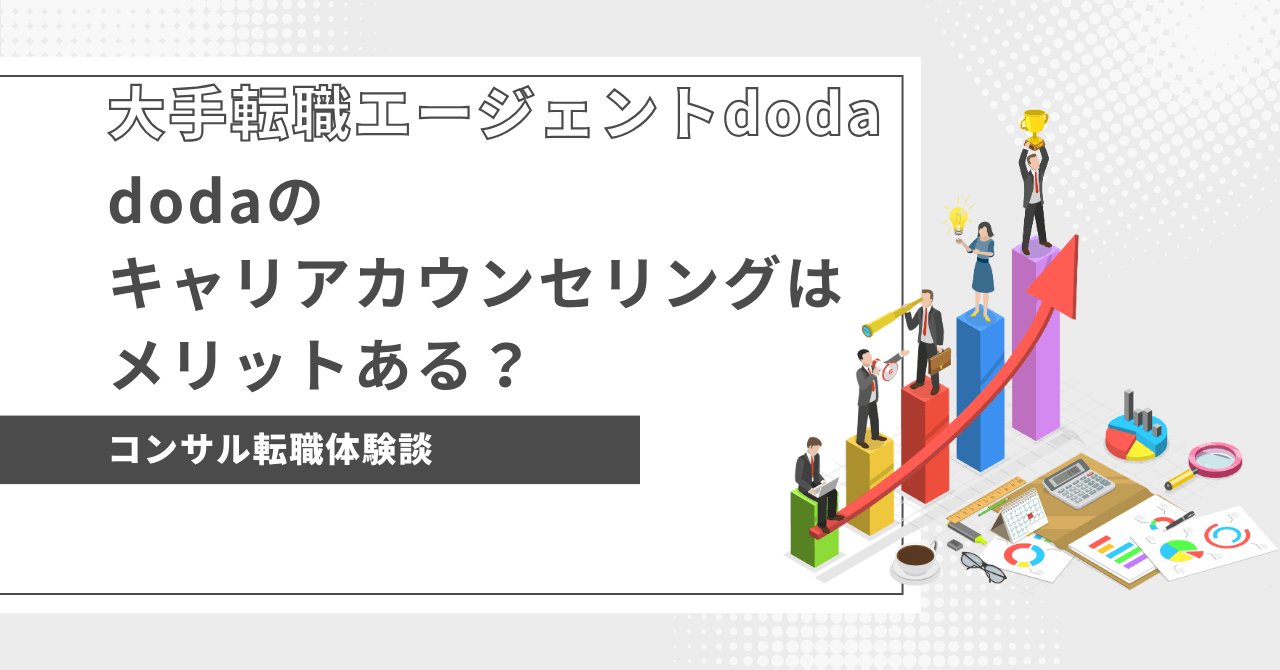
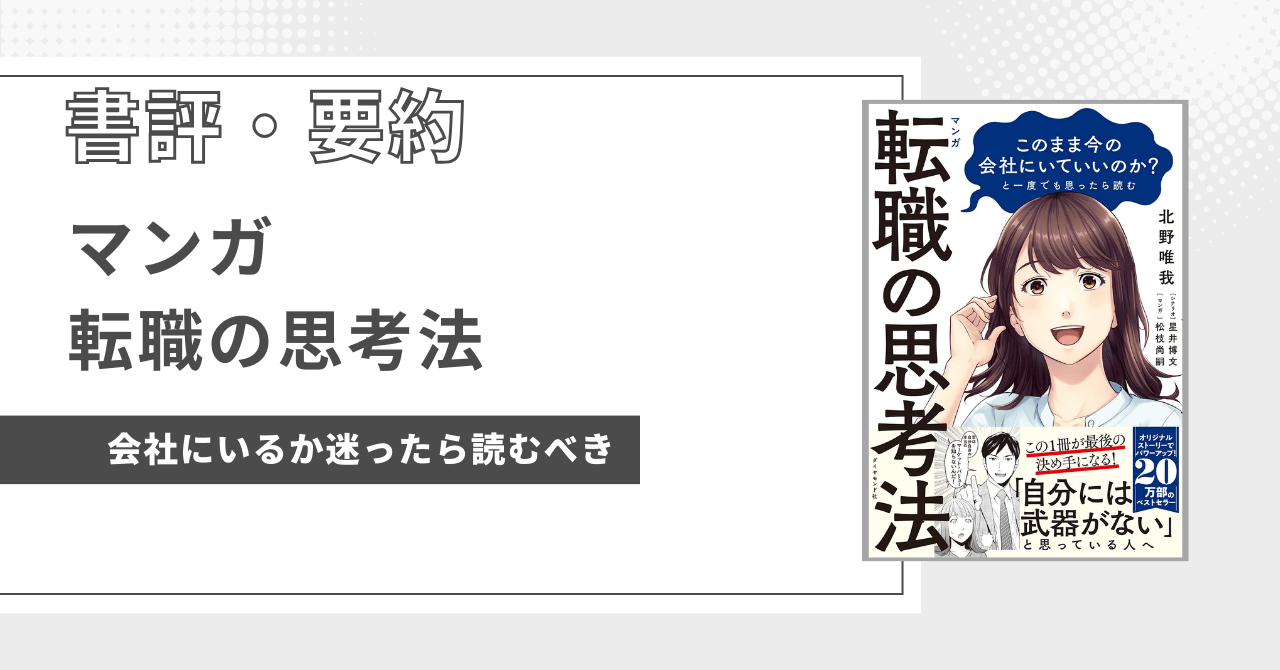


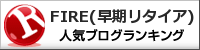
コメント