「論理的で頭の良いだけのビジネスパーソン」が活躍できる時代は終わりを迎えます・・・。
環境が目まぐるしく変化する時代。
あなたは、新時代に適応したニュータイプのビジネスパーソン足り得るでしょうか?
仮に少しでも不安を抱いたのであれば、山口 周氏が著した本【ニュータイプの時代】を読んでください。
ニュータイプの時代|概要
「ビジネスパーソンとしてバリバリ活躍して、稼いでやる!」
そんな野望を胸に、ロジカルシンキングを鍛えたり、自己啓発書を読み漁ったり、MBAの授業を受けてみたり。
何もしないで上司の命令に従うだけよりは、遥かに「優秀なビジネスパーソン」となれることでしょう。
しかし、これまでの「優秀なビジネスパーソン」が今後も活躍できるとは限らない。
環境が目まぐるしく変わり、王道とされてきた賢いビジネスパーソンの得意とする解決策の検討は時代に合わなくなってきました。
ニュータイプの時代では、変化を捉えた問題の発見・課題提起が求められる時代になっているのです。
そんな新時代に活躍するニュータイプになるため、24の思考・行動様式が記された【ニュータイプの時代】をご紹介します。
『ニュータイプの時代』おすすめ読者
- 勤勉で真面目なだけの自分に不安を抱くビジネスパーソン
- 将来的に向けて何を学べば良いか迷っている新人社員
- 社会人になるまえにキャリアについて考えたい大学生
ここで質問です。
「出世をして年収を上げたい・キャリアアップをしたい!」
「仕事のできるビジネスパーソンになって、周囲の評判をひっくり返したい!」
「ビジネス力を高めて、収入上げて、投資で不労所得を得たい!」
筆者「きつね」と同じく、あなたもそう考えたことはありませんか?
書籍から知識を得ることであなたの目的達成に近づきます。
ですが、本を購入すると費用もかかりますし、保管場所も負担になりますよね・・・。
そんなお悩みを持つあなたにオススメできるサービスがあります。
200万冊以上の本が読み放題になるAmazon(アマゾン)の電子書籍読み放題サービスです。
「あなたの年収を上げる・サイドFIRE実現を助ける・不労所得をゲットする」本が見つかります!
電子書籍よりも紙の本が好きという方もいるかもしれません。
ですが、初めてご利用の方は30日間の無料体験が可能です。
使いにくければ30日経過する前に解約をしましょう。
無料期間終了後は月額980円で使えます。
「1か月だと読み切れないし、1年だと長すぎるかも・・・。」
もちろん、いつでも解約できます。
ですので、3か月くらい集中して本を読み漁って解約するという使い方でも良いかもしれません。
>>Amazon Kindle Unlimitedを無料で試してみる\ 初回利用は30日間無料!200万冊以上の本が読み放題 /
ニュータイプの時代|章構成
『ニュータイプの時代』の章構成は以下になります。
各章に3~4つの思考・行動様式が記載されており、合計すると新時代を生き抜く24の思考・行動様式が示されています。
『ニュータイプの時代』章構成
- 第1章 人材をアップデートする6つのメガトレンド
― ニュータイプへのシフトを駆動する変化の構造 - 第2章 ニュータイプの価値創造
― 問題解決から課題設定へ - 第3章 ニュータイプの競争戦略
―「役に立つ」から「意味がある」へ - 第4章 ニュータイプの思考法
― 論理偏重から論理+直感の最適ミックスへ - 第5章 ニュータイプのワークスタイル
― ローモビリティからハイモビリティへ - 第6章 ニュータイプのキャリア戦略
― 予定調和から偶有性へ - 第7章 ニュータイプの学習力
― ストック型学習からフロー型学習へ - 第8章 ニュータイプの組織マネジメント
― 権力型マネジメントから対話型マネジメントへ
ニュータイプの時代|著者(山口 周 氏)紹介
著者は山口 周さんです。
アート思考やデザイン経営などの文脈で山口周さんの本を読んだことがある読者もいらっしゃるのではないでしょうか?
独立研究者・著作者・パブリックスピーカーという様々な肩書をお持ちですが、経歴や実績は本当に素晴らしいものがあります。
「山口 周」 とは
- 1970年、東京都生まれ
- 慶應義塾大学文学部哲学科卒業、同大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了
- 株式会社ライプニッツ代表
- 電通、ボストン・コンサルティング・グループ等を経て、
組織開発・人材育成を専門とするコーン・フェリー・ヘイグループに参画 - 『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』など著書多数
実は山口周さんの書籍は拝読させていただく機会が多いと言いますか、「気になる本を手にしてみたら著者が山口周さんだった」というケースが結構あります。
これまで拝読した本で言うと・・・
- ニュータイプの時代 新時代を生き抜く24の思考・行動様式
- 世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 経営における「アート」と「サイエンス」
- 知的戦闘力を高める 独学の技法
- 外資系コンサルの知的生産術 プロだけが知る「99の心得」
- 外資系コンサルが教えるプロジェクトマネジメント
- 外資系コンサルのスライド作成術―図解表現23のテクニック
- 外資系コンサルのスライド作成術 作例集: 実例から学ぶリアルテクニック
結構ありましたね。
「スライド作成術」の本はコンサル必読書として、こちらの記事でも紹介しています。
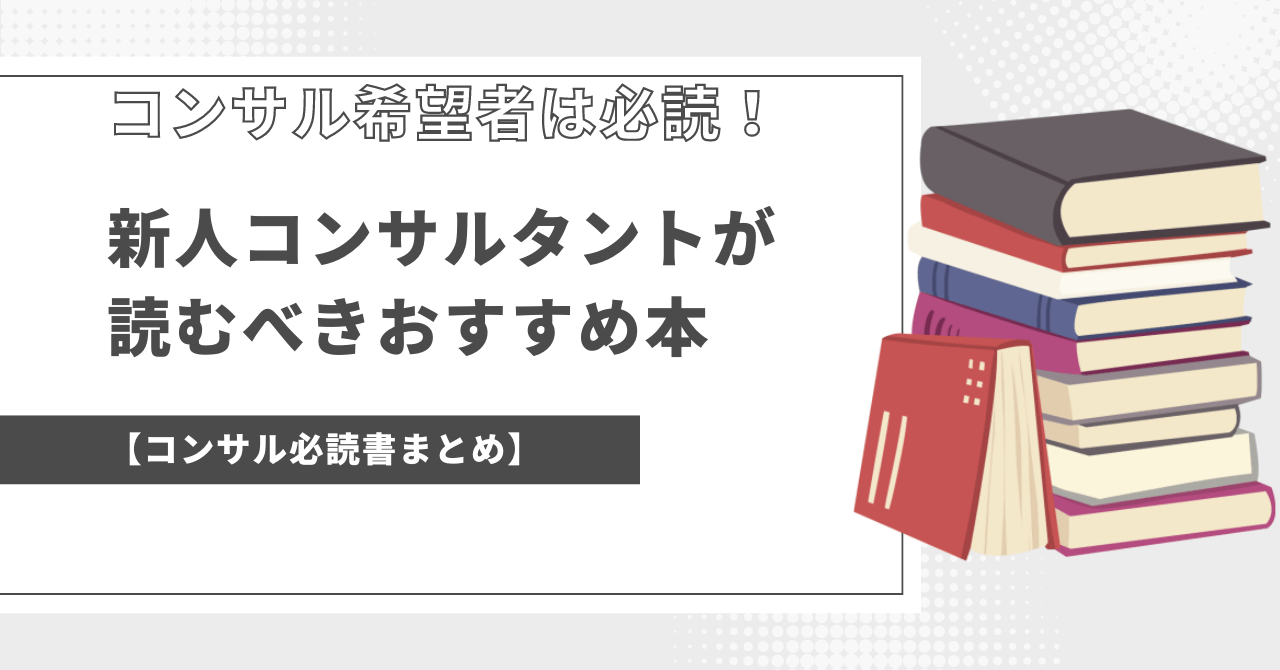
電通や外資系コンサルでお仕事をされていた経験に加え、哲学・美術史を専攻されていたというバックグラウンドから紡ぎだされる示唆はとても刺激的です。
「人文科学と経営科学の交差点」に活動をされているというテーマをお持ちで、私が【コンサルタント×カウンセラー】を志すきっかけになったのも山口さんの影響です。
ニュータイプの時代|書籍紹介
本書で定義されている「オールドタイプとニュータイプの違い」をまとめると下図のようになります。

第1章 人材をアップデートする6つのメガトレンド ── ニュータイプへのシフトを駆動する変化の構造
ニュータイプとして推奨する24の思考・行動様式を説明する前に、
変化の構造としての6つのメガトレンドが紹介するのが、この第1章の位置づけになります。
では、6つのメガトレンドとは何を指しているのか。
6つのメガトレンドとは?
- メガトレンド1 飽和するモノと枯渇する意味
- メガトレンド2 問題の希少化と正解のコモディティ化
- メガトレンド3 クソ仕事の蔓延
- メガトレンド4 社会のVUCA化
- メガトレンド5 スケールメリットの消失
- メガトレンド6 寿命の伸長と事業の短命化
高度経済成長期が終わり、先進国ではモノ余りの状態が定常化。
古き大量生産時代の遺産が環境を破壊し、情報技術・医療技術などの発展により人の生き方が変わる。
そんな時代が来ていることを改めて簡潔に記されています。
恐らく40代以上の方にとっては「何をいまさら」という感があるでしょう。
ですが、30代以下の人間は改めて、
自分の生まれ育った時代がこれまでの時代とは異なることを客観的に捉えなければなりません。
そうでないと、
過去の習慣が正しいものか、惰性なのか判断できなくなることでしょう。
まずはメガトレンドをしっかりと押さえましょう。
第2章 ニュータイプの価値創造 ── 問題解決から課題設定へ
20世紀後半以降の世界においては、
問題を発見・提起する人に価値があると説かれています。
世界の「あるべき姿」を構想し、
その姿に至るまでの課題を特定・解決にこだわることで、
結果としてイノベーションが起こる。
それがニュータイプの思考様式である一方、
オールドタイプは目の前にある見えている課題をイノベーションで解決しようと考え、
見えそうな未来へたどり着く方法を考える。
思考の順序が逆であり、能動的か受動的かの差があるように感じますね。
ニュータイプの価値創造
- 問題発見
1 問題を解くより「発見」して提案する
オールドタイプ 問題が与えられるのを待ち、正解を探す
ニュータイプ 問題を探し、見出し、提起する - 課題設定
2 革新的な解決策より優れた「課題」
オールドタイプ 課題に向き合わずにイノベーションという手段にこだわる
ニュータイプ 手段にこだわらず課題の発見と解決にこだわる - 構想力
3 未来は予測せずに「構想」する
オールドタイプ 未来を予測する
ニュータイプ 未来を構想する
第3章 ニュータイプの競争戦略 ── 「役に立つ」から「意味がある」へ
これからのビジネスにおいては「意味」の持つ力・「意味」を伝える力の重要性を増すといった内容です。
誰かにとって意味があるビジネスを、
課題解決ということにしっかりとフォーカスをして(ニッチだとしても)展開していく。
グローバルにビジネスを展開することが容易になった現代においては、
フォーカスをしたニッチなビジネスが広範囲に広がる可能性が高いということもあり、
「意味がある」を重視した競争戦略を提唱しているのが本章の内容になるかと思います。
ニュータイプの競争戦略
- 意味のパワー
4 能力は「意味」によって大きく変わる
オールドタイプ 目標値を与え、KPIで管理する
ニュータイプ 意味を与え、動機付ける - 限界費用ゼロ
5 「作りたいもの」が貫通力を持つ
オールドタイプ スケールを求めて市場におもねる
ニュータイプ 自分がやりたいことにフォーカスを絞る - ポジショニング
6 市場で「意味のポジション」をとる
オールドタイプ 「役に立つ」で差別化する
ニュータイプ 「意味がある」で差別化する - リーダーシップ
7 共感できる「WHAT」と「WHY」を語る
オールドタイプ HOWを示して他者に指示・命令する
ニュータイプ WHAT+WHYを示して他者をエンパワーする
第4章 ニュータイプの思考法 ── 論理偏重から論理+直感の最適ミックスへ
最近では至る所で語られるようになった「論理偏重」へのアンチテーゼです。
ロジカルシンキング・ルール・定量的マネジメントといったガチガチなマネジメント手法では、
意思決定に時間がかかるだけではなく、導き出された答えは差別化されていない「妥当なもの」になる。
VUCAな時代においては、そのように決めた判断も変化する環境に対応できない。
対応策として、論理と直感を使い分け、倫理観に基づいて意思決定に「遊び・余白」を持たせること。
論理が不要というわけではありませんが、
感情や倫理も大事にしていくことがニュータイプには求められるという示唆ですね。
ニュータイプの思考法
- 論理と直感
8 「直感」が意思決定の質を上げる
オールドタイプ 論理だけに頼り、直感を退ける
ニュータイプ 論理と直感を状況に応じて使い分ける - 野生の思考
9 「偶然性」を戦略的に取り入れる
オールドタイプ 生産性を上げる
ニュータイプ 遊びを盛り込む - 美意識
10 ルールより自分の倫理観に従う
オールドタイプ 組織のルール・規範に従って「無批判」に行動する
ニュータイプ 自らの道徳・価値観に従って「わがまま」に行動する - 意思決定
11 複数のモノサシを同時にバランスさせる
オールドタイプ 量的な向上を目指す
ニュータイプ 質的な向上を目指す
第5章 ニュータイプのワークスタイル ── ローモビリティからハイモビリティへ
「ハイモビリティ」という言葉を私なりに解釈すると、
自分が輝ける場所を探求しながら、成長を目指すワークスタイルだと思います。
大企業の会社員をしながら、個人で副業・複業をすることが普通になってきました。
様々な組織を渡り歩きながら、
多くの人と仕事をすることで「適応力」が高まっていくのではないでしょうか。
そのことが、結果として組織人としての価値も高めていく。
これからの時代は組織人としても個人としても活躍できる人間が輝けるのです。
ニュータイプのワークスタイル
- モビリティ
12 複数の組織と横断的に関わる
オールドタイプ 一つの組織に所属し、留まる
ニュータイプ 組織間を越境して起動する - 努力と成果
13 自分の価値が高まるレイヤーで努力する
オールドタイプ 今いる場所で踏ん張って努力する
ニュータイプ 勝てる場所にポジショニングする - モチベーション
14 内発的動機とフィットする「場」に身を置く
オールドタイプ 命令に駆動されて働く
ニュータイプ 好奇心に駆動されて働く - 知識と経験
15 専門家と門外漢の意見を区別せずフラットに扱う
オールドタイプ 専門家の意見を重んじる
ニュータイプ 素人の門外漢にも耳を傾ける
第6章 ニュータイプのキャリア戦略 ── 予定調和から偶有性へ
ワークスタイルの話を発展させて、キャリア戦略として捉えるとどうでしょうか。
環境は目まぐるしく変化する世の中に対し、
「ここだ!」と働く場所や職業を決めつけてしまうのは危険です。
一定の方向性を定める・考えることは必要ですが、
決めつけ過ぎず・こだわり過ぎずに様々な経験を得るために試してみることが重要です。
クライアントやプロジェクトによって様々な役割を求められるコンサルタント。
「適応力」という言葉はコンサルタントとして働く中でも重要だと思っており、
逆に言うと、自分に合う合わないを試す機会が圧倒的に多いのがコンサルタントという職業だと思います。
ニュータイプのキャリア戦略
- キャリア
16 大量に試して、うまくいったものを残す
オールドタイプ 綿密に計画し、粘り強く実行する
ニュータイプ とりあえず試し、ダメならまた試す - 逃走論
17 人生の豊かさは「逃げる」ことの巧拙に左右される
オールドタイプ 一箇所に踏み留まって頑張る
ニュータイプ すぐに逃げて、別の角度からトライする - 逃走論
18 シェアしギブする人は最終的な利得が大きくなる
オールドタイプ 奪い、独占する
ニュータイプ 与え、共有する
第7章 ニュータイプの学習力 ── ストック型学習からフロー型学習へ
「学ぶ」ことは時代を問わずに必要なこと。
しかし、「学び方」は変化させることが必要。
ニュータイプとしては、課題を解くためのサイエンスより、
リベラルアーツを元にした課題発見・問いの設定が重要となるそうです。
自分と異なる他者にも耳を傾けて、異文化からも新しい学びを得る受容力と
過去の学びに固執しないリセット力が良質な問いの設定に貢献することは肝に銘じておきたいですね。
ニュータイプの学習力
- リベラルアーツ
19 常識を相対化して良質な「問い」を生む
オールドタイプ サイエンスに依存して管理する
ニュータイプ リベラルアーツを活用して構想する - 気づき
20 「他者」を自分を変えるきっかけにする
オールドタイプ 要約し、理解する
ニュータイプ 傾聴し、共感する - アンラーン
21 苦労して身につけたパターン認識を書き換える
オールドタイプ 経験に頼ってマウントする
ニュータイプ 経験をリセットし、学習し続ける
第8章 ニュータイプの組織マネジメント ── 権力型マネジメントから対話型マネジメントへ
最後の第8章は組織について。
ヒエラルキーに縛られている組織では、
これからの時代に必要な柔軟性や自由さが失われてしまう。
同調や忖度が蔓延した組織では、
本来見るべき市場や顧客を見ずに、役員や上司のことを考える組織になってしまいます。
そんな組織に違和感を抱き、
立場に関係なく意見を言う優秀なビジネスパーソンを大事にする組織は大丈夫でしょう。
一方で、権力を重視して服従することを強制する組織は、
これから活躍するであろうビジネスパーソンに見切りを付けられてしまう。
組織で役職に就いている方には気付いてほしい現実です。
ニュータイプの組織マネジメント
- 権力の終焉
22 「モビリティ」を高めて劣化した組織を淘汰する
オールドタイプ 空気を読み、同調し、忖度する
ニュータイプ オピニオンを出し、エグジットする - 上司と部下
23 権威ではなく「問題意識」で行動する
オールドタイプ 肩書きや立場に応じて、振る舞いを変える
ニュータイプ 肩書きや立場に関係なく、フラットに振る舞う - 資本主義の脱構築
24 システムに耽落せず脚本をしたたかに書き換える
オールドタイプ システムに無批判に最適化する
ニュータイプ システムを批判し、修正する
ニュータイプの時代|読んでみての感想
ニュータイプが取るべき24の思考・行動様式。
私がコンサルタントとして働くうちに自然と実践できていたことが多いように感じます。
提唱されている全てが必ずしも正しいというわけでも、実践しないといけないという話でもありません。
とはいえ、従来の「お利口なビジネスパーソン」という在り方に少しでも違和感があるのであれば、
この本を読んで自分の意見を発信することから初めてみてはいかがでしょうか?
ニュータイプの労働環境として
今回ご紹介した【ニュータイプの時代】に記載された思考・行動様式を実践していくことで、あなたのキャリアや市場価値は磨かれていくはずです。
ニュータイプの働き方を実践しやすい職業の一例として、コンサルタントが挙げられると思いました。
職業として「課題特定と解決」が求められるのは当然です。
プロジェクトやクライアントが変わることで、否が応でも知識を塗り替えて人間関係も構築し直し、過去の知見を発信して課題解決をリードしていくことが求められます。
そんなコンサルタントという職業はプレッシャーも多いですが、現在ではホワイト企業として労働環境が整備されてきています。
コンサルタントに期待される役割や求められる成長率は変わらない一方で、過度なブラック企業感はなくなってきているというのは若手にとっては最高の環境となるかもしれません。
もしもあなたもコンサルティング業界について興味があれば、筆者「きつね」がコンサル業界特化の転職エージェントに相談したときの体験談記事をご覧ください。
コンサルタントとしてビジネスパーソンのスタートを切ったのですが、「より自分に適したファームがあるのでは・・・?」と思い、転職活動をした際の記事になります。
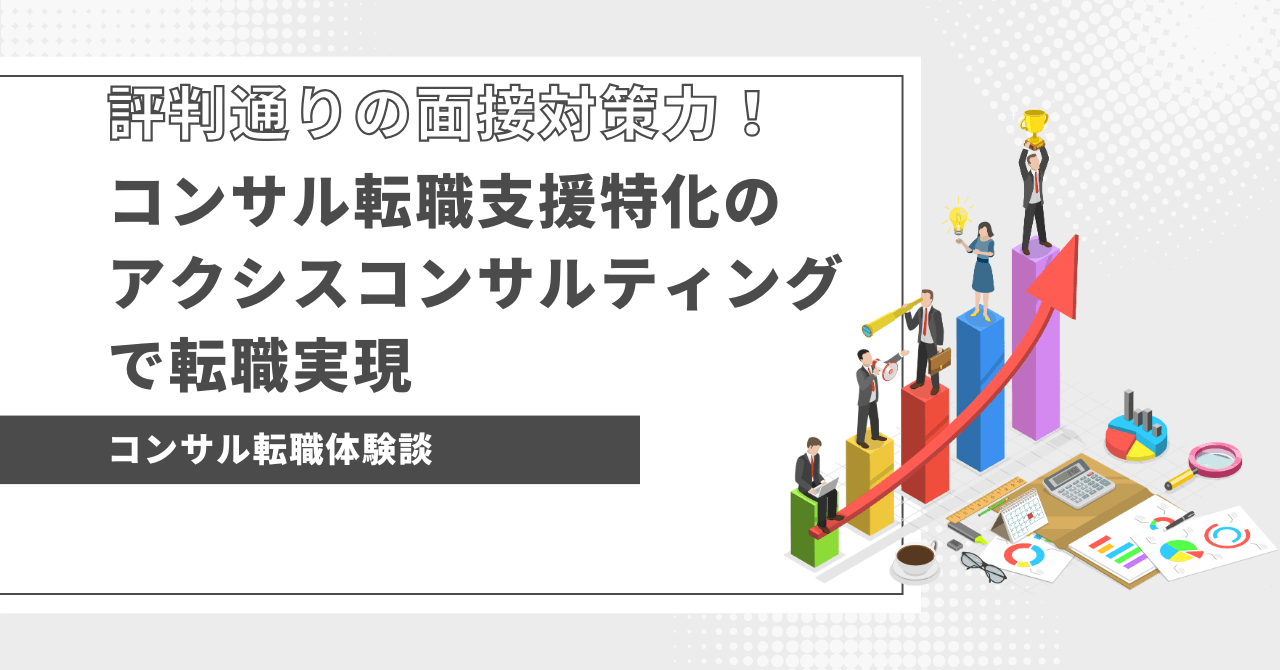
山口周さんが出版されている他の著書についても記事を書いているので、覗いてもらえると嬉しいです!
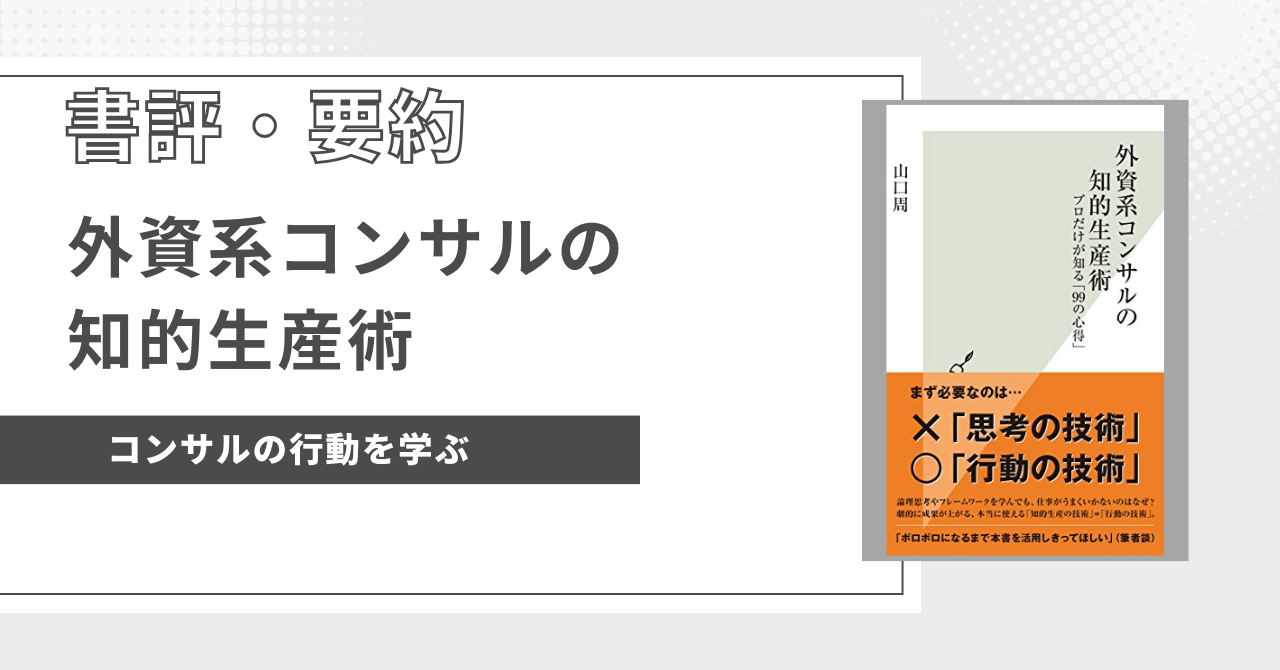
今回、筆者「きつね」が実際に読んだオススメの本をご紹介させていただきました。
他にもコンサルタントとして多くの本を読んだなかで、「これは必読!」と感じた本を厳選した紹介記事も書いています!
ぜひよろしくお願いいたします!
スキマ時間・休日の自己投資にオーディオブックサービスを活用
「休日を充実させる自己投資がしたい!」
「仕事で忙しいけど、スキマ時間に勉強をしたい!」
「たくさんビジネス書を読んで、活躍できるビジネスパーソンになりたい!」
あなたも同じ考えではありませんか?
そんな人にオススメできるのが、会員数250万人を突破したオーディオブック配信サービス【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】です。
【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】のおすすめポイント
- 年割プラン料金なら「月額833円」で15,000点以上のコンテンツを聴ける
- 14日間の「聴き放題お試し」が提供されている
- 厳選されたプロがナレーターとして本を朗読する
\ 14日間の「聴き放題お試し」あり /
本をたくさん買う人には、オーディオブックの方が安くなることもあります。
audiobook.jpの年割プラン料金なら「月額833円」で15,000点以上のコンテンツを聴くことができます。
14日間の「聴き放題お試し」が提供されているので、いちど気になる作品を聴いて継続利用するかお考えてみてください。
ちなみに、Amazonの子会社であるAudible Inc.が提供するオーディオブック・サービス【Audible】の料金は月額1,500円です。
外国語のコンテンツも多いので、英語学習をしたい方はAudibleをオススメします。
しかし、多くの方には月額880円で「聴き放題月額プラン」が使えるaudiobook.jpをオススメします。
audiobook.jpには定額の「聴き放題プラン」以外にも「チケットプラン」があります。
「チケットプラン」は通常価格 ¥1,500で1枚のチケットを購入します。
購入したチケットと聴きたい作品を交換することができます。
チケット交換した作品は永久に何度も聴くことができます。
何度も聴き返したいオーディオブックコンテンツはチケット交換がオススメです。
ビジネス書は1冊2,000円以上することもあるので、「聴き放題プラン」「チケットプラン」のどちらでもコスパが良いですよね!
最近ではAIが音声を読み上げるオーディオブックサービスもありますよね。
でも、厳選されたプロがナレーターとして本を朗読するaudiobook.jpが聴き心地は良いです。
ぜひ、スキマ時間や休日の自己投資にオーディオブック配信サービス【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】を活用してみてください!
\ 14日間の「聴き放題お試し」あり /
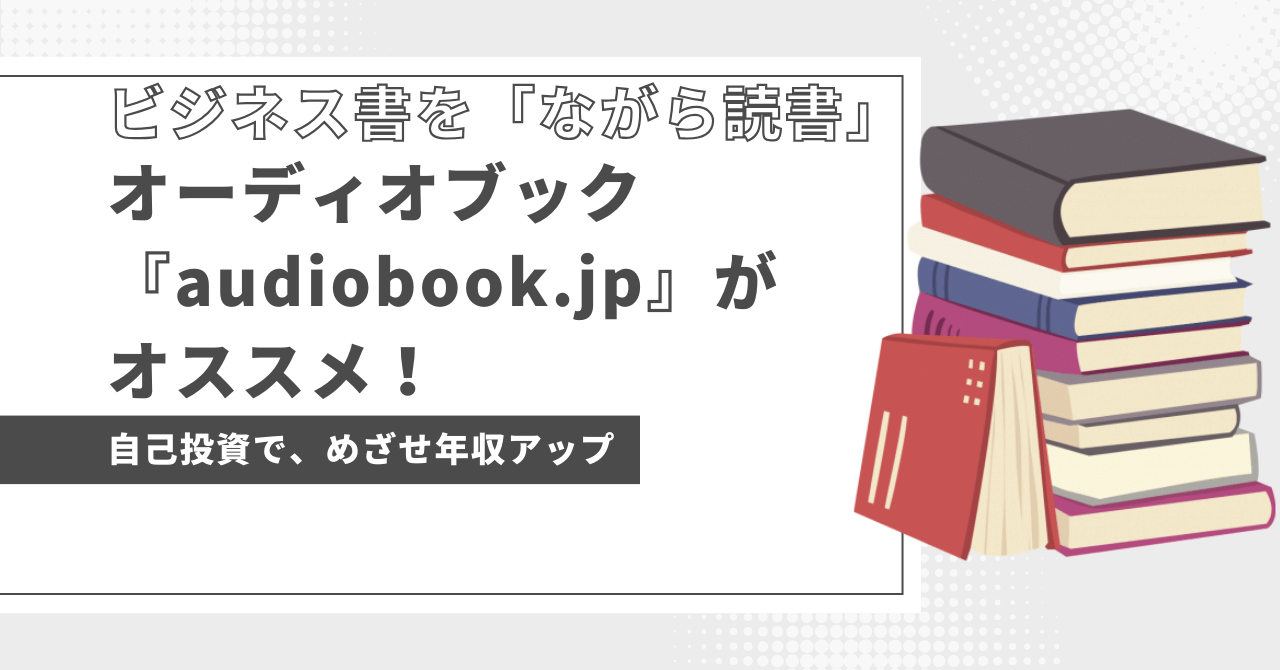
コンサル転職・自己研鑽に有効な資格は?
筆者「きつね」が実際に合格/勉強して、コンサルティング業務や自己研鑽に役立ったと思える資格を紹介します。
ぜひ、あなたのコンサル転職・自己研鑽の参考としてください!
コンサル転職前のオススメ資格/勉強記事
>>20代コンサルにおすすめ!年収を上げるIT資格【応用情報技術者試験】
>>【基本情報技術者試験】20代のコンサル転職で年収を上げるIT資格
>>【対策本あり】文系こそ取得すべき国家資格『ITパスポート』取得メリットを紹介
>>文系のIT未経験コンサルタントがプログラミングを学ぶべき3つの理由
>>【本も紹介】図解思考の技術・モデリング技術で概念を具体化【資格のUMTPもオススメ】
>>【合格体験談】マーケティング検定3級の体感難易度は簡単!勉強時間に参考書も紹介
>>【コンサル転職体験談】資格挑戦:マーケティング検定2級に挑戦|いきなり合格は無理?難易度は3級より確実に高い!
>>TOEIC400点台から800点台!コンサル実践の英語勉強法
>>【PMBOK】5つのプロセスと10の知識エリアはコンサル必修科目
>>新人コンサルにおすすめの資格「ビジネス会計検定3級」:簿記との違い・難易度・合格率をまとめた!
>>【オススメ】動画学習サービスSchoo(スクー)は評判がいい!
>>【無料あり】マーケティングが学べるオススメ動画学習サービス5選
コンサル転職に有利な資格合格に向けて
コンサル転職・転職後の自己研鑽として、資格取得を目指して勉強することはオススメです。
コンサルティング業界で働いていると、常に試験勉強をするように新しい知識をキャッチアップしないといけないので「勉強慣れ」をしておくとよいでしょう。
【STUDYing】中小企業診断士・応用情報技術者などをカバー
上記の資格をフルサポートしているわけではありませんが、スキマ時間で効率的に中小企業診断士などの資格合格を目指すなら、STUDYingも使うのがオススメです。
STUDYing中小企業診断士講座の2022年2次試験の最終合格実績が「業界No.1」
- 【合格実績 No.1!】
- ※1 2022年2次試験合格者数:167名
- 【合格者続々輩出中!】
- 2023年1次試験合格者数:510名
※1:同種の資格講座を提供している業者について、KIYOラーニング株式会社が2023年11月6日時点でHP上に記載されている合格者実績を調査した範囲での比較となります。
コンサルティング業界転職体験談まとめ
筆者「きつね」がコンサル転職を2回した体験談をまとめています!
30代で資産3,000万円を築いて、サイドFIREを実現したい。
そのためにコンサルティング業界で働いて年収を上げるため頑張っています。
転職をすることで年収を上げる、もしくは労働環境を改善させながら年収を維持することも可能です。
コンサル転職の成功は人それぞれですが、あなたのコンサル転職を成功させるため、ぜひ筆者「きつね」の体験談を参考にしてもらえたら嬉しいです!
コンサル転職体験談のオススメ記事
- 【オススメ】コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
- 【コンサル転職体験談】20代で年収1,000万!コンサルタントが年収を上げてきた思考法を伝授!
- 客先常駐=高級派遣?アクセンチュアやベイカレントなどの総合系コンサルが揶揄される理由
- 【コンサル転職体験談】転職候補はアクセンチュアソング、デロイト、PwC、インキュデータ
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職スケジュール公開!実際の転職ステップで要点を解説!
- 【3つの理由】「20代でコンサルタント就職・転職」が市場価値を高め、生涯年収を上げる!
- コンサル流「20代で市場価値を上げる休日の過ごし方」を紹介!暇な社会人こそ自己研鑽!
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職ならホワイト500の日系総合コンサルがオススメ!
- 【コンサル転職体験談】30代マネージャーが総合系コンサルファームを辞める理由は?
- 【コンサル転職体験談】面接でした逆質問を紹介!志望度を間接的に伝える重要要素
- 【コンサル転職体験談】コンサル就職・転職前に必読!ケース面接の対策本3選!
- 【コンサル転職体験談】職務経歴書|書き方のコツ!書類選考は全社通過!
- 【高年収】コンサルタントの種類?コンサルタントの職位・相場年収って?
- 【コンサル転職】転職活動おすすめの「企業の口コミサイト」を紹介!
- 【未経験30代のコンサル転職】コンサル転職に失敗する人の特徴3選
コンサル転職を成功させるため転職エージェントを複数利用
筆者「きつね」が内定までサポートしてもらった転職エージェントはアクシスコンサルティングでした。
>>コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
もちろんオススメですが、コンサルティング業界・ポストコンサル転職を目指すなら、転職エージェントは複数登録しておいた方が良いでしょう。
1つの転職エージェントから得られる求人情報は偏ってしまいますし、キャリア相談におけるセカンドオピニオンを得られることが複数の転職エージェントを活用するメリットです。
以下が筆者「きつね」も利用した転職エージェントです!
最近はコーチングにお金を払って転職をサポートするエージェントもいますよね。
ご紹介しているサービスはあくまで転職エージェントなので、無料で利用可能です!
転職活動の初期は複数の転職エージェントから求人情報をもらいつつ、担当さんとの相性も見極めましょう!
アクシスコンサルティング
アクシスコンサルティングは、コンサルティング業界の転職を目指すなら登録必須です。
コンサルティングファームの採用担当者と密に連携をしており、あなたの希望にあった非公開求人を紹介してくれます。
長年コンサル業界の転職を支援しているので、ケース面接対策もバッチリです。
\ コンサルティング業界に特化した転職面接サポート!! /
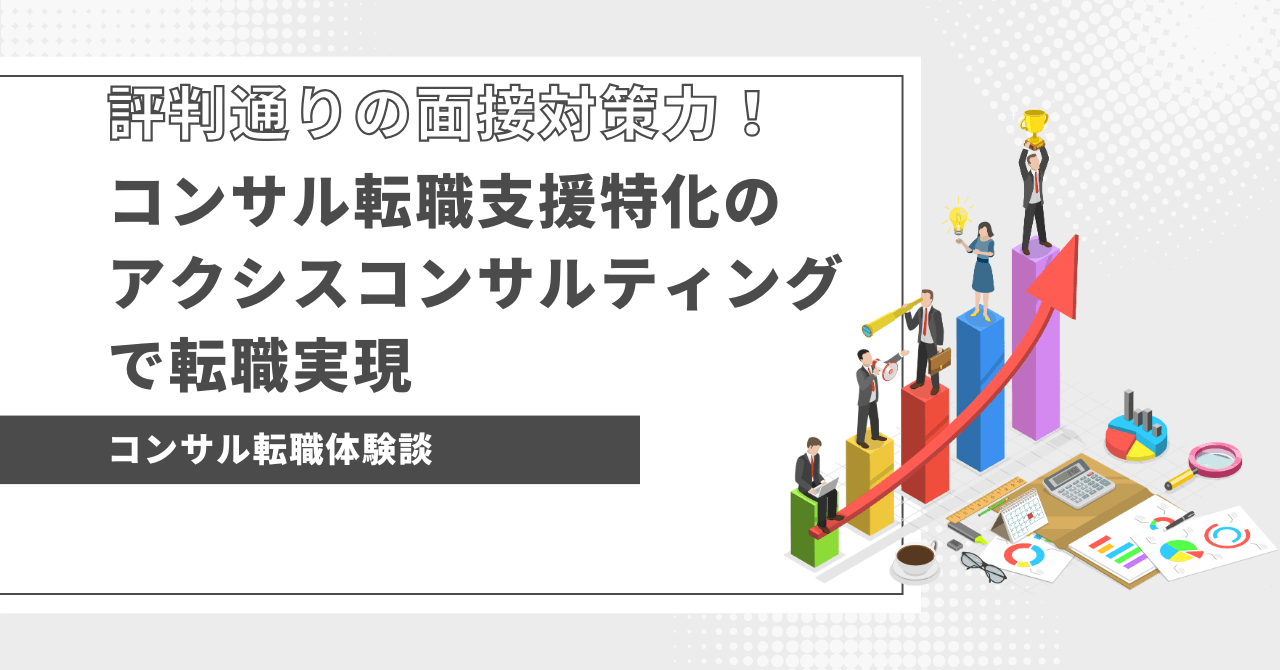
コトラ
ハイクラス転職に強く、特に金融業界の転職に強いのが「コトラ」です。
コンサル業界の転職も支援をしてくれます。
CFOや金融業界を専門としたコンサルを目指すなら登録必須だと思います。
コンサルタントとして金融業界の支援経験がある方も登録をしておくと良いでしょう。
\ ハイクラス転職に強い! /

マスメディアン
もし、あなたがコンサルティング業界にこだわらず、広告業界やマーケティング職の転職を考えているなら「マスメディアン」の登録がオススメです。
「宣伝会議」という広告やマーケティングに関する出版社が運営する転職エージェントで、出版社としてのコネクションを活かした転職情報が魅力的です。
多くの事業会社におけるマーケティング職や広告・クリエイティブ職の求人情報が掲載されています。
大手転職エージェント・転職サイトでは見つけにくい専門的な職種の情報が掲載されていますし、マスメディアンの担当者も職種特化で知識も豊富。
マーケティング職にキャリアチェンジしたい場合、マーケティング職としてキャリアアップを目指したい場合も力になってくれるはずです。
\ 広告・マーケティングの求人情報・転職なら! /
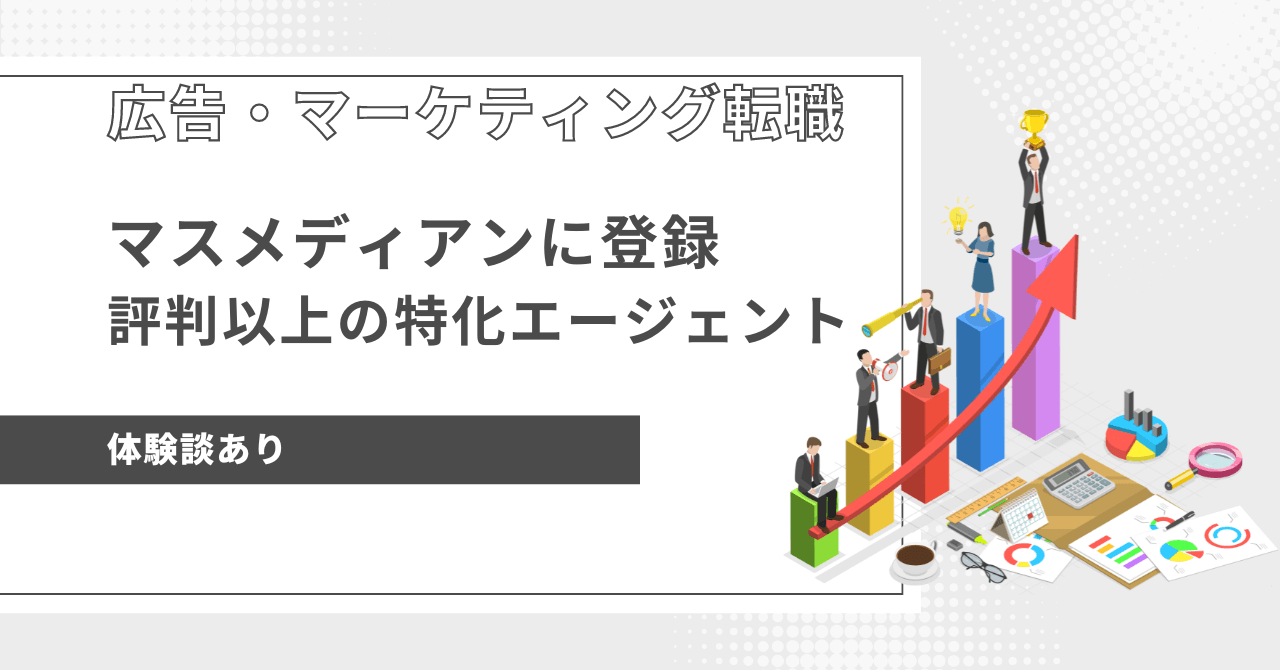
DODA
大手転職エージェントdodaは約12万件ある求人情報から、あなた専任のキャリアアドバイザーが希望に合致した求人情報をリストアップしてくれます。
ワークライフバランスを見直したり、業種・職種を広く検討したい場合はdodaがオススメです。
\ 大手ならでは!!安心のサポート力!! /
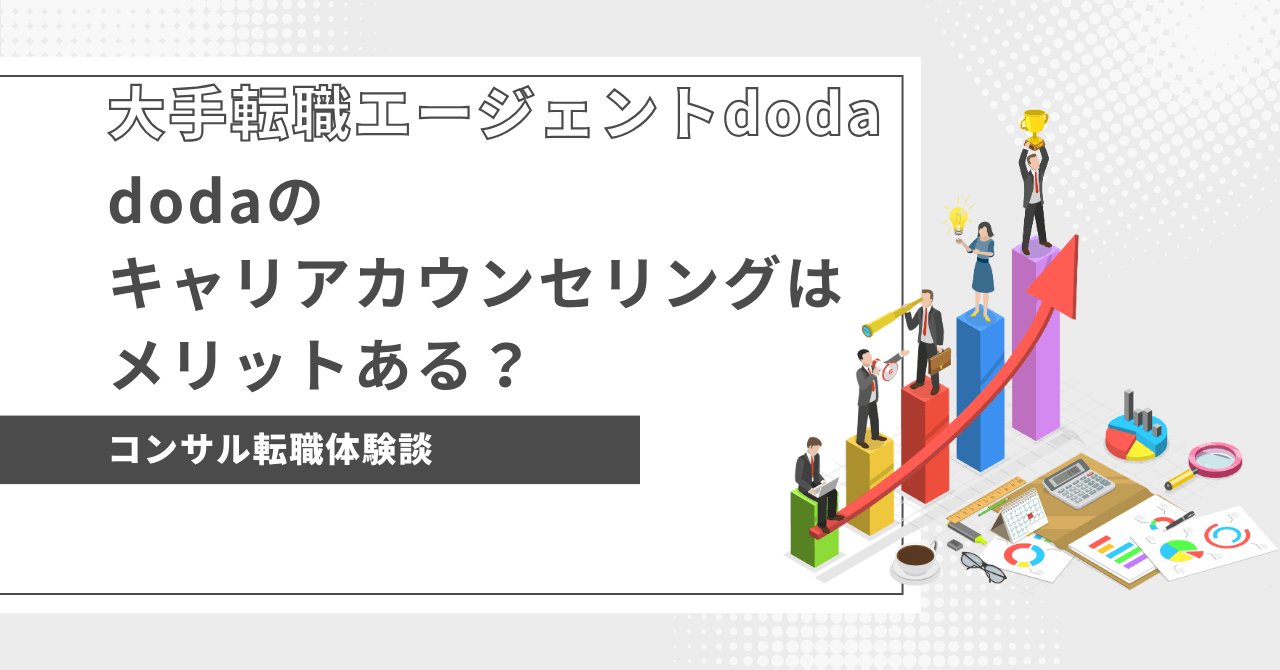
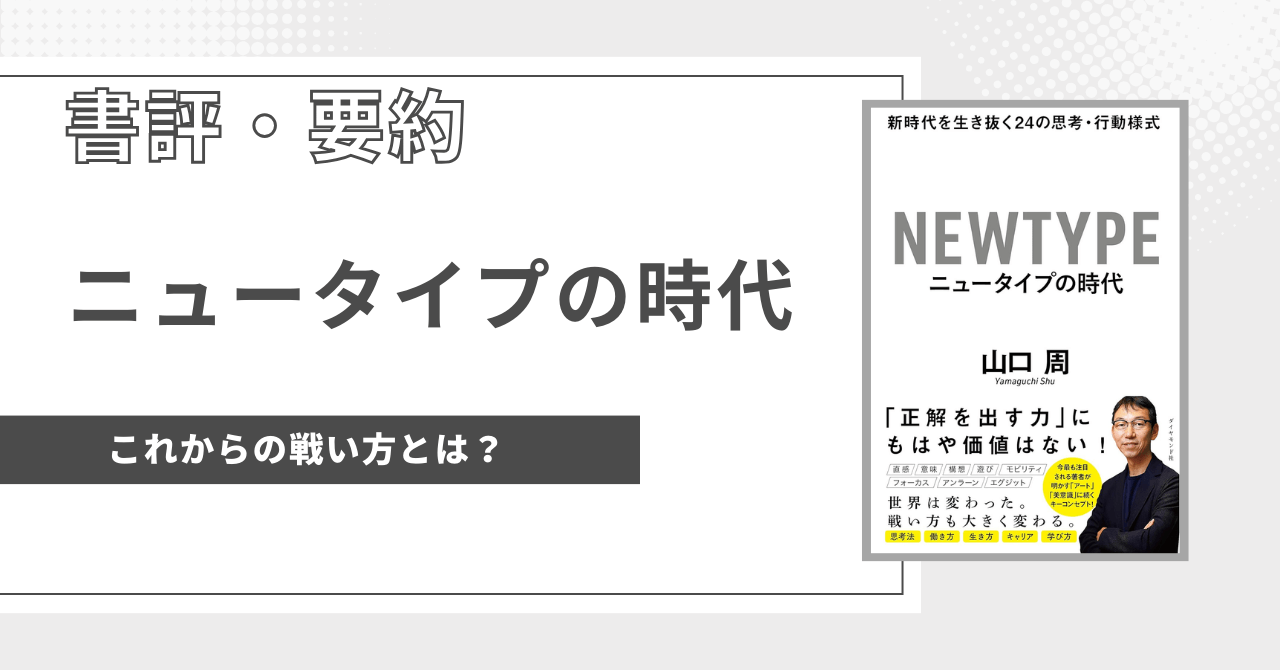


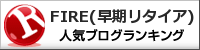
コメント