マーケティング戦略等を考案する際、論理的に考えるだけでは現状を打破できるアイデアや解決策が出てこないことがあります。
顧客分析や競合分析を行って収集された事実からは、納得感はあるものの独自性があって競争力のある施策が生み出されない。
チャレンジャーやフォロワーとして生きる企業が次の一手を模索する際に直面する機会の多い課題のように思います。
調査や分析に基づく「左脳思考」も大事です。
しかし、ロジカルシンキング(論理的思考)を重視する方が優秀なビジネスパーソンっぽいですよね。
この本ではロジカルな世界だけでは活きていけないビジネスの世界での武器として「右脳思考」の見直しを提唱しています。
右脳思考|概要
右脳思考|要約
- 「 ”観” 察し・ ”感” じ・ ”勘” を働かせる」ことをロジックに加えることで、生産性と創造性が向上する。
経営企画部やマーケティング部の方には、調査や分析といった論理的な世界での限界を感じている方がいると思います。
ロジカルが重視され絶対視されている風潮がありますが、その固定観念を打破して欲しいです。
更に今後の先進国では機能やスペックを重視したサービス企画・製品開発ではなく、顧客一人ひとりに寄り添ったサービス・製品を展開する企業が生き残っていくはずです。
顧客体験を磨いていく力の基礎を本書で学んでいきましょう。
右脳思考|おすすめ読者
- 新製品・サービス企画業務に従事している方
- プロモーション施策を検討している方
- ロジカルシンキング(論理的思考)を鍛えることに注力してきた方
ここで質問です。
「出世をして年収を上げたい・キャリアアップをしたい!」
「仕事のできるビジネスパーソンになって、周囲の評判をひっくり返したい!」
「ビジネス力を高めて、収入上げて、投資で不労所得を得たい!」
筆者「きつね」と同じく、あなたもそう考えたことはありませんか?
書籍から知識を得ることであなたの目的達成に近づきます。
ですが、本を購入すると費用もかかりますし、保管場所も負担になりますよね・・・。
そんなお悩みを持つあなたにオススメできるサービスがあります。
200万冊以上の本が読み放題になるAmazon(アマゾン)の電子書籍読み放題サービスです。
「あなたの年収を上げる・サイドFIRE実現を助ける・不労所得をゲットする」本が見つかります!
電子書籍よりも紙の本が好きという方もいるかもしれません。
ですが、初めてご利用の方は30日間の無料体験が可能です。
使いにくければ30日経過する前に解約をしましょう。
無料期間終了後は月額980円で使えます。
「1か月だと読み切れないし、1年だと長すぎるかも・・・。」
もちろん、いつでも解約できます。
ですので、3か月くらい集中して本を読み漁って解約するという使い方でも良いかもしれません。
>>Amazon Kindle Unlimitedを無料で試してみる\ 初回利用は30日間無料!200万冊以上の本が読み放題 /
右脳思考|著者紹介
ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)の日本代表も務めていらした内田 和成さんが著者です。
著者
- 内田 和成(うちだ かずなり)
- 1951年生まれ
- 慶應義塾大学大学院経営管理研究科 (KBS) 修了
⇒日本航空勤務
⇒ボストン・コンサルティング・グループ
⇒同社日本代表やシニア・アドバイザー
⇒早稲田大学ビジネススクール教授
姉妹本の「仮説思考」「論点思考」も併せて読むことで、左脳と右脳をフル活用した思考術を体得できます。
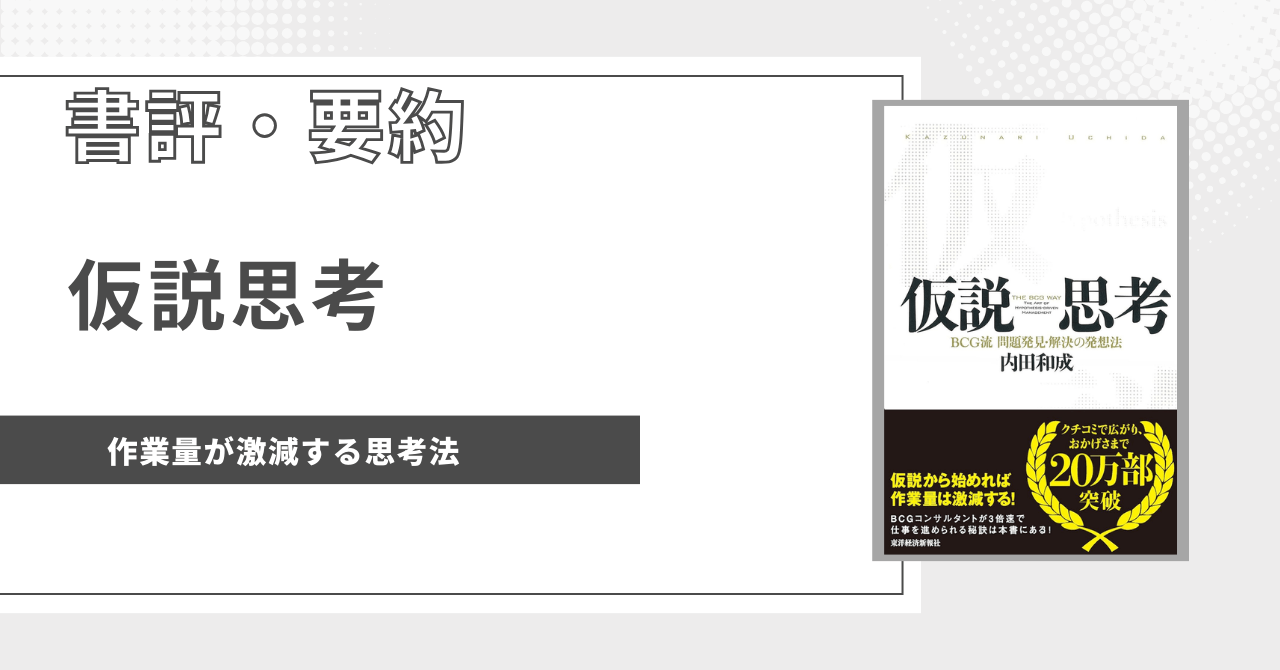
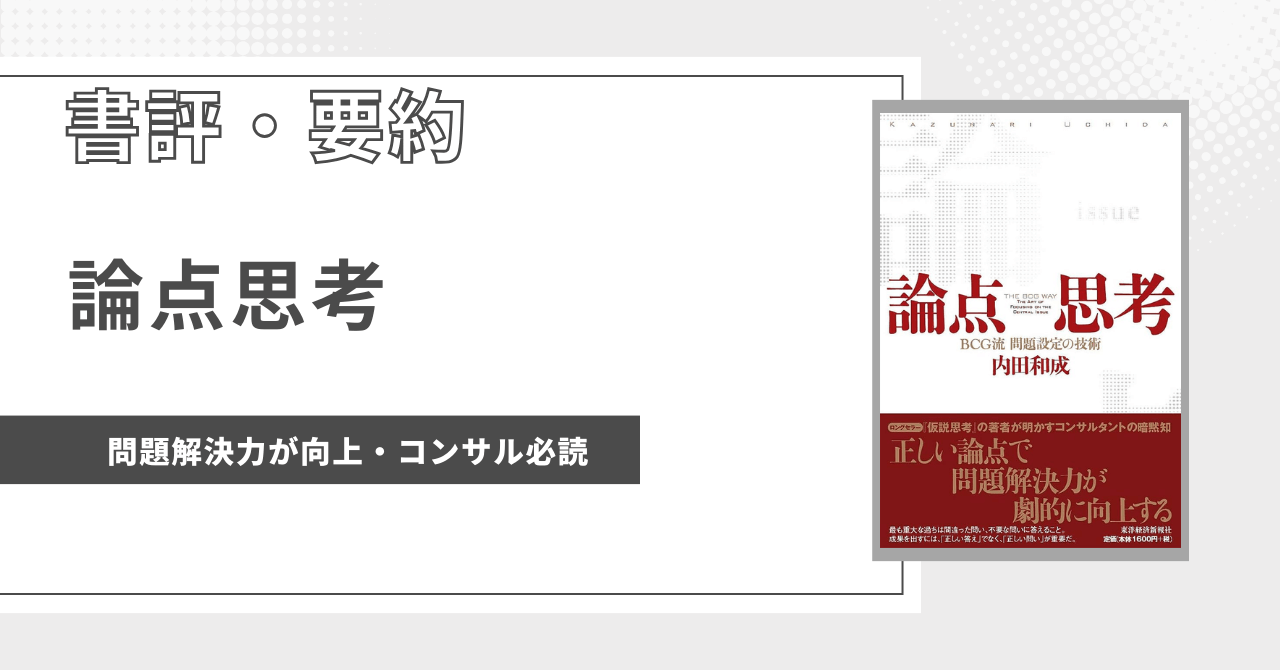
右脳思考|詳細
「観・感・勘」の ”3カン” の価値を見直すことで、ロジカル偏重により眠っていたクリエイティビティを呼び覚ましましょう!
右脳思考|章構成
各章の概要を記します。
1冊読む前に、どのような内容が書いてあるのか確認してみてください。
第1章:右脳を使うことが重要な理由
・人は感情の生き物。正しいけれど面白くない提案では、人は動かない。
・「右脳」による思いつきを「左脳」のロジックで理論武装する。
・相手が納得しない場合は「相手の感情と理屈」を因数分解して、どの因数に働きかければ良いか考える。
第2章:右脳の使い方
・仕事は3つのステージで成り立つ。
1.「インプット」
2.「検討・分析」
3.「アウトプット」である
・右脳⇒左脳⇒右脳という「右脳と左脳のサンドイッチ構造」で仕事を進める。
・「観・感・勘」でインプットとしての仮説づくりを行い、「ロジック」で課題特定。
最後に「腹落ち、感情移入」の為に右脳を活用したアウトプットを。
第3章:右脳で考え、左脳でロジカルチェック
・「面白い」「やりたい」から仕事を始めても良い。
・ただし、理論的に検証できないのであれば成功は見込めない。
・「キーコンセプトから結論を考えてロジックを逆算する」か「ストーリーを作って細部をロジックで詰める」ことが必要。
第4章:左脳で考えたロジックフローを右脳で肉づけ
・ロジックフローが完璧でも、意思決定者を動かすことができなければ提案は受け入れられない。
・人を動かすのは「論理性」「ストーリー」「ワクワク・どきどき」「自信・安心を与える」の4つ。
第5章:右脳「力」を鍛える
・生まれつきの差はあれど「勘」を鍛えることは可能である。
・①観察して感じたことを書きだし、②「観・感・勘」の検証を行い、③勘の軌道修正を繰り返すことで右脳力を鍛える。
・「相手の靴に自分の足を合わせる」という感情移入の考え方が、相手を納得させる上で重要。
第6章:ロジカルシンキングより直感を信じてみよう
・ロジカルシンキングが重要視され過ぎているのではないかと疑問を持ち、仕事のステージに応じて左脳と右脳を使い分ける。
右脳思考|読んだ感想
この本を読んだ後、「左脳を使わない決断」から始めようと思いました。
私は元々、論理思考が苦手でした。
感情優先型の人間だったので、コンサルタントになってからは弱点を補うようにロジカルシンキング、要は左脳思考を鍛えることに注力していました。
おかげでクライアントや上位職からも一定の評価を頂ける、価値を提供できる論理思考を身に付けました。
しかし、そこでぶち当たるのは「整理屋としての壁」でした。
気付かぬ内に、論理に頼り切るようになっていたんです。
この本でも書かれている「正しいけれど面白くない」という壁にぶつかっていました。
私本来の右脳思考を強みとして伸ばしていく。
そのためにも、左脳から始めない。
そのように決めました。
今回、筆者「きつね」が実際に読んだオススメの本をご紹介させていただきました。
他にもコンサルタントとして多くの本を読んだなかで、「これは必読!」と感じた本を厳選した紹介記事も書いています!
ぜひよろしくお願いいたします!
スキマ時間・休日の自己投資にオーディオブックサービスを活用
「休日を充実させる自己投資がしたい!」
「仕事で忙しいけど、スキマ時間に勉強をしたい!」
「たくさんビジネス書を読んで、活躍できるビジネスパーソンになりたい!」
あなたも同じ考えではありませんか?
そんな人にオススメできるのが、会員数250万人を突破したオーディオブック配信サービス【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】です。
【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】のおすすめポイント
- 年割プラン料金なら「月額833円」で15,000点以上のコンテンツを聴ける
- 14日間の「聴き放題お試し」が提供されている
- 厳選されたプロがナレーターとして本を朗読する
\ 14日間の「聴き放題お試し」あり /
本をたくさん買う人には、オーディオブックの方が安くなることもあります。
audiobook.jpの年割プラン料金なら「月額833円」で15,000点以上のコンテンツを聴くことができます。
14日間の「聴き放題お試し」が提供されているので、いちど気になる作品を聴いて継続利用するかお考えてみてください。
ちなみに、Amazonの子会社であるAudible Inc.が提供するオーディオブック・サービス【Audible】の料金は月額1,500円です。
外国語のコンテンツも多いので、英語学習をしたい方はAudibleをオススメします。
しかし、多くの方には月額880円で「聴き放題月額プラン」が使えるaudiobook.jpをオススメします。
audiobook.jpには定額の「聴き放題プラン」以外にも「チケットプラン」があります。
「チケットプラン」は通常価格 ¥1,500で1枚のチケットを購入します。
購入したチケットと聴きたい作品を交換することができます。
チケット交換した作品は永久に何度も聴くことができます。
何度も聴き返したいオーディオブックコンテンツはチケット交換がオススメです。
ビジネス書は1冊2,000円以上することもあるので、「聴き放題プラン」「チケットプラン」のどちらでもコスパが良いですよね!
最近ではAIが音声を読み上げるオーディオブックサービスもありますよね。
でも、厳選されたプロがナレーターとして本を朗読するaudiobook.jpが聴き心地は良いです。
ぜひ、スキマ時間や休日の自己投資にオーディオブック配信サービス【audiobook.jp(オーディオブックドットジェイピー)】を活用してみてください!
\ 14日間の「聴き放題お試し」あり /
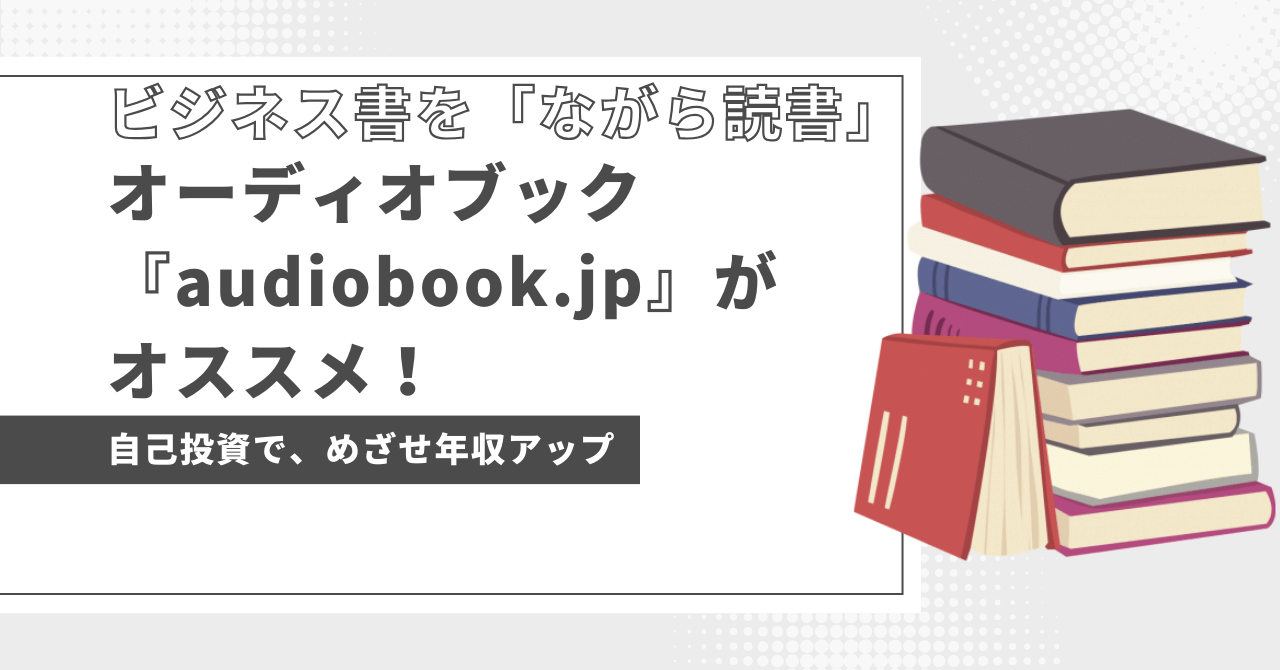
コンサルティング業界転職体験談まとめ
筆者「きつね」がコンサル転職を2回した体験談をまとめています!
30代で資産3,000万円を築いて、サイドFIREを実現したい。
そのためにコンサルティング業界で働いて年収を上げるため頑張っています。
転職をすることで年収を上げる、もしくは労働環境を改善させながら年収を維持することも可能です。
コンサル転職の成功は人それぞれですが、あなたのコンサル転職を成功させるため、ぜひ筆者「きつね」の体験談を参考にしてもらえたら嬉しいです!
コンサル転職体験談のオススメ記事
- 【オススメ】コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
- 【コンサル転職体験談】20代で年収1,000万!コンサルタントが年収を上げてきた思考法を伝授!
- 客先常駐=高級派遣?アクセンチュアやベイカレントなどの総合系コンサルが揶揄される理由
- 【コンサル転職体験談】転職候補はアクセンチュアソング、デロイト、PwC、インキュデータ
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職スケジュール公開!実際の転職ステップで要点を解説!
- 【3つの理由】「20代でコンサルタント就職・転職」が市場価値を高め、生涯年収を上げる!
- コンサル流「20代で市場価値を上げる休日の過ごし方」を紹介!暇な社会人こそ自己研鑽!
- 【コンサル転職体験談】コンサル転職ならホワイト500の日系総合コンサルがオススメ!
- 【コンサル転職体験談】30代マネージャーが総合系コンサルファームを辞める理由は?
- 【コンサル転職体験談】面接でした逆質問を紹介!志望度を間接的に伝える重要要素
- 【コンサル転職体験談】コンサル就職・転職前に必読!ケース面接の対策本3選!
- 【コンサル転職体験談】職務経歴書|書き方のコツ!書類選考は全社通過!
- 【高年収】コンサルタントの種類?コンサルタントの職位・相場年収って?
- 【コンサル転職】転職活動おすすめの「企業の口コミサイト」を紹介!
- 【未経験30代のコンサル転職】コンサル転職に失敗する人の特徴3選
コンサル転職を成功させるため転職エージェントを複数利用
筆者「きつね」が内定までサポートしてもらった転職エージェントはアクシスコンサルティングでした。
>>コンサル転職特化の転職エージェント『アクシスコンサルティング』は評判通りの面接対策力!
もちろんオススメですが、コンサルティング業界・ポストコンサル転職を目指すなら、転職エージェントは複数登録しておいた方が良いでしょう。
1つの転職エージェントから得られる求人情報は偏ってしまいますし、キャリア相談におけるセカンドオピニオンを得られることが複数の転職エージェントを活用するメリットです。
以下が筆者「きつね」も利用した転職エージェントです!
最近はコーチングにお金を払って転職をサポートするエージェントもいますよね。
ご紹介しているサービスはあくまで転職エージェントなので、無料で利用可能です!
転職活動の初期は複数の転職エージェントから求人情報をもらいつつ、担当さんとの相性も見極めましょう!
アクシスコンサルティング
アクシスコンサルティングは、コンサルティング業界の転職を目指すなら登録必須です。
コンサルティングファームの採用担当者と密に連携をしており、あなたの希望にあった非公開求人を紹介してくれます。
長年コンサル業界の転職を支援しているので、ケース面接対策もバッチリです。
\ コンサルティング業界に特化した転職面接サポート!! /
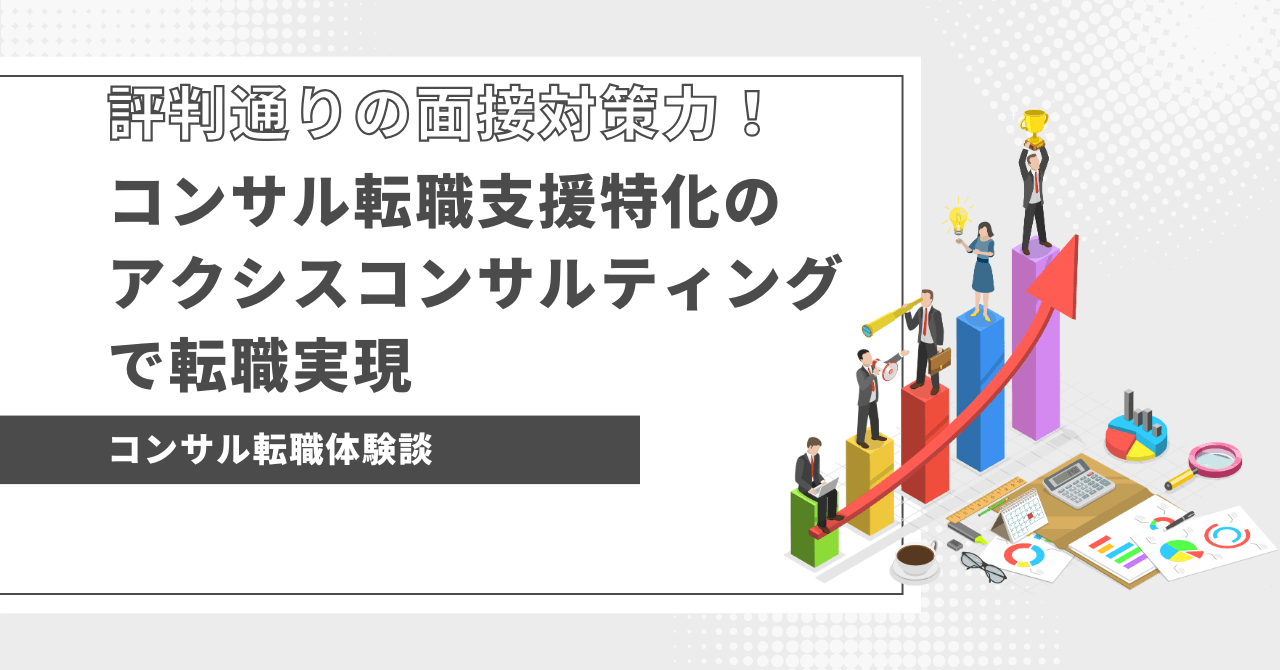
コトラ
ハイクラス転職に強く、特に金融業界の転職に強いのが「コトラ」です。
コンサル業界の転職も支援をしてくれます。
CFOや金融業界を専門としたコンサルを目指すなら登録必須だと思います。
コンサルタントとして金融業界の支援経験がある方も登録をしておくと良いでしょう。
\ ハイクラス転職に強い! /

マスメディアン
もし、あなたがコンサルティング業界にこだわらず、広告業界やマーケティング職の転職を考えているなら「マスメディアン」の登録がオススメです。
「宣伝会議」という広告やマーケティングに関する出版社が運営する転職エージェントで、出版社としてのコネクションを活かした転職情報が魅力的です。
多くの事業会社におけるマーケティング職や広告・クリエイティブ職の求人情報が掲載されています。
大手転職エージェント・転職サイトでは見つけにくい専門的な職種の情報が掲載されていますし、マスメディアンの担当者も職種特化で知識も豊富。
マーケティング職にキャリアチェンジしたい場合、マーケティング職としてキャリアアップを目指したい場合も力になってくれるはずです。
\ 広告・マーケティングの求人情報・転職なら! /
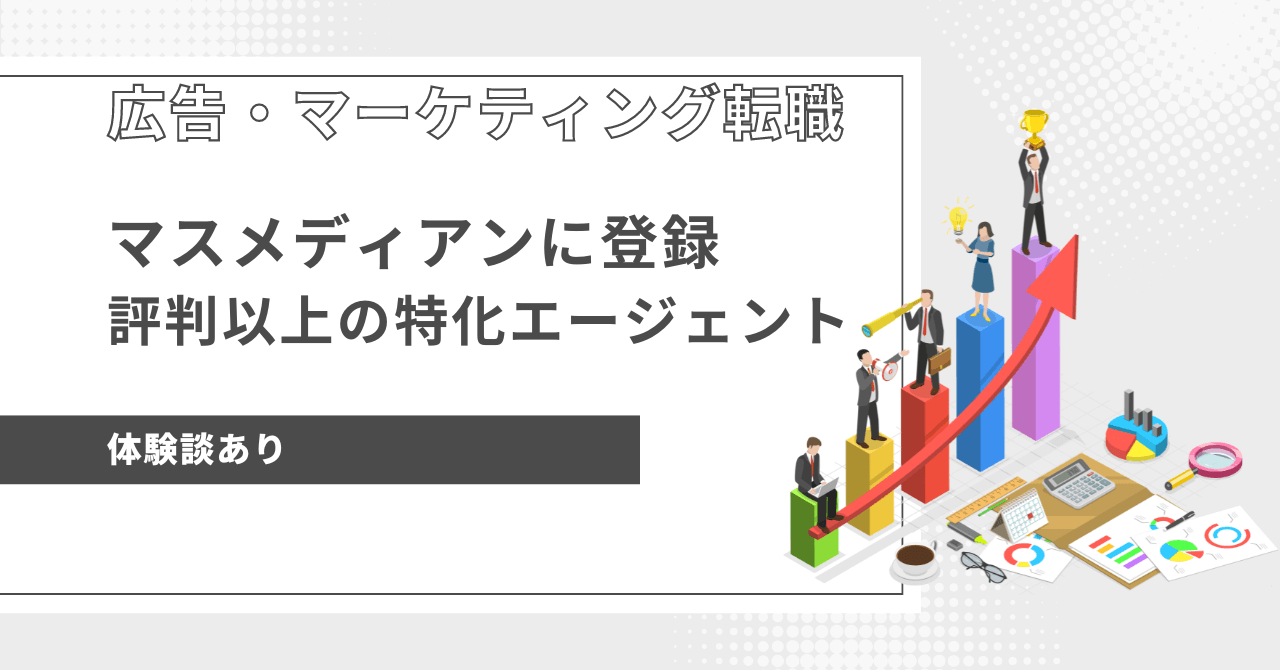
DODA
大手転職エージェントdodaは約12万件ある求人情報から、あなた専任のキャリアアドバイザーが希望に合致した求人情報をリストアップしてくれます。
ワークライフバランスを見直したり、業種・職種を広く検討したい場合はdodaがオススメです。
\ 大手ならでは!!安心のサポート力!! /
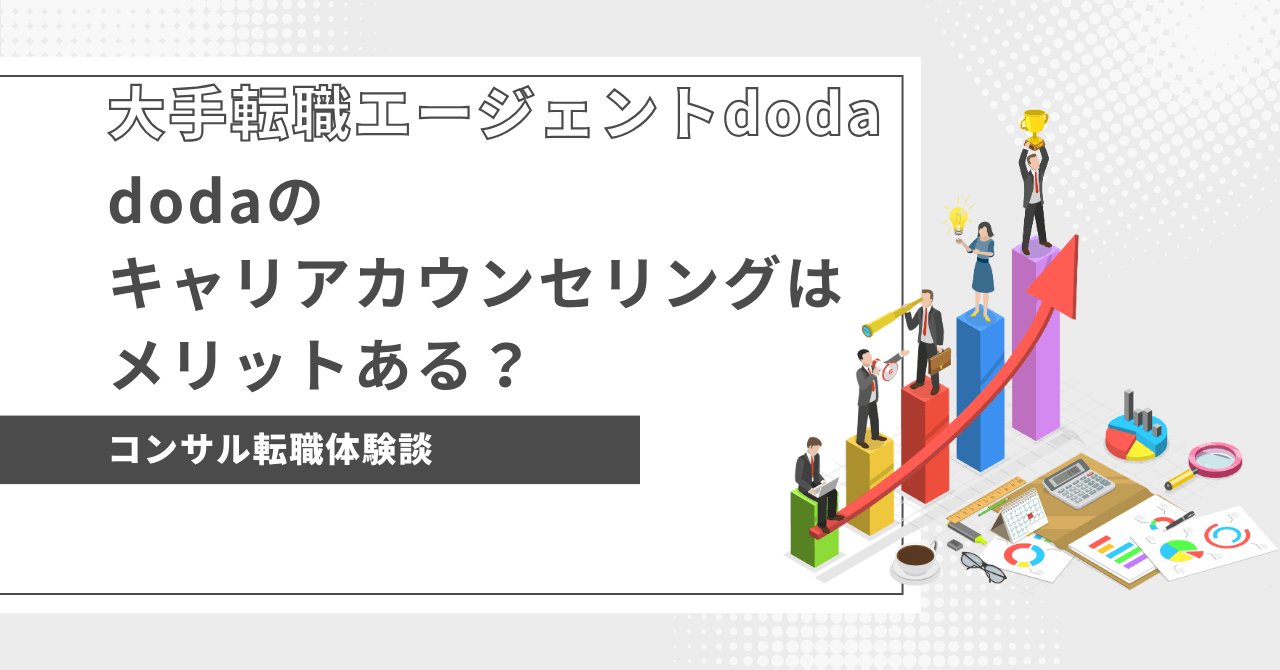
コンサル転職・自己研鑽に有効な資格は?
筆者「きつね」が実際に合格/勉強して、コンサルティング業務や自己研鑽に役立ったと思える資格を紹介します。
ぜひ、あなたのコンサル転職・自己研鑽の参考としてください!
コンサル転職前のオススメ資格/勉強記事
>>20代コンサルにおすすめ!年収を上げるIT資格【応用情報技術者試験】
>>【基本情報技術者試験】20代のコンサル転職で年収を上げるIT資格
>>【対策本あり】文系こそ取得すべき国家資格『ITパスポート』取得メリットを紹介
>>文系のIT未経験コンサルタントがプログラミングを学ぶべき3つの理由
>>【本も紹介】図解思考の技術・モデリング技術で概念を具体化【資格のUMTPもオススメ】
>>【合格体験談】マーケティング検定3級の体感難易度は簡単!勉強時間に参考書も紹介
>>【コンサル転職体験談】資格挑戦:マーケティング検定2級に挑戦|いきなり合格は無理?難易度は3級より確実に高い!
>>TOEIC400点台から800点台!コンサル実践の英語勉強法
>>【PMBOK】5つのプロセスと10の知識エリアはコンサル必修科目
>>新人コンサルにおすすめの資格「ビジネス会計検定3級」:簿記との違い・難易度・合格率をまとめた!
>>【オススメ】動画学習サービスSchoo(スクー)は評判がいい!
>>【無料あり】マーケティングが学べるオススメ動画学習サービス5選
コンサル転職に有利な資格合格に向けて
コンサル転職・転職後の自己研鑽として、資格取得を目指して勉強することはオススメです。
コンサルティング業界で働いていると、常に試験勉強をするように新しい知識をキャッチアップしないといけないので「勉強慣れ」をしておくとよいでしょう。
【STUDYing】中小企業診断士・応用情報技術者などをカバー
上記の資格をフルサポートしているわけではありませんが、スキマ時間で効率的に中小企業診断士などの資格合格を目指すなら、STUDYingも使うのがオススメです。
STUDYing中小企業診断士講座の2022年2次試験の最終合格実績が「業界No.1」
- 【合格実績 No.1!】
- ※1 2022年2次試験合格者数:167名
- 【合格者続々輩出中!】
- 2023年1次試験合格者数:510名
※1:同種の資格講座を提供している業者について、KIYOラーニング株式会社が2023年11月6日時点でHP上に記載されている合格者実績を調査した範囲での比較となります。
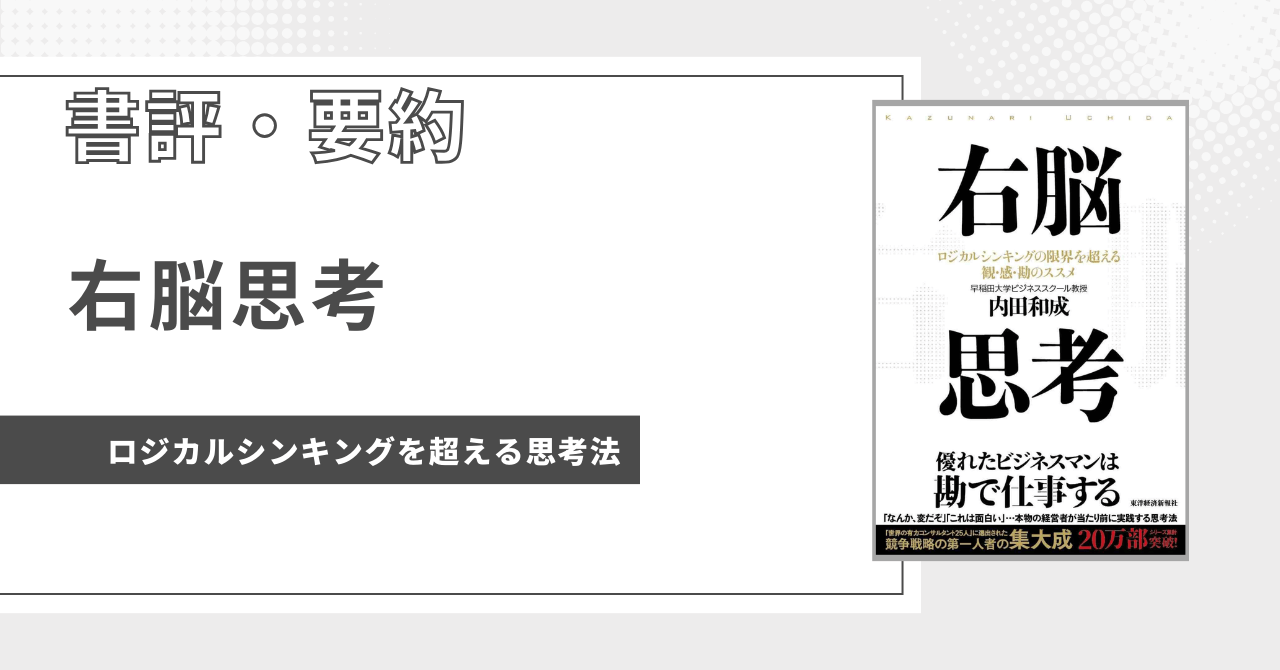


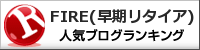
コメント